3/18の感動的なムーティ指揮・東京春祭オーケストラによるオープニングから約1か月、終盤に入ったハルサイでまた凄い名演を聴いた。ピエール・ジョルジョ・モランディ指揮によるプッチーニ『トゥーランドット』(演奏会形式)は、2022年の音楽祭のハイライトのひとつで、読響と東京オペラシンガーズの実力を鮮やかに聴かせる奇跡的な上演となった。
冒頭の合唱から、ブッチーニが遺作で描こうとした巨大なオペラのパノラマスコープが突然現れ、残酷なトゥーランドット姫のもとで求婚者を処刑する首切り人たちのクレイジーな狂気が溢れ出した。オーケストラも異常なほどの恐怖を掻き立て、打楽器群の衝撃が凄まじい。
指揮者はある意味、この冒頭場面をジャーナリスティックに表現していると思った。ある異常な統治下においては、凶器を持った者たちはこのようにおかしな狂騒状態に入ってしまう。もちろん、演奏家たちは譜面通りのことをやっている。設定はおとぎ話の世界だが、オペラはこのように聴く側の心に衝撃を与えてくる。現実と演劇の境界は薄い。
カラフのステファノ・ラ・コッラの声は英雄的で、大変な努力をともなって出すタイプの声ではなく、こういう凄い声は天性のものに違いないと咄嗟に思った。カラフやラダメスを歌うために生まれてきた人で、実際2015年にはシャイー指揮のカラフ役でスカラデビューを飾っている。現代にはこういう貴重な歌手がいるのだ…と驚きながら聴いた。
ティムール役のシム・インスンも温かみのある声で、全員が譜面なしで演技していた。リューのセレーネ・ゼネッティの清純で繊細な「お聞きください、王子様」は、アドレナリンが充溢していた空気を一瞬で変え、太陽の光で反射する宝石のように輝いた。多くの聴衆は3幕でのリューの最期を知っているので胸を打たれたのではないかと思う。原作にはない役で、プッチーニ家の小間使いドーリア・マンフレーディがモデルという説がある。
プッチーニの妻エルヴィーラが不倫を疑い、ドーリアを中傷したため彼女は自殺を図り、解剖の結果「処女であった」というエピソードは有名だ。プッチーニはドーリアの遺族に多額の慰謝料を支払った。
なかなか登場しないトゥーランドットは、2幕でようやく現れる。ブルーのアイシャドウで凄味を出したリカルダ・メルベートが、尋常でない「この宮殿で…」を歌った。先祖のロウ・リン姫の悲劇を語り、異国の男どもに辱められた姫の屈辱を、怨念を込めて歌いつづるのだが、指先まで爬虫類のようにわななわなさせて怒りの高音を出すメルベートは、悪霊そのものを表現していた。トゥーランドットは凄い役なのだ…と改めて思った。
千年前の先祖の怨念が乗り移っている存在なので、この世のものではない(彼女自身もそう歌う)。恐ろしいトゥーランドットから、愛情深いメルベートが透けて見えた。先日新国で観た『ばらの騎士』の、前回の上演では元帥夫人を演じていた歌手だ。
トゥーランドットの「異形さ」が強力であればあるほど、カラフの勇敢さとリューの可憐さが引き立つ。そして当然のように、氷の姫君の心境は某国の暴君を連想させた。
コミカルな宦官のピン・パン・ポンは、萩原潤さん(ピン)、児玉和弘さん(パン)、糸賀修平さん(ポン)が歌った。それぞれカラフルな違う色の蝶ネクタイをつけて、息の合った演技を見せてくれた。
バリトンがテノールより高い音域を歌ったり面白い工夫が凝らされていて、彼らが故郷を懐かしむ歌はどこかもの悲しさも漂う。毎回ピン・パン・ポンの「トゥーランドットなど裸になればただの肉」という歌詞には痛く共鳴する。原作では4人の道化的な存在をプッチーニは3人にしたが、音楽的にも正解だった。
ピエール・ジョルジョ・モランディはプッチーニのスペシャリストだが、過去に来日したことはあっただろうか? 親しい名前に感じられたのは、この指揮者の録音を聴いていたからだと思う。スカラ座で10年間オーボエ奏者として活動し、その間にムーティやパターネのアシスタント指揮者になったという。スカラ座のピットの「中の人」として、色々なスター歌手や色々な指揮を迎え、劇場で起こる様々なトラブルや困難も経験してきたと思う。指揮をする背中から、苦労を厭わず働いてきた人なのだろうなと想像した。
音楽はドラマティックで、読響からは底力のあるサウンドが次々と溢れ出したが、『トゥーランドット』特有のグロテスクな不協和音や、現代音楽に踏み込んだ解釈は強調されなかった。グロテスクな音を強調した『トゥーランドット』を聴いた後では、しばらく鬱が続くという経験を過去にしたが、指揮者はどのようにでも物語を作ることが出来る。モランディの「節度」が有難かった。
3幕の緊張感も素晴らしい。『リューの死』までを書いたプッチーニは、癌で亡くなる直前まで創造力は衰えていなかったのだ。『マノン・レスコー』から綺羅星のごとくはじまるヒット作の、さまざまな名旋律の破片が聴こえたが、さらに新しい冒険に踏み出しているプッチーニの若々しさが遺作には漲っていて、60代の早すぎる死がなければ、どんなオペラを書いていたのか惜しく感じられた。
「リューの死」以降のアルファーノによる補筆部分は、勢いで聴いてしまうこともあるが、モランディは正直すぎるのか、補筆部分はやや通俗的で薄い音楽に聴こえないこともなかった。ベリオによる補筆版はあまりに「不思議すぎ」なので、物語としてのカタルシスを感じるにはこちらを選ぶしかない。ラストでは、メルベートが一瞬のうちに悪霊を取り払い、可愛い姫になっていたのにびっくりした。
ムーティ、ヤノフスキ、モランディと名指揮者の演奏を聴き、見事なキャスティングの歌手たちを堪能した18年目の音楽祭はいつも以上に有難かった。コロナや戦争で来日できなかった演奏家もいて、全体をコーディネートしている音楽祭側の苦労は想像を絶する。
ハルサイが行われるのは一年のうち1か月だが、運営は365日続いていて、春に咲く桜の花のように普段は「見えない」のだ。感極まる公演を多く聴いた今年、東京・春・音楽祭が行われることの幸福を噛み締め、感謝の念を新たにした。音楽祭の「親心」に甘えて、幸せの上塗りを満喫するばかりの自分だった。
名指揮者モランディと読響による『トゥーランドット』は4/17にも上演される。
読響によるプッチーニ・シリーズは来年以降も予定されている。
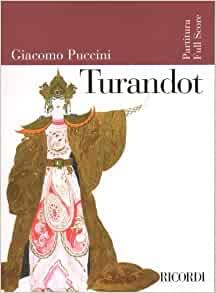
編集部より:この記事は「小田島久恵のクラシック鑑賞日記」2022年4月17日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「小田島久恵のクラシック鑑賞日記」をご覧ください。














