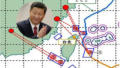Zhenikeyev/iStock
「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許しいただきたい。
(前回:「気候変動の真実」から何を学ぶか③)
第10章「誰がなぜ科学を壊したのか」
 この章は、本書の中で異彩を放っていると言える。これまで一貫してきた、科学的データと事実との感情を交えない客観的な突き合わせではなく、本書の著者が直接見聞してきた内容に基づく主観的な主張がメインになっているからだ。
この章は、本書の中で異彩を放っていると言える。これまで一貫してきた、科学的データと事実との感情を交えない客観的な突き合わせではなく、本書の著者が直接見聞してきた内容に基づく主観的な主張がメインになっているからだ。
よりハッキリと言うなら、地球温暖化・気候変動のような、科学的には未確定で現時点では断言できないはずの物ごとに対して、なぜ科学者・科学機関・活動家とNGO・マスコミ・政治家など、多様な気候関係者がみんな、説得のための「ウソ」に加担しているのか?と言うことだ。
この現象に対して、本書の著者は、秘密めいた陰謀などではなく、いろいろな関係者の視点や利害がどんどん一致してしまうからだと解釈している。その関係者として挙げられているのは、① マスコミ、② 政治家、③ 科学機関、④ 科学者、⑤ 活動家や非政府組織(NGO)、⑥ 一般市民である。
マスコミに関して重要な指摘は、インターネットの進展に伴って見出しが刺激的になった事実だ。クリックやシェア数を稼ぐために「ニュースはショッキングなほどウケル」が基本になってしまった。昨今も、マスコミは「世界各地への熱波襲来」で喧しい。しかしデータを冷静に見れば、気象現象としての寒暖は、局地的・一時的なものに過ぎず、熱い所があれば寒い所もあり、暑かった場所が今度は寒くなったりするのだ。
例えば日本では、今は暑い暑いと騒いでいるが、半年前の今年の冬には、厳寒に震えていたではないか?フランスも今は熱波に苦しんでいるが、春先には低温で霜害に悩まされていた(ワインの出来が懸念されている)。
マスコミ記者の「質」についても、当事者には耳の痛い指摘がある。記者の多くが、基本知識を持たず(=科学を知らず)、報告書やニュース内容の複雑微妙なニュアンスを理解できないこと。この点は、筆者もアゴラで何度か指摘したことがある。ちょっと考えたら分かりそうなことさえも質問しなかったのかね?と。「一番乗り競争」に勝ち、少しでも早く伝えるため、しっかり裏も取らずに発表してしまう軽率さに関しても、その例には事欠かない。
また、マスコミ記者の一部にとって「気候変動」は一種の「大義や使命」になってしまっている事実も重い。これは政治家から一般市民に至る幅広い層に対しても言える。つまり、人間由来のCO2が温暖化→気候変動の元凶であるとの「信念」(=実は科学的には全く不確実な命題)が、すべての議論の前提になっていることだ。日本で言えば、NHKや朝日新聞などが典型例である。彼らの頭の中では「人為的温暖化説」が、不変の真理として君臨しているようにしか見えない。
政治家については、ここでは省略する。より重要なのは、科学機関と科学者の役割である。科学では本来、実験・観測事実と論理的推論のみによって正誤が決まる。多数決や「権威」によっては決まらない。しかし実際には、国連機関などの「権威」が大きくモノを言う。
温暖化や気候変動問題では、世界気象機関やIPCCの「権威」がとても強い。特に日本では、政府から野党の共産党まで、全員が国連やIPCCの主張を正しいと認めている。だからこそ、脱炭素法は国会で全会一致で採択された。メダカの学校のごとく、ただ一人の国会議員も、気温やCO2濃度変化と脱炭素の意義に関して、疑問を挟まなかった。
筆者に言わせれば、その意味では日本学術会議も似たようなものではないかと思う。「人為的地球温暖化説」に関して、学術会議はどのような見解をお持ちであるのか、ぜひお聞かせ願いたいものだ(筆者のような無名の在野研究者の言い分など「権威」をお持ちの方々には全く耳に入らないとは思うが、今はネットの時代なので、一縷の望みを託す)。
本章には、非常に印象的な言葉が載っている。レフ・トルストイの1894年の哲学論文からの引用である。すなわち、
いかに難しい話であっても、そのことに関して先入観のない人に対しては、いかにその人の頭が悪くても説明が可能である。だが、いかに単純な話であっても、そのことをとっくに知っていると固く信じている人に対しては、いかにその人の頭がよくても説明が不可能である。
この言葉は、活動家・NGO・一般市民などにも当てはまるし、北欧のグレタ嬢にも妥当する。科学は本来、単純明快なものである。ただ単に、事実に基づいて、正しいか正しくないかが決まるから。
故に、種々の要因が入り込み話が複雑化しややこしくなってきたら、科学に関しては、本来の原点に立ち戻るのが良い。つまり、事実は何であるかをよく確かめることだけだ。その際「権威」に頼ってはならない。「裸の王様を見つめる子供の目」だけが必要である。
第11章「壊れた科学の修復」
本章では、科学の修復法として「レッドチーム」を置くことを提案している。「レッドチーム」とは、科学に関する報告書などを厳しくチェックする役目を担う科学者グループを指す。この対比は「ブルーチーム」で、その報告書の著者たちを指す。「レッド」の指摘・主張に対し、「ブルー」が反論する機会が与えられる。この仕組みは軍隊では以前から採用されており、エラーやギャップを見つけ、盲点を明らかにし、破滅的事態の回避にしばしば貢献する。ごくごく、合理的な仕組みと言える。
実はこれまでも、科学論文や科学的報告書には査読システムが存在し、何らかの審査・査読を受けてから発表されてきた。しかし本書の著者は、その上にもう一段、「レッドチーム」を置けと主張する。その理由は、これまでの審査方法には問題があるからだと。特に、その現場を直に見てきた本書の著者は、気候科学の評価報告書では、草案作成や審査プロセスは、客観性を高めるためにはなく、説得力が優先されやすいと言う。
一方、本書にも書かれているが、この「レッドチーム」案は、なかなか通らない。利害相反の関係からこの案を通したくない科学者たちが多数いるだけでなく、この案自体が抱えている難題があるからだ。
その第一は、誰がその「レッドチーム」に入るかの選定過程だろう。どういう人がこのチームに入るかによって、そのチームの「破壊力」は大きく違うから、メンバーの選定方法段階から大いに揉めることだろう。これまでの政府関係の審議会とか分科会とかと同様の選定方法ならば、毒にも薬にもならない「レッドチーム」になってしまう。一方、一家言ある「有志連合」で結成されるならば、科学的には説得力のある報告書ができると期待されるが、まとまるまでに紆余曲折するだろう。
本章の最後には、気候関連のニュースに、より批判的に接するためのヒントがいくつか書かれている。
- 科学者を「否定論者」「アラーミスト」呼ばわりする人は、政治やプロパガンダに関わっている。また、自然起源と人為起源の区別なく「気候変動」という言葉を使うのは、(恐らくは意図的に)いいかげんな考え方をしている証拠だ。
- 科学者の「97%が合意」といった主張も怪しい
- 気象と気候の混同も危ない
- 数字をはしょるのも怪しい
- 不安をあおる数字を背景情報なしに引用するのもよく使われる手
などなど。
「PARTⅠサイエンス」の全11章は、以上の内容で終わる。第10・11章は少し変わった内容と言えるが、温暖化に関する科学的な事実を扱った第1〜9章の内容は、筆者から見れば特に目新しいものではなかった(第3章のCO2収支に関する議論では見解が異なるが、これはまだ観測結果待ちの未解決問題でもあるので仕方がない)。その理由は、これらの内容は、筆者がかつて調べ学び、論文に書いた内容(pdf添付)とほぼ重複するからである。また、この論文で参考文献に挙げた諸書の内容ともほとんど一致する事実がある。
筆者が最初に学んだ本は、赤祖父俊一博士の「正しく知る地球温暖化」(誠文堂新光社刊)だった。この書は2008年7月に発刊され、筆者は同年12月に入手・読了している。それまで温暖化問題に関してモヤモヤしていた種々の疑問が、一挙に晴れる思いがした。
それ以後、種々の著書を読み情報を入手したが、この本に書かれた内容が裏切られたことはない。今読んでも、この本の内容とクーンの本書の間には本質的な相違点は見られない。すなわち、クーンの今回の著書は「地球温暖化に関する教科書の決定版」などと称され、実際その通りではあるけれども、日本には14年前からそれに匹敵する本が実在していた事実も忘れるべきではない。
赤祖父博士のこの本は、マスコミに取り上げられることも殆どなく、多くの読者を得ることはなかった。より多くの日本人がこの書を読み、文字通り地球温暖化を「正しく知る」ことができていれば、現在のバカげた「脱炭素狂騒曲」は起こらなかったかも知れない。
(次回に続く)
【関連記事】
・「気候変動の真実」から何を学ぶか①
・「気候変動の真実」から何を学ぶか②
・「気候変動の真実」から何を学ぶか③