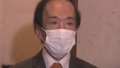14日に国会に提示される日銀総裁に、植田和男氏が内定したようだ。日経の「雨宮副総裁に打診」という報道は誤報ではなく、本人が辞退したもようだ。
かつてはタカ派だったが最近はハト派?
この人事は市場にとってもサプライズだったらしく、きのうは一時1ドル=130円近くまで円高に振れた。これは日銀審議委員だった当時の植田氏が、『ゼロ金利との闘い』にみられるようにタカ派だったため、相場が利上げ(YCCの撤廃)を見込んだものと思われる。
しかし植田氏は、きのう記者団に「現状では金融緩和の継続が必要である」とコメントしている。昨年7月の日経新聞の記事では「拙速な引き締め避けよ」と論じている。
現在の異例の金融緩和が微調整に向かない枠組みになっている点にも留意が必要だ。異例の金融緩和を2%のインフレが持続的に見込まれるまで継続すると宣言していることが緩和効果を発揮している。従ってインフレ率の少しばかりの上昇に対し政策を正常化方向へ微修正すると、一種の約束やぶりになってしまう。
審議委員だった時期に、将来インフレになっても引き締めないと約束する時間軸政策を考案した植田氏は、黒田総裁の「期待に働きかける」政策を否定していない点ではハト派である。
ただ彼は「インフレ率は23年後半にかけてせいぜい1%程度」とみていたが、その後コアCPIは4%を超え、エネルギー価格を除いたコアコアCPIでも3.0%である。「約束破り」のコストとどっちが大きいかは再考の余地があろう。
ゼロ金利は永久に続かない
問題はバランスシートである。日銀の保有する国債残高は昨年12月末で555兆円で、8.8兆円の評価損が出た。日銀の自己資本は(引当金などを入れて)約11兆円なので、あと4兆円の損が出ると債務超過になるが、それ自体は問題ではない。日銀が国債を売却することはないので評価損は心配していない、と黒田総裁は国会で答弁している。
しかし日銀当座預金の付利は、翌日からキャッシュで発生する。日銀は長期金利(国債)を超短期金利(付利)に置き換え、金利リスクを増やしてしまった。付利は今はゼロ(一部マイナス1%)だが、これが誘導目標なので、政策金利が上がると付利も上がる。1%上がると、毎年5.55兆円の支払い金利が発生する。その財務リスクは、黒田総裁も国会で認めた。
外資が空売りをかけても、日銀が国債を買う原資は無限にある。本質的な問題は統合政府の支払い能力だが、これも今のところ大きな問題はない。もし市場が政府の支払い能力に疑問をもっていたら、国債の金利はもっと大きく上がっているはずだ。
しかし長期的には、何が起こるかわからない。かつて植田氏は2020年12月の日経新聞で、MMTにも一理あると書いた。財政赤字を拡大し、政府によるネズミ講をずっと続けろという主張は、ゼロ金利で長期金利<名目成長率の状態が今後も永久に続くとすれば成り立つ。
それは火災保険をかけないで火事が起こらないことを祈るようなものだから、平時には保険料の分だけもうかる、悪くない賭けである。だが火事が起こってから火災保険には加入できないので、一定の保険としての財政規律は必要だ。
彼の理解はブランシャールの日銀レクチャーとほぼ同じで、現在の「新主流派」のマクロ経済理論ともいえる。ここではゼロ金利がいつまで続くかが問題だが、今それが終わりつつある。YCCからの撤退は不可避だが、問題はその先である。
新総裁の仕事は債務管理
植田氏は『ゼロ金利との闘い』の結びでこう書いた。
日銀は1998年施行の新日銀法で独立性を高めたが、独立性が高まる前の旧日銀法には日銀が債務超過に陥った場合に政府が自動的にこれを補填するという条項が含まれていた。しかし、この条項は新日銀法では消えている。[…]民主主義の下では、独立性の高い中央銀行がとれる、あるいはとってよい財務リスクには限りがあると考えるべきだろう。
日銀の財務リスクとは、その保有資産が大きく減価し、政府が救済する状態になることだ。もし日銀がYCCから撤退して、長期金利が1%超に上がると債務超過になり、債務の削減を迫られるだろう。
このうち国債は、統合政府でみると政府債務と中央銀行の資産が相殺できるので、理論的には解決法がある。たとえば国債を徐々に永久債で借り替えれば、売却しないで実質的に政府債務を減額できる。これは日銀当座預金の金利がゼロのうちにやったほうがいい。
だが株式は、日銀が保有する時価総額約50兆円の一部を売却する方針を示しただけで、株価が暴落するだろう。これを基金に移管し、SWF(政府系ファンド)を設立して海外の資源を買う活用法もある。
いずれにしても植田総裁の最大の任務は、緩和か引き締めかといったフローの微調整ではなく、ゼロ金利が終わった時代の債務管理である。今すぐ何かが起こる状況ではないが、長期的な時間軸を示して期待に働きかける必要がある。