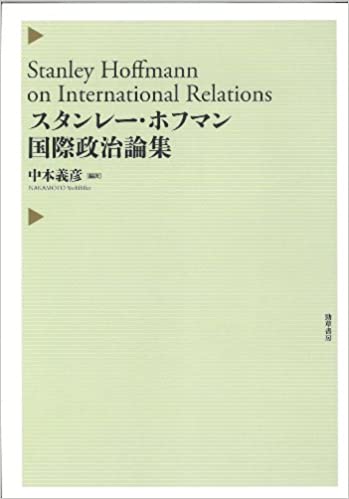blackred/iStock
ロシア・ウクライナ戦争には、多くの日本人が高い関心を持ったこともあり、メディアでは、連日のように「国際政治」を専門にする学者や識者と言われる人たちが、この戦争のさまざまな側面や展開を解説しています。我が国において、いわゆる「国際政治学者」が、これほど世間に注目されたことは、これまでなかったでしょう。
日本の国際政治学・アメリカの国際関係論
日本の「国際政治学」は、同学の本場ともいえるアメリカの「国際関係論」に比べると、学問的に多様であるところに特徴があります。
すなわち、日本の国際政治学には、人文科学の側面が強い「国際政治史」や「政治外交史」と社会科学の手法に依拠する「理論研究」、さらには「地域研究」や「政治思想史」といった、さまざまな専門分野が共存しているのです。
これは学問の方法論上の多様性を擁護する上では好ましいことなのでしょうが、市民や学生が国際政治学を体系的に理解することを難しくしているかもしれません。
国際政治学は、アメリカでは「国際関係論(IR:International Relations)」と呼ばれています。この国際関係論は、政治学の自立した分野として発展してきました。ですから、国際関係論はアメリカの大学では、例外的な場合を除いて、ほとんど政治学部(Department of Political Science/Politics)や行政学部(Department of Government)で教えられています。
日本では「国際政治学者」という肩書が流通していますが、アメリカでは「政治学者」あるいは「国際関係研究者(IR scholar)」が一般的です。
国際関係論は、かつて「アメリカの社会科学」といわれたことがありました。この学問は、スタンレー・ホフマン氏によれば「圧倒的にアメリカで研究されてきたために、国際関係論は本質的にアメリカ的な特徴を帯びてきたし、他国で真剣な研究対象になりつつあるか定かではない」という状態でした(『スタンレー・ホフマン国際政治論集』119ページ)。今から約45年前のことです。
そのために、国際政治学はアメリカ以外の国家では役に立たないと勘違いされることがあります。ある日本の学者は、「国際政治学は…アメリカ的な特徴を持つ。それを日本に輸入してみたところで…アメリカとその関係国との相互作用の理解には有用であっても、日本が直面する固有の課題についてまで、解答を用意するものではない」(『日本の国際関係論』勁草書房、2016年、180ページ)と断言するくらいです。
確かに、50年くらい前の国際政治学は、アメリカの政治学者による、アメリカの対外政策のための学問だったかもしれません。しかしながら、その後、社会科学としての国際関係論は、世界の動きを説明する学問として、アメリカのみならず世界各国の政治学界で鍛えられました。国際政治学/国際関係論がアメリカ国籍の研究者に「独占」されていた時代は、とっくに終わっています。
世界の国際関係論
今では、世界の多くの国々で国際関係論は教育・研究されると共に、アメリカ人以外の研究者が、この学問に参入しています。このことをジョン・ミアシャイマー氏(シカゴ大学)は、以下のように的確に指摘しています。
国際関係論の研究者はアメリカ中心主義で、視野を広げる必要があるとよく言われる。私はそう思わない…国際学会(ISA)の年次大会のプログラムに目を通しただけでも、国際関係研究者が地球村に住んでいることは明らかである。このような多様性は世界中の若者が大学に進学し、国際関係論を学ぶようになるにつれ、時間の経過とともに大きくなっていくと思われる。つまり、アメリカの学者は、その数の多さゆえに大きな影響力を持っているわけではない…国際関係論におけるアメリカの優位性は、世界中から多くの優秀な大学院生がアメリカにやってきて、アメリカのキャンパスで知的な状況を支配している理論や手法が一流の研究者になるための不可欠なツールであると教えられるという事実によって強化されている。そして、(アメリカの)大学院で学んだことを活かして、アメリカだけでなく他の国でも活躍する人が多いのである。
現在の国際関係論はアメリカの社会科学ではありません。国際関係論は、世界を動きや国家行動の普遍的なパターンを発見して説明しようとするとする知的営為であり、れっきとした「科学」なのです。アメリカの大学で学んだ半導体の物理学的知識が、日本では役立たないなど、ありえないでしょう。
同じことは国際関係論にも言えます。アメリカで発達した現在の国際関係論は、それ以外の国家でも通用するということです。このことは、我が国では、あまり理解されていないような印象があります。
国際関係論の5つのキー概念
4月から新しい学年が始まり、大学で国際政治学や国際関係論を履修する学生も少なくないでしょう。また、ロシア・ウクライナ戦争で、この学問に興味を持った方も多くいらっしゃるでしょう。そこで、この記事では、国際関係論の概要を理解するのに役立つエッセーを紹介します。
最も手短で分かりやすい国際関係論の解説は、スティーヴン・ウォルト氏(ハーバード大学)が外交専門誌『フォーリン・ポリシー』誌に寄せた「5分で国際関係論の学士号を取得する方法」でしょう。
このエッセーで、彼は国際関係論のキー概念を5つに集約しています。それらは①アナーキー(無政府状態)、②バランス・オブ・パワー(勢力均衡)、③比較優位、④誤算と誤認、⑤社会構成です。これを読めば、あなたも、たったの5分で国際関係論のエッセンスが理解できるということです。
アナーキーは、国家を統べる上位の中央権威が存在しないことです。こうした国際構造は国家に生き残りとパワーをめぐる競争を強いるということです。
バランス・オブ・パワーは、さまざまな意味がありますが、国家はどの国が台頭しており、どの国が衰退しているのかを常に気にしながら行動するということです。
比較優位(比較生産費説)は、国家が国際分業に基づく貿易をすれば富を増やせることの理解を促します。
誤認や誤算は、国家の指導者が時として愚かな決断をする要因になっています。
社会構成は、アイディアやアイデンティティ、規範といった非物質的要因が国際関係に影響していることに、我々を気づかせてくれます。海賊や奴隷制度の衰退は、こうした人間の行為が野蛮で非人道的であるという考えが、世界に広まった結果であるということです。
これら5つの概念はどれも大切なのですが、国際関係を説明したり理解したりするために、最も重要であるにもかかわらず、最も軽視されているのは、バランス・オブ・パワーでしょう。
ウォルト氏は、別のエッセーで、こんな冗談めいたことまで言うくらいです。「もし、あなたが大学で国際関係論の入門コースを受講し、担当教員が『バランス・オブ・パワー』について言及しなかったとしたら、授業料の返金を求めて母校に連絡してください」と。
バランス・オブ・パワーのロジックは、以下に紹介するように非常に簡潔です。にもかかわらず、この理論は国家のバランシング行動のパターンを明らかにできるのです。
バランス・オブ・パワーの基本的な論理は単純である。国家を互いに保護する『世界政府』が存在しないため、征服されたり、強制されたり、その他の形で危険にさらされるのを避けるために、それぞれが自国の資源と戦略に頼らざるを得ない。強大な脅威になる国家に直面したとき、不安な国は自国の資源をより多く動員したり、同じ危険に直面する他の国家との同盟を求めたりして、より有利にバランスを変化させられるということだ。
国際関係理論の真骨頂は、より少ない要因でより多くの出来事を説明することです。この点では、バランス・オブ・パワー理論は優れています。
日本政府は防衛費を二倍にすることを約束しました。バランス・オブ・パワーは、この日本の決定について、強大化する中国の脅威が日本に自国の資源を防衛により多く投入することを強いたとシンプルに説明できるのです。なお、このエッセーは、地政学者の奥山真司氏が、ご自身のブログで日本語に訳して紹介しています。興味のある方は、ぜひ、こちらでお読みください。
国際関係理論により明らかになる危険な世界
国際関係研究や教育、政策提言で大活躍しているマシュー・クローニグ氏(ジョージタウン大学)が、『フォーリン・ポリシー』誌に寄稿した入門エッセー「大国間戦争の到来を示唆する国際関係理論」は、読む価値が十分にあるでしょう。
彼は日本での知名度は低いかもしれませんが、核兵器をめぐる国際政治や大国間政治における民主主義国の優位性ついて、斬新で意欲的な研究成果を次々に発表している、注目すべきアメリカの政治学者です。
幸いなことに、この記事は『ニューズウィーク日本版』が、「国際関係論の基礎知識で読む『ウクライナ後』の世界秩序」というタイトルになおして、その日本語訳を掲載しました(ここでは著者の名前がクレイニグと記載されていますが、同一人物です)。
彼によれば、現在の世界はますます危険になっています。なぜ、そのように判断できるかといえば、以下のように、戦争を抑制する要因が弱まっていると理論的に言えるからです。
国際関係論のリアリズム(現実主義)によれば、冷戦下の二極世界と冷戦後のアメリカが支配する一極世界は比較的単純なシステムで、誤算による戦争は起きにくい。核兵器は紛争のコストを引き上げて、大国間の戦争を考えられないものにした。一方、リベラリズムは、制度、相互依存、民主主義の3つの変数が協力を促進し、紛争の緊張を緩和すると考える。第二次世界大戦後に設立され、冷戦後も拡大し、信頼されている国際機関や協定(国連、WTO、核拡散防止条約など)は主要国が平和的に対立を解決する場を提供してきた。さらに経済のグローバル化によって、武力紛争はあまりにもコストが高くなった。商売が順調で誰もが豊かなのに、なぜ争うのか。この理論でいけば、民主主義国はあまり争わずに協力することが多い。過去70年間に世界で起きた民主化の大きな波が、地球をより平和な場所にした。そして社会構成主義(コンストラクティヴィズム)は、新しい考えや規範、アイデンティティが国際政治をよりポジティブな方向に変えてきたとする。かつては海賊行為や奴隷、拷問、侵略戦争が日常的に行われていた。だが大量破壊兵器の使用に関する人権規範が強まり、タブー視されるようになり、国際紛争に歯止めを設けた。とはいえ残念ながら、平和をもたらすこれらの力のほぼ全てが、私たちの目の前でほころびつつあるようだ。国際関係論において、国際政治の主要な原動力は米中ロの新たな冷戦が平和的に行われる可能性が低いことを示唆している。
国際関係論は、ざっくり言うと、パワーと安全保障をめぐる国家間の競争に注目するリアリズム、ルールや規範といった制度の役割や民主主義、経済のグローバル化といった要因から国家間の協力の可能性を模索するリベラリズム、アクターのアイディアやアイデンティティが社会を構成するとみるコンストラクティヴィズムという主要な理論から構成されています。
クローニグ氏によれば、リアリズムでは多極世界が不安定であると説明されていること、リベラリズムで国際協調の指摘される国際制度が大国間の競争の場所になっていること、コンストラクティヴィズムで強調される平和の国際規範が脆いものであることをから推論すれば、今後、米中あるいは米ロが軍事的に衝突しても不思議ではないということです。
国際関係論の多様な理論
国際関係論をもっと詳しく勉強したい、国際関係理論を深く理解して、現実世界を分析するツールとして使いたい方には、ウォルト氏による広く読み継がれている古典的エッセー「国際関係論―1つの世界、多くの理論―」がおススメです。これは4半世紀前に書かれたものですが、今でも通用します。
ここで彼は、リアリズムについては、古典的リアリズム、防御的リアリズム、攻撃的リアリズムといった学派を分かりやすく解説するとともに、今ではすっかり衰退してしまったマルクス主義に依拠した従属論をラディカル派のアプローチとして紹介しています。
リベラリズムについても、民主主義や国際制度、相互依存という3本の柱を中心にコンパクトな解説を施しています。さらに、政策決定者や政府に焦点を当てた国家の政策決定理論にも言及しています。コンストラクティヴィズムは、リアリズムやリベラリズムに比べてとっつきにくいと感じる人が少なくないようですが、彼の以下の解説が多くの人の理解を促進すると思います。
冷戦の終わりはコンストラクティヴィストの理論を正統化するという意味で重要な役割を果たすことになった。なぜならリアリズムとリベラリズムは双方とも冷戦の終結を予測できなかったし、その理論からこの現象を説明することも困難だったからだ。ところがコンストラクティヴィストたちはこれを説明できたのである。具体的には、元ソ連代表のミハイル・ゴルバチョフが新たに『共通の安全保障(common security)』というアイディアを出したおかげでソ連の対外政策に革命を起こしたというものだ。
ありがたいことに、このエッセーも奥山氏が日本語に訳して、ご自身のウェブサイトで公開しています。国際関係論の世界に足を踏み入れたけれども躓いてしまったら、基本に戻って、ウォルト氏の解説を読み直すとよいでしょう。
国際関係論と政策提言
社会科学としての国際関係論に与えられた最大の役割は、世界がどのように動いているのかを説明することです。国際関係理論は国家行動に観察されるパターンや法則を明らかにすることを主な目的としており、残念ながら、国際事象を正確に予測するツールとしては弱いと言わざるを得ません。
主要な国際関係理論が大国間戦争のリスクの上昇を警告しているからと言って、必ず、大戦争が起こるわけではありません。国際関係論が語る将来の世界は、より危険であるだろうということです。
同時に、国際関係論は政策立案に役立てることもできます。我々は「日本はこうすべきだ」といった政策提言をよく語りますが、こう発言する時には、必ず、自分が信じる「理論」に頼っています。「Xを実行すれば、Yという成果を得られるだろう」という推論です。これこそが理論なのです。
理論を使っているにもかかわらず、自分がどのような理論を頼りにしているのか、それがどれほど高い説得力があるのか、他の理論の方が妥当ではないのか、といった問いを自覚している人は、はたしてどれくらいいるでしょうか。
実は、専門家の政治予測は必ずしもあてにならないことが、大規模な長期的調査から明らかになっています。フィリップ・テトロック氏(ペンシルバニア大学)の研究によれば、衝撃的なことに、専門家の政治予測の的中率は、ダーツを投げるチンパンジーすなわち当てずっぽうの予測と成績はほとんどかわらず、メディアでの露出度が高い自信過剰な識者ほど、予測は当たらない傾向にあるということです。
彼は「うまくいくと自信ありげに言いきったことがうまくいかなかったことを示す数々のエビデンスを前にしながら、まちがいを認める政治オブザーバーがめったにいないことにうんざりしていた」と語ったうえで、複雑な世界における政治予測の精度を高めるカギは、データに基づき、自分とは違う考えを持つ相手の長所を認める「キツネ」型の思考にあると結論づけています。
間違った理論による政策を実行する国家は、大きな代償を払うことになります。だからこそ、政策を導く理論が何であるかを明らかにして、それが国家の利益や安全保障に最適な選択につながるものであるのかを厳しく検証することが必要です。
国際関係論は、一般市民が世界の動きを理解するのみならず、国家の指導者が政策立案や決定をする際にも役立つ、力強い知的ツールなのです。国家の政策決定は、あまりにも重要なので、「国際政治学者」だけに任せるわけにはいきません。
「キツネ型」の独立した市民は、国際政治学者や地域研究者、外交官OBといった「専門家」の発言を鵜呑みにすることなく、自分とは違う意見に耳を傾けながら、間違った分析をただす「集団知」の形成に臆することなく参加すべきでしょう。