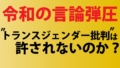イランのマフムード・アフマディネジャド元大統領は2010年9月の国連総会で、「イスラエルを地上の地図から抹殺してしまえ」と暴言を発し、国際社会の反感を買ったことがあった。
一方、パレスチナ自治区を実効支配しているイスラム過激テロ組織ハマスは10月7日、イスラエル領内に侵入して1200人余りのユダヤ人を虐殺し、200人以上を人質として拉致した。ハマスは「ユダヤ民族の撲滅」をその創設文に明記するテロ組織だ。

国民向けに声明を発表するイスラエルのネタニヤフ首相(2023年12月5日、イスラエル首相府公式サイトから)
両者に違いがあることに気が付く。イラン元大統領はシーア派のイスラム教徒であり、ハマスはスンニ派グループに属する。それだけではない。元大統領は「イスラエルを地上の地図から抹殺」と呼び掛け、後者は「ユダヤ民族の撲滅」を標榜していることだ。すなわち、憎悪の対象が前者は「イスラエル」であり、後者は「ユダヤ民族」の違いだ。一見、ささやかな違いのようだが、相違はある。
イスラエルの呼称は旧約時代のヤコブまで遡る。旧約聖書の創世記によると、神はヤコブに「イスラエル」という呼称を与えている。
神はサラにも1人の息子イサクを与える。そのイサクからヤコブが生まれた。ヤコブは母親の助けを受け、父イサクから神の祝福を受けた。そのため、イサクの長男エサウは弟ヤコブを憎み、殺そうとしたので、ヤコブは母親の兄ラバンの所に逃げる。そこで21年間、苦労しながら、家族と財産を得て、エサウがいる地に戻る。その途中、夢の中で天使と格闘し、勝利する。その時、神はヤコブに現れ、「イスラエル」という名称を与えたのだ。
「あなたは、もはやヤコブと言わず、イスラエルと言いなさい。あなたが神と人とに、力を争って勝ったからです」(創世記32章28節)と記述されている。「イスラ」は「戦う、支配する」を、「エル」は「神」を意味する。
一方、「ユダヤ民族」はイスラエルの12部族の一つ、「ユダ部族」を指していた。ヤコブの12人の息子から始まったイスラエル民族はエジプトで約400年後、モーセに率いられ出エジプトし、その後カナンに入り、士師たちの時代を経て、サウル、ダビデ、ソロモンの3王時代に入ったが、神の教えに従わなかったイスラエル人は南北朝に分裂し、捕虜生活を余儀なくされる。
北イスラエルはBC721年、アッシリア帝国の捕虜となり、南ユダ王国はバビロニアの王ネブカデネザルの捕虜となったが、バビロニアがペルシャとの戦いに敗北した結果、ペルシャ王クロスはBC538年、ユダヤ民族を解放し、エルサレムに帰還することを助けた。
なぜ、ペルシャ王は当時捕虜だったユダヤ人を解放したかについて、旧約聖書のエズラ記に説明している。ユダヤ人という言葉は、バビロン捕囚以降、イスラエル12部族全体を指すようになった。
このように説明すると、「イスラエル」と「ユダヤ民族」はほぼ同じ意味と受け取れるが、1948年に建国したイスラエルの人口構成をみると、3つの異なった出自がある。2022年5月のイスラエル中央統計局によると、①ヤコブの血統引く生粋のユダヤ人(約74%)、②アラブ系でイスラエル国籍を有する国民(約21%)、③キリスト教徒など少数派(5%)で、全人口は約950万人だ。だから、たとえ、ユダヤ人が全体の4分の3を占めているといっても、イスラエル=ユダヤ民族というわけにはいかないわけだ。
イスラエルでユダヤ人と呼ばれるには母方の血統が問われる。母親がユダヤ人だったら、父親には関係なくユダヤ人と呼ばれる。ユダヤ民族は母親の血統重視なのだ。アブラハムを“信仰の祖”とするキリスト教やイスラム教は教えを広げようとするが、ユダヤ教には宣教という考えはない。なぜならば、ユダヤ人となるためには母親の血統が不可欠だからだ。
興味深い点は、イスラエルでは18歳から男性(3年間)だけではなく、女性(2年間)も兵役義務があるが、それは主にユダヤ人国民だけを対象としたもので、キリスト教徒やアラブ系のイスラム系国民は兵役が免除されていることだ。国家の安全を守る兵役義務は他民族出身の国民には任されないという考えがその根底にあるのだろう。リベラルな国民が増えてきた現在のイスラエル社会ではキリスト教徒やアラブ系のイスラム系国民にも兵役義務を課すべきだという声が出ているという。
参考までに、アフマディネジャド元大統領の「イスラエルを地上から抹殺」発言はユダヤ、アラブ系を含む全てのイスラエル国民の殺害を意図し、ハマスの「ユダヤ民族撲滅」宣言はイスラエル内の4分の3を占めるユダヤ人だけの抹殺を意味している、と解釈できるわけだ。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2023年12月7日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。