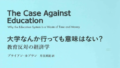今の大学をそのまま無償化するのは、税金をドブに捨てるようなものだ。その本来の目的は教育ではなく、研究者の養成だったからだ。19世紀初めにドイツで生まれた大学は、中世のuniversityとは似て非なるものだった。
初期のuniversityは職業学校であり、アメリカでは神学校だったが、キリスト教会の衰退で行き詰まった。他方ナポレオン戦争に敗れたドイツでは、国力を高めるために研究の水準を上げることが急務だった。
フィヒテやフンボルトの創立した大学の目的は教育ではなく、世界最先端の研究者を養成することだったが、その資金は税金だけでは足りなかった。そこで授業料と称して研究資金を集めるベルリン大学などのビジネスモデルができた。
研究費を「授業料」として集金するシステム
実験や演習を中心として研究室を単位とする学問は、職業の役には立たないが、授業料で資金は回る。自分で勉強する学生には授業は必要ないが、授業料を取るには必要だった。20世紀前半まで世界をリードする科学的成果がドイツで生まれたのは、このおかげだった。それは教授の研究費を授業料として集金する装置なので、学生にはメリットがない。
大学はアメリカに輸入されて、さらに進化をとげた。アメリカのuniversityはハイスクールのようなリベラルアーツが中心だったが、もっと安価に学べるカレッジがたくさんできると、教養主義だけでは学生が集めにくい。そこでドイツから輸入した研究中心の大学モデルを学部の上に継ぎ足して大学院をつくり、そこで職業教育をすることにした。
これはドイツでは大学と呼んでいた研究を大学院と呼ぶ「上げ底」だった。ジョンズ・ホプキンズ大学が1900年ごろ始め、ロースクールとメディカルスクールが4年の学部の上にでき、6年修了して初めて一人前の職業人となるようにした。大学院の2年は学生にとっては無駄だが、大学にとっては差別化できる宣伝文句になった。
学部の教師はハイスクールと大して変わらない「教育者」だったが、大学院には全米から一流の「研究者」を集めることができた。それは研究者養成機関だったので、大学院を修了して博士号をもつ者だけが教授になれるギルドを形成したのだ。博士課程に5年もかける必要はないが、それは丁稚奉公と同じく徒弟修行に投資させて研究の質を守る意味があった。
大学は研究者の生活を守るギルド
大学は、今日も残る最大のギルドの一つである。歴史的には聖職者が最古で、医師と弁護士がそれに次ぐが、大学教授は聖職者のようなものだ。ギルドは情報の非対称性が大きいときには職業的な能力のシグナルとして役に立つが、その欠点は供給制限によってのみ機能する点にある。
医師や弁護士は資格試験で十分であって免許制にする必要はないが、それをやめた国はない。免許によるレントが確実な収入をもたらし、勉強のインセンティブになるからだ。大学も大卒でないと大企業のホワイトカラーになれないという供給制限が教育投資のインセンティブになる。
これは合理的だが、社会的にみると非生産的なレントである。大学教授のギルドは医師や弁護士ほど職業団体として堅固ではないので、いま危機に瀕している。ギルドが供給の質を高めるのは、そのシグナリング効果が信じられているときで、そのときに限られるバブルなので、誰も大学教授の価値を信じなくなると、それが消滅するのは意外に早いかもしれない。