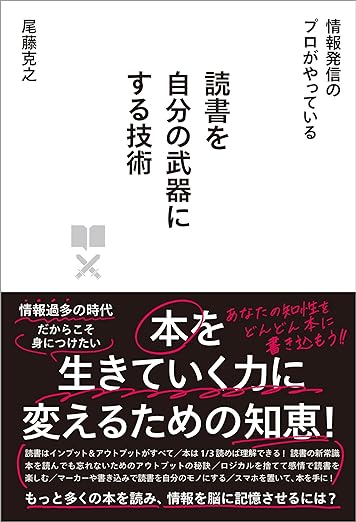Pitiphothivichit/iStock
生きている限り、いつか、必ずやってくる“死”。頭ではわかっていても、そう簡単には受け入れられるものではありません。
今回は、訪問看護ステーションを立ち上げ、自ら140名以上を看取った看護師が書きおろした一冊を紹介します。
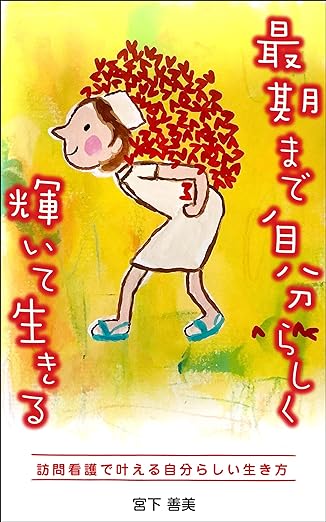
「最期まで自分らしく輝いて生きる: 訪問看護で叶える自分らしい生き方」(宮下善美 著)Kindle版
亡くなる場所を選択できる時代
あなたが末期ガンになり、余命数か月の人生と告知されてしまったら、どこで最期を迎えたいですか? 医療機器が整っている病院でしょうか。 それとも住み慣れた我が家でしょうか。
現在では病院はもちろん、施設や自宅など様々選択肢の中から最期の時間を過ごす場所を選ぶことができるようになりました。宮下さんは次のように言います。
「日本では少し前までは、病院死が大半で、今でも病院で亡くなることがスタンダードと考えている人は少なくありません。しかし、よく考えてみてください。 病院での入院生活は、常に点滴が繋がれ、行動範囲も制限されてしまいます。 好きなものも自由に食べられない。ICUに入ってしまえば、ご家族にも会えないまま亡くなってしまう、なんてこともありえます」(宮下さん)
「我が家は、特別です。 今までのご自分の人生そのものが詰まったものに囲まれて過ごす時間は、穏やかなときをもたらすことでしょう。そう、人間、自分が生まれてくる場所は決めることはできませんが、 亡くなる場所は自分で決めることができます」(同)
義父の自宅介護が契機に
宮下さんが、准看護師として働いていた2004年頃、義父が胃ガンの末期と宣告を受けました。緊急手術となり、一命をとりとめたものの、介護が必要な状態になり、在宅療養に切り替えます。
「義父に、好きなだけ、お酒やたばこを楽しんでもらい、息子や孫たちと時間を過ごしてもらいたいと思いました。最後は『よっ!』と手をあげて、笑顔で旅立ちました。義父は満足のいく最期を迎えられたのでしょうか? そんな義父との生活をきっかけに、私は訪問看護への道を進もうと決意したのです」(宮下さん)
「そのとき、すでに40歳。看護学校に入学し、3年間、働きながら学校に通い、正看護師になることができました。 公立病院で勤務した後に、ついに訪問看護ステーションを立ち上げることになったのです」(同)
しかし、その現実は過酷なものでした。オムツ交換だって、食事介助だって、なんだってやれると思っていました。
しかし、“やれる”と“できる”は違います。 技術的にやることができても、毎日のこととなるとそうはいかず、肉体的にも精神的にも追い込まれていきます。
年々拡大する介護離職
総務省が公表した2022年の「就業構造基本調査」によれば、親などの介護をしている人は629万人、そのうち仕事をしている人は365万人。さらに、介護離職が全国で年10.6万人を超えたことが明らかになりました。
介護離職は増加の一途をたどり、私たちの暮らしに立ち塞がろうとしています。会社のなかでは、「家族の面倒は家族が見るのが当たり前」という風潮が残っています。このような、偏向した考えや空気が原因で介護離職になってしまうケースが多いのでしょう。
介護離職をすると実際にはどうなるのでしょうか。間違いなく、経済面、精神面、肉体面での負荷が増えていきます。収入が減り、外部との接点が無くなることで精神面の負担も増えます。介護による肉体面の負担が増えていきます。
介護は、その過酷さに心が折れそうになることもあります。だからこそ、介護から逃げる、介護を手放す方法を知らなければいけないのです。
あなたが、自分の命が残りわずかだと宣言されたら、どこで、どんな風に人生を終えたいですか?本書を読み、様々な選択肢があることを理解してください。
尾藤 克之(コラムニスト・著述家)
■
2年振りに22冊目の本を出版しました。
「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)