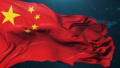バルカン半島の盟主セルビアのアレクサンダル・ヴチッチ大統領は親ロシア派指導者と見られているが、ロシアの著名な反体制派活動家アレクセイ・ナワリヌイ氏(47)の急死の報にショックを隠せられない。

EU外務・安全保障政策担当上級代表のジョゼップ・ボレル氏と会見するヴチッチ大統領(独ミュンヘンで開催されたMSCで、セルビア大統領府公式サイトから)
ミュンヘンで開催された第60回安全保障会議(MSC)で16日、ロシアのプーチン大統領によって夫を殺害されたナワリヌイ氏のユリア夫人が演壇に立ってプーチン大統領の蛮行を厳しく批判した直後、会場にいた国家元首、政府首脳らは一斉に立ち上がって拍手を送った。その時、ヴチッチ大統領が同じように立ち上がったが、拍手しなかった。セルビア国営放送がそのシーンを放映した。「なぜヴチッチ大統領はユリア夫人のアピールに拍手を送らなかったか」といったメディアからの批判を受けた。
ジャーナリストの質問に、ヴチッチ大統領は、「私は演壇で語っていた夫人がナワリヌイ氏の夫人とは知らなかった」と苦しい返答をしている。2メートル余りの長身のヴチッチ大統領が演壇のユリア夫人が見えなかったということはないだろう。
ロシアの著名な反体制派活動家の獄死ニュースは親ロシア派政治家として知られているヴチッチ大統領にとってもやはりショックだったはずだ。ナワリヌイ氏の死の一報を聞いた直後、「愕然とした」と答えていることから見てもその動揺ぶりが分かる。
セルビアは伝統的に親ロシア派。ロシア軍がウクライナに侵攻して以来、世界の正教会ではロシア正教会離れが急速に進んでいる中、セルビア正教会は依然、モスクワ総主教キリル1世のロシア正教会と密接な関係を維持している数少ない正教会だ。ヴチッチ大統領は外交・政治的にはロシアとの関係を深めている。ヴチッチ大統領はモスクワを訪問し、プーチン大統領と会合しウクライナ戦争では欧米諸国の対ロシア制裁に対して距離を置いてきた。
その一方、ヴチッチ大統領は欧州連合(EU)加盟を模索し、ブリュッセルのバルカン半島の欧州統合政策に積極的に応じている。要するに、セルビアの国家オリエンテーションはロシアとEUの両方向に向いているわけだ。東か、西か、といったハムレット的な二者択一の悩みではなく、東も西もセルビアの国益に合致する限り、関係を深めていくという一種のプラグマティズム(実用主義)だ(「セルビア大統領『全方位外交』の行方」2022年5月3日参考)。
そこにモスクワからナワリヌイ氏の獄死が伝わってきた。ヴチッチ大統領は18日、セルビアのテレビ局ブルヴァで「クレムリンとの関係が今後難しくなる」と正直に懸念を表明したという。47歳の若い反体制派活動家の獄死は53歳とまだ若い世代に入るヴチッチ大統領にとってもまったく他人事とは言えない。もちろん、ヴチッチ大統領の言動はセルビア大統領としてというより、一人の人間としての反応だろう。セルビアの親ロシア政策がナワリヌイ氏の死を契機に大きく変わるということは考えられないが、何の影響もないとは断言できない。
ヴチッチ大統領のセルビアはロシアから安価な石油やガスを得る一方、中国との経済関係を深め、EUからは先進工業製品や消費財を得るという基本方針には変わらない。セルビアの近未来の路線は、ロシアとウクライナ間の戦争の行方と、米国の次期大統領選の動向に依存しているともいえる。その意味で、ヴチッチ大統領の二股外交はここしばらくは続くだろうが、年末までにはひょっとしたら選択を強いられるかもしれない。
ヴチッチ大統領と共に親ロシア派のハンガリーのオルバン首相は先月24日、北大西洋条約機構(NATO)のストルテンベルグ事務総長との電話会談でスウェーデンの早急な加盟批准を国民議会に要請した旨を伝えている。
オルバン首相の場合、プーチン大統領の唯一のEUパートナーであり、ウクライナ戦争ではEUの対ロシア制裁を拒否、EUのウクライナ支援にも拒否権を行使してきた生粋の親ロシア派政治家だ。そのEUの異端児として知られているオルバン首相がスウェーデンのNATO加盟ボイコットを中止するというのだ。
冷戦時代、ソ連共産党政権は東欧諸国を衛星国家として支配し、西側に傾斜する政治的動きが見られるとワルシャワ条約機構軍を侵攻させ、東欧諸国の国民を圧政してきた歴史がある。その後継国ロシアのプーチン大統領は現在、ウクライナにNATO加盟、EU加盟の動きが出てくると軍をウクライナに侵攻させている。
オルバン首相はロシアから安価な天然ガスなどの供与を受ける一方、ロシアの援助を受け原発の新設を進めるなど、モスクワとは深い経済的つながりがあるが、ナワリヌイ氏の獄死はオルバン首相にとっても一過性の出来事ではないはずだ。多分、これは当方の一方的な希望的観測に過ぎないだろうが、そうあってほしいものだ。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2024年2月20日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。