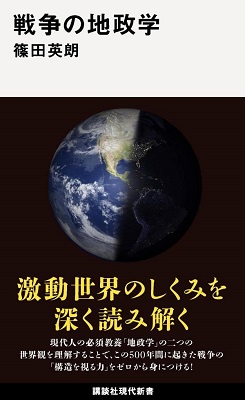ICC(国際刑事裁判所)のカーン検察官が、ハマス指導者3名とあわせて、イスラエル政府のネタニヤフ首相とガラント国防相に対する逮捕状を請求する、という発表をした。
待ち焦がれていた発表である。
すでにイスラエル政府はこの動きを察知しており、4月末にはネタニヤフ首相が反発する声明を出していた。それだけでなく、アメリカの国会議員に働きかけ、訴追の場合にはICC職員に対する制裁を科する威嚇をする、といった声明を出させたりもしていた。
以前には、アフガニスタンにおける戦争犯罪の捜査開始だけで、当時のトランプ米国大統領が、ICC検察官の米国入国ビザ発給停止などの制裁を科したことがあった。当時のベンスーダ検察官が国連本部への出張を取りやめざるを得なくなったことがある。もし今回アメリカが、組織としてのICCや、職員に対する金融制裁を発動すると、ICCの捜査等の活動にも支障が出ないとも限らない。
しかしイスラエルの戦争犯罪行為は明白である。制裁を恐れて捜査を回避するようなことがあったら、ICCの存在意義が問われる。
ICCは、多数のアフリカ諸国の締約国を持つ。これらの諸国は、2017年頃には、ICCがアフリカ人ばかりを訴追しているのは二重基準だ、という理由で、南アフリカを先頭にして、大量脱退の脅しをかけたことがある。
アメリカもイスラエルも締約国ではない(パレスチナが締約国の扱いになっているためICCは管轄権を行使して捜査ができる)。締約国ではない戦争犯罪(支援)国の威嚇に屈して、ガザにおける戦争犯罪の訴追を見送ったら、ICCのほうが締約国に見限られて、崩壊してしまうだろう。
ネタニヤフ首相に対する訴追は、大きな政治的負担がかかる。しかしICCにとっては、それを避けることのほうにより大きな地獄が待っている。進むしかない。
今回の発表は、検察官による逮捕状発行の請求である。裁判官三名で構成される予審部Iが、その請求の妥当性を審理したうえで、正式な逮捕状の発行となる。通常は、この手続きで判断が覆ることはない。ただ政治的圧力は大きい。国際世論を喚起することによって、正常な手続きが阻害されないようにするのが、今回のカーン検察官の発表の意図でもあるだろう。
かつて、アフガニスタンにおける戦争犯罪の捜査を開始したいという検察官の要請が、予審部によって却下されたことがある。ICCの能力の限界を理由にした判断をした当時の第二予審部の判事の中に、現在ICCの所長に就任している赤根智子氏がいた。日本の検察官から、ICC判事に転身したばかりの2019年のことであった。
この判断は、ICCを支援してきた国際人権団体等から一斉に猛批判を浴びた。赤根判事らは、現実的な判断をしたつもりだっただろうが、国際世論がICCに求めているのは、そのような醒めた態度ではなかった。結局、検察官の再請求を受けて、翌2020年に別の判事が構成する予審部が、アフガニスタン捜査の開始を許可した。

この時のICCの混乱は、まだ記憶に新しい。今回のガザ危機で、予審部判事が醒めた対応をする余裕は、ほとんどないだろう。法律的には、ネタニヤフ首相らの訴追は、確固たる根拠を持っている。その判断を覆すとしたら、政治的な配慮以外には理由がない。これほどまでに世界的に注目されている案件で、そのような大胆な政治的配慮をすることができる判事がいるとは思えない。
カーン検察官による逮捕状請求の発表がなされた5月20日、日本の国会では、事態を察知しないやり取りが行われていた。参議院決算委員会では、金子道仁議員(維新の会)が、「UNRWAがテロに関与した蓋然性が否定できない」ことを理由に、UNRWAへの資金提供再開は時期尚早だったという見解を述べたうえで、資金を他の組織に回すべきではないか、と政府に問う質問を行っていた。
しかしUNRWAを糾弾したイスラエル政府は、その糾弾を裏付ける証拠を何も提示していない。国連の側は、調査を行ったうえで、糾弾を裏付ける証拠が何もない、という報告書を提出している。糾弾しているイスラエル政府は、人道援助を止めてガザの人々を飢餓状態に陥らせていることも理由に、戦争犯罪行為を問われているのである。
その戦争犯罪人のイスラエル政府の言葉を鵜呑みにして、証拠も何もないまま、「UNRWAがテロに関与した蓋然性が否定できない」と主張するのは、日本の国会でイスラエル政府の戦争犯罪行為に加担する行為に等しくなる。
人道援助を止めないように他の組織に資金を回したところで、気に入らなくなればイスラエル政府はその組織もまた「ハマスだ」と糾弾するだろう。その都度、戦争犯罪人が動かしているイスラエル政府の証拠のない政治的糾弾で、日本政府の政策をコロコロと変えるのは、正しくない。
同日の同じ参議院決算委員会で、和田正宗議員(自民党)は、ハマスと通じているという理由で、トルコ政府を糾弾する趣旨の質問を繰り返した。しかしトルコ政府は、ハマスは占領に抵抗する組織であって、テロ組織ではない、という見解を表明しているにすぎない。具体的な支援を表明しているわけではない。
これに対して、アメリカは、戦争犯罪人が動かすイスラエルに巨額の武器支援を行って、ガザにおける戦争犯罪行為を助長している。トルコは批判するが、イスラエルやアメリカは批判しない、というのは、全く一貫性がないだけでなく、進行中のイスラエルの戦争犯罪行為を支持する含意さえあると言わざるを得ない。
日本では、右派系議員が、今回のガザ危機をめぐり、一貫して親イスラエルの立場を取っている。これに加えて、ここ数年で急速に防衛装備やテロ対策の領域で、イスラエルとの関係を深めてきた国防系の議員も、同じように一貫して親イスラエル的な立場を取り続けている。今回のICCによるネタニヤフ首相逮捕状請求の意味をよく考え、日本の長期的な国益を第一に考えて、慎重に発言して行動してほしい。

日本の岸田首相と上川外相は、国際社会の法の支配を語る。しかし、最近ではもっぱらウクライナ情勢をめぐってロシアを非難するときだけに用いている。普遍的な概念であるかのような言い方になっているが、実際には、地域特化的なやり方でしか、この概念を用いない。ガザ危機をめぐっては、同じようなことを言わない。
そこで日本政府関係者は、アメリカ人特有の言い回しを真似することを覚えて、「ルールに基づいた国際秩序(rules-based international order)」といった言い方も好み始めている。しかし、これはG7以外の諸国には通用しない。
非欧米圏の諸国においては、「ルールに基づいた国際秩序」とは、アメリカが自分に都合の良いように恣意的に二重基準を振り回すときに使う言い回し、という理解が定着している。どうも岸田首相も上川外相も、それに気づくことなく、「ルールに基づく国際秩序」を「グローバルサウス」に説く、といった説明を好んでしまっているが、早く現実に気付いたほうがいい。ICCでも「ルールに基づいた国際秩序」などというアメリカ産の概念は、使わない。

NicoElNino/iStock
日本は、イスラエルから武器購入はしようとしているが、アメリカのように武器支援まではしていないので、まだ罪は軽いかもしれない。しかし二重基準のまま、これからもずっとやっていこうとするのは、無理だ。
今回のICC検察官によるネタニヤフ首相らに対する逮捕状請求を真摯に受け止めて、あらためてICC支援を通じて、国際社会の法の支配に対する揺るぎない信念を示してほしい。
■