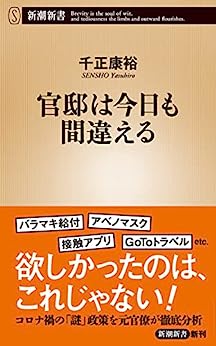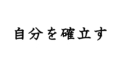1. 成長戦略「新しい資本主義のグランドデザイン2024」とは
6月21日(金)、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」が閣議決定されました。これはいわゆる「成長戦略」と呼ばれるもので、政権ごとに名前は変わりますが、骨太の方針や規制改革実施計画と共に、この時期に閣議決定される3つのうちの一つです。
成長戦略は、日本の産業発展や経済成長に関する国の大方針を示す文書です。閣議決定後にはメディアでも内容が大きく報道されるので、目にした、耳にした方も多いのではないでしょうか。
一方、よく質問を受けるのは「骨太の方針」と「成長戦略」何が違うのか?ということです。骨太の方針の正式名称は「経済財政運営と改革の基本方針」ですよね。ここにも「経済財政」という言葉が入っており、実際に経済政策についても書き込まれています。実際比較してみてみると、骨太の方針と成長戦略で重複する項目が多くあることが分かります。
どっちも同じ項目の経済政策について記述しているのだとすると、何が違うの?というところですが、その点について理解すると、成長戦略をどのように読み解くか、何に注目すればいいかが分かってきます。
本時期ではまず、骨太の方針と成長戦略の位置づけや役割分担について整理したうえで、発表されたばかりの「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024」の見どころについて解説していきます。

新しい資本主義実現会議に出席する岸田首相 首相官邸HPより
2. 骨太の方針と成長戦略、何が違うの?成長戦略の「成り立ち」を見てみる
骨太の方針と成長戦略、2つが明確に違うのは、「法律上に規定されているかどうか」ということです。
別の回でも触れたとおり、骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)は、内閣府に設置される経済財政諮問会議の議論をとりまとめたものですが、経済財政諮問会議には法律上の根拠があります。
内閣府設置法第19条は、経済財政諮問会議について記しており、そこで「経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策」や「国土形成計画法に規定する全国計画その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するため調査審議する」などの事務をつかさどる、とその役割を示しています。
一方で、成長戦略および、それを議論する場(岸田政権で言えば、新しい資本主義実現本部および新しい資本主義実現会議)については、法律で具体的に規定されているわけではありません。
では成長戦略はどのように生まれ、どのような変遷を経て現在の形になっていったのでしょうか。その経緯についてまとめた国立国会図書館の文献(※)はまず、成長戦略について次のように定義しています。
「我が国の成長戦略は、主に構造改革の推進により、少子高齢化・人口減少の負の影響を克服し、経済の潜在的成長力を中長期的に上昇させる戦略として、小泉純一郎内閣以降の歴代内閣によって策定されてきた。成長戦略の公的な定義やリストは存在せず政府の様々な戦略、ビジョン等のうち、どれが成長戦略に該当するかを確定することは難しい。本稿では、成長戦略とは、政府が、中長期的な経済成長(GDP成長率等)の見通し又は目標を掲げ、その達成に必要な施策を省庁横断的にまとめた独立の文書、を指すものとする。」
国立国会図書館 成長戦略の経緯と論点 調査と情報―ISSUE BRIEF― NUMBER 868(2015. 5.19.)より ※太字筆者
つまりざっくりいえば、政府が、中長期的な経済成長の「目標」をかかげ、省庁横断的に、その達成に必要な施策をまとめたものということです。
文献をもとに、これまでの経緯をまとめると、以下のようになります。
- 小泉政権において、「改革なくして成長なし」の号令の下で進められた構造改革の流れの中で、2006年に「経済成長戦略大綱」が作られた。その施策内容は「骨太方針2006」に盛り込まれ、経済成長戦略は歳出・歳入一体改革と車の両輪であると位置付けられた。
- 第2次安倍政権において、日本経済再生本部の下に置かれた産業競争力会議を中心に検討が進められ、「日本再興戦略―JAPAN is BACK―」が閣議決定。日本産業再興プラン、戦略市場創造プラン、国際展開戦略を柱とし、各分野の政策群ごとに成果指標(Key Performance Indicator: KPI)を定めて進捗管理を行うとした。
- 菅義偉政権の発足に伴い日本経済再生本部という枠組みが改められ、「骨太の方針の下、我が国経済の持続的な発展に向け、成長戦略の具体化を推進する」として成長戦略会議が置かれ、「成長戦略実行計画」が閣議決定された。
この経緯を見ていくと、成長戦略は、構造改革や日本再生戦略などの大きな政治の流れの中で、まずは骨太の方針を補完するものとして策定され、その後、より成長を志向した経済政策について「中長期的な目標に対する、より具体的な計画(工程表や数値目標を伴うもの」として作られてきた、と解釈してもいいかもしれません。
成長戦略は、その成り立ち故に、骨太の方針の特に経済政策の項目としては重複するところが少なくありません。骨太の方針で全体の方向性を示し、成長戦略はよりそれをより具体的な内容を示すものと考えるとわかりやすいかもしれません。
骨太の方針も、成長戦略も、どちらも閣議決定される重要文書です。上記の位置づけの違いを頭に入れた時に、より個別の政策やビジネスを実現したいと考えるなら、どちらに記載されているほうがベターなのか?と考えていく方法もありそうです。
実際、企業や力のあるNPOの担当者は、自分たちが実現したい政策が成長戦略に掲載されるよう、積極的に働きかけを行っています。
ではここからはより具体的に、最近発表されたばかりの「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」について詳しく見ていきながら、成長戦略を策定するプレイヤーやそのスケジュール、さらには、そこに民間からの意見を反映させるためにどのような働きかけが可能なのかについて、見ていきます。
(この続きはこちらのnoteから)
(執筆:西川貴清、監修:千正康裕)
講演、コンサルティング、研修のご依頼などはこちら
■
編集部より:この記事は元厚生労働省、千正康裕氏(株式会社千正組代表取締役)のnote 2024年6月25日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。