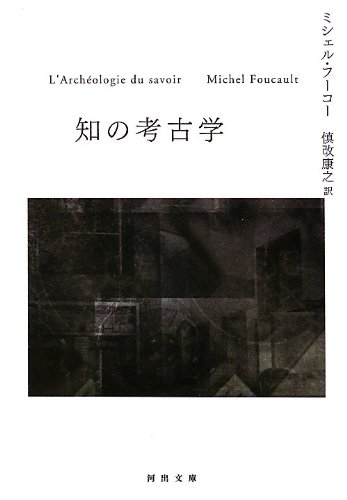NiseriN/iStock
フーコーとは?
ミッシェル・フーコーはかの有名な「フーコーの振り子」のフーコーではない。左翼思想に毒されている人や学者、政治家の多くは、フーコー的善と悪の解釈の考古学(アルケオロジー)において、歴史上の社会情勢等の変化で善と悪の価値観が転換し得ることを説いた学問として有名であり、その影響を多大に受けていると考えられる。
フーコー的考古学的善悪の解釈論は何が善で何が悪か?の尺度について論じているのではなく、その価値観は時代の変化とともに変わるものだと言う意味だ。それは法治国家の法治とは何か?に通じる。
民意の具現としての選挙と立法が民主主義の依って立つ場所、依拠する場所であるとするならば、民主主義は法律で「のみ」定義つけられ価値観が法治によって固定された概念として息をし続けることになる。これは、民主主義とは社会契約論と相争うのか?と言う古典的論争のテーマでもある。
したがって、左翼思想に毒された人たちが陥る、マイノリティへの過剰な思い入れを背景とする権利主張は、フーコー的善悪論に立てば、アルシーヴ(社会背景上の資料収集・要素収集)を等価で判断材料とする上において、感情論に左右されることを否定されなければいけないことになり、やはり左翼思想による自己承認欲求と解釈しても言い過ぎでは無いように思う。
と当時に、フーコーは社会を構成する人に対して、ディシプリン(規律)をささやかなことであっても重要な要素と定義付けたが、これが後の、忌まわしき社会主義国家のパノプティコン(一望監視施設)による監視社会を生み出すことになる。つまり、この監視する側と監視される側が相互に監視している社会の具現だ。
社会主義とはこのようなフーコーの機械論的な人間の有り様に起因する。フーコーは人間を機械的な存在と見做したわけではなく、社会を秩序だった社会として成り立たせるには、この機械論的要素(種々のアルシーヴ)が必要だと考えた。
王政が倒れ、資本主義が席巻すると当時に、果たして社会はこのまま人間を自由なるものとして放置していていいのか?への問いに対するフーコーの答えが、ディシプリン(規律)による、機械論的な解釈としての人間と社会だったと言えるだろう。
社会主義は未完成
社会主義はこうやって醸成されていくことになる。あたかもこれが差別の無い平等な人間社会実現の礎となると東欧の社会主義国家は礼賛したことだろう。
しかし、学問的解釈としての人間は、共産主義者や社会主義者が思い描くほど、彼らのイデオロギーに従順ではなかった。結果において、共産主義者と社会主義者は、人間を測り間違えたのだ。それが、ソヴィエトの崩壊であり、東欧諸国の社会主義国家の崩壊だ。二者共に、とてつもない格差と貧困と階級社会を生み出した。そしてそれは、いくつかの国において現在進行形でもある悲劇だ。
人は人を管理したがる。権力者は権力者とそれ以外を分断したがる。権力者以外の人々は、抑圧されていると考える。そしてその抑圧観念は、権力者が権力者として振る舞っているからだと考える。だから、社会主義における権力者は、権力者以外の溜飲を下げる目的で、互いを監視対象にしたがる。社会主義における権力者は自身の目ではなく、権力者に服従する者の目を自分たちの目として利用する。
時は進み、テクノロジーの進歩は、権力者の目を機械に置き換えている。今の中国やロシアが正にそれだ。正に機械論的な社会秩序としての監視が機能している。中国共産党が厄介なのは、その機械論的な民衆への解釈の上に法律があり、その上に絶対者として共産党員がいる。中国共産党は、それを公平で公正な秩序だと考えている。
この場合、監視される側の思いなどどうでも良い。機械論的に正しいことが、彼らにとって正しいことであり、最上位にある共産党綱領が絶対なのだから、綱領に基づく秩序は絶対的に正しいと言う、人間存在を放棄した社会統制のあり方を大真面目に機能させようとしているのだ。
自己責任論
一方で、共産主義者や社会主義者が選択した言葉に「主体」というものがある。サルトルもハイデッガーもデカルトだってこの「主体」についての見解を残している。
主体とは誰でもないあなた自身ということだ。あなた自身が考え行動したことは、それ以上でもそれ以下でもなく、また他の誰かが取って代わることも出来ない「存在」論だ。「我思う故に我あり」というやつだ。マルクスのように「すべてのものを疑え」と言われても仕方ないじゃないか?あれこれ悩みあれこれ考えあぐねた結果をもたらしたのは、他でもないあんた自身やろ?ということを存在証明としている。
サルトルが提示した存在論的主体を「私」であるあなたに求めるという暴力は、所謂、右翼的自己責任論とは観察者と考察者の立場的な違いを意味している。つまり、存在論としての自己責任論は客体である他者が「私」への責任を求めることだ。保守的思想、右翼的思想は自分自身である「私」の中に主体と客体を持ち込み、自分自身が自分自身である「私」に対して責任を負い、かつ、問うことになる。
三島由紀夫は自衛隊蜂起を語りかけたが、組織的な、従属関係としての上司と部下の関係性において、また国家護持の責任を負う自衛隊員が、法的曖昧さの中で自己責任を押し付けられていていいのか?という問いかけであり、三島の言葉はある種の幼稚さを以て捉えられたかもしれない。
しかし、三島自身は、「私」が存在している国家と自分自身を分断してはならないと考えていたのかもしれない。その「檄」の中には、国家とは何か?という三島の素朴な問いがある。その問いの源泉は、国家と自己との関係性における自己責任を問うている。お前ら自衛隊員が警察の一部などと曖昧模糊とした誤魔化しの中で存在していていいのか?と自衛隊員自身に問うたのだ。
自衛隊員にしてみれば、戦争が終わり、新しい国家感、国民感を記した日本国憲法において兎にも角にも今の自分たちの立場があり、それはそれで国家と国民を憂う責任論の具体として自衛隊員という立場があるのであり、政治家でもない三島が何を言おうが、お前の言ってることだって所詮は他人事だろ?という思いがあったかもしれない。
三島は大事を引き起こした責任と、国家を憂う憂国の志士の生き方として自決の道を選んだ。右翼的表現を借りれば、それこそが右翼的自己責任の完結の一つの在り方だと三島が考えていたとも言える。三島にとっての「一人一殺」は自己への責任の取り方だったかもしれない。
正にそれは、あまりに日本人的な責任の取り方だ。誰にも裁かれない。「私」は「私」の名において自己で全てを完遂するという責任の取り方だろう。
フーコーの言う社会と国家を構成する人間への期待を込めた「規律(ディシプリン)」的社会秩序というか決まりごとというか、まあ、これをちゃんとしておけば間違いねえんじゃね?という淡い希望は、ソヴィエト崩壊、東欧の社会主義国の崩壊、中東紛争、アフリカ内戦、サリン事件、911テロ、阪神淡路大震災、東日本大震災で脆くも崩れ去っている。人間は弱き者であると、証明されてしまった。
■
以後、
・法治国家とは?
続きはnoteにて(倉沢良弦の「ニュースの裏側」)。