1月30日のNature誌のNew欄に「How China created AI model DeepSeek and shocked the world」というタイトルの記事が掲載されている。中国政府の方針、潤沢な資金、AIを学ぶ学生の供給が生成AIを支えたと副題にあった。米国OpenAI社・ChatGPTの一人舞台と思われていた生成AIワールドに中国のベンチャー企業が割り込んで騒動となっている。
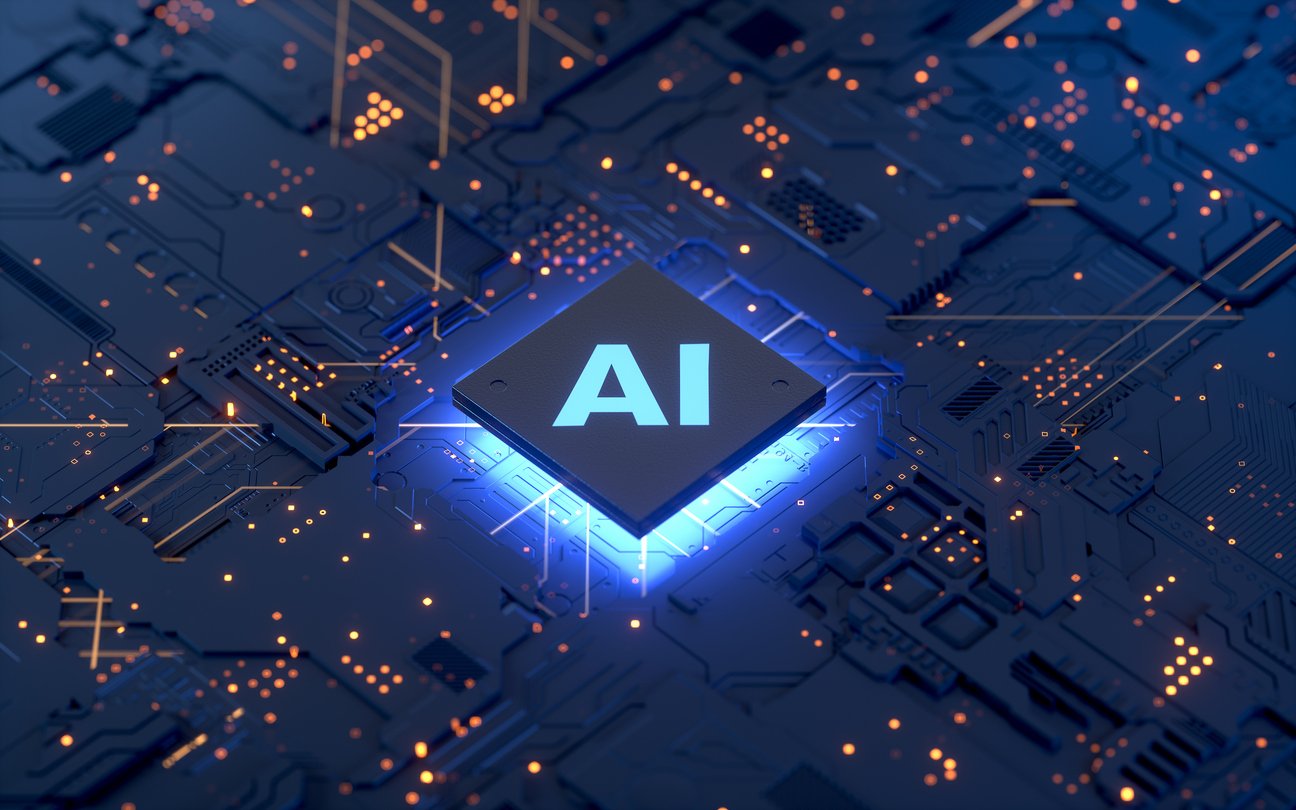
Andy/iStock
米中の人工知能開発競争が熾烈だが、OpenAI社の大規模言語モデルを用いたChatGPTが先行していた中で、2大国の競争が表面化した。中国政府が国を挙げて人工知能開発に取り組んでいることは周知の事実だ。さらに中国でのベンチャーファンドの投資額は、日本よりも2桁大きい。日本は政府も民間も及び腰でしか投資しないので、すべてがToo Late, Too Littleで結局つぎ込んだ資金が水泡と化している。これが20-30年続いていることが、日本の地盤沈下の一大要因だ。
さらに中国のIT大手企業アリババもDeepSeekの機能を上回るQwen2.5-Maxを開発したと1月29日に発表しているそうだ。それ以外にもChatGPTの性能を上回る生成AIを開発したと謳っている中国の企業がある。中国は2030年には世界の人工知能分野のリーダーになると公表している。総理大臣が「楽しい日本」と言っているような余裕はこの国にはないはずだが、本当にゆったりとした楽園ガラパゴス島になってきた。
シカゴにあるシンクタンク・マルコポール社によると、2022年度には中国は世界のAI研究者のおおよそ50%を供給しており、米国の18%を大きく上回っているそうだ。中国では440大学が人工知能に特化した学科をもっており、如何にこの分野に注力しているかが窺える。ゲノムも人工知能を含む情報科学も、審判がストライクとコールしてからバットを振るような日本では、得点できるはずもない。
さらに、米国は2022年から高性能チップの中国への輸出を制限していたが、この危機的状況下で生成AIが開発されたことに驚きを隠せない。「窮鼠猫を噛む」ではないが、追い詰められることによって、それを脱却するために中国が総力を挙げて取り組んだ成果と言える。ただし、米国側からは知的財産を盗んだとの疑いがかけられているのは当然か?
■
編集部より:この記事は、医学者、中村祐輔氏のブログ「中村祐輔のこれでいいのか日本の医療」2025年2月2日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。














