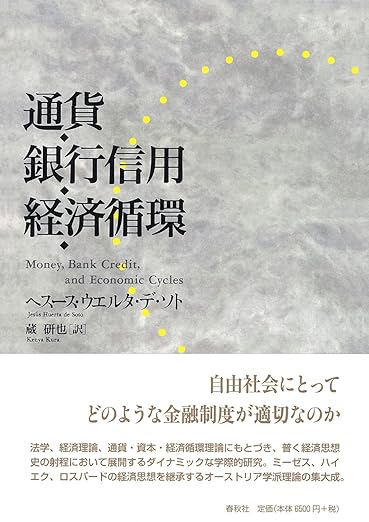DNY59/iStock
こんにちは!自由主義研究所の藤丸です。
最近、「長期金利の上昇」がニュースでも話題になっています。日銀の追加利上げについても、その動向が注目されています。

ところで、短期金利、長期金利、政策金利など、いろいろありますが、そもそも「金利」とは何でしょうか?
今回は、「金利が経済成長に与える影響~オーストリア学派の視点」という2024年6月29日に「ミーゼス研究所」のHPに掲載された記事を、一部意訳して紹介しながら、「金利」について考えてみたいと思います。
現代社会で通常に考えられている「金利」とは、一見違った捉え方なので戸惑う人もいるかもしれませんが、そもそも「金利とは?」と物事の根本を考えることは重要だと思います。
短い文章なので、読んでいただけると嬉しいです。
(※)は筆者の追記、太字も筆者です。
The Impact of Interest Rates on Economic Growth:An Austrian Perspective
金利が経済成長に与える影響~オーストリア学派の視点
長年にわたり、金利と経済成長の関係は、経済理論や政策議論の主要な焦点となってきた。
オーストリア学派の理論によれば、金利は、借り手と貯蓄者の「時間選好」のバランスをとる市場経済における重要な「シグナル」であり、中央銀行が経済の安定を維持するために管理するツールではない。
この金利というシグナルを、誤って解釈したり無視したりすることで、深刻な経済の歪みや不正投資が生じる可能性がある。
1. 金利の性質~「時間選好とは?」
オーストリア経済学の視点では、金利は、個人の「時間選好」の相互作用から自然に発生する。
「時間選好」とは、「将来のもの」よりも「現在のもの」を好む度合い、である。
「時間選好が低い」と、消費を先延ばしにして、将来のために貯蓄する。
「時間選好が高い」と、貯蓄よりも、現在の消費を優先する。
金利によって、自由市場における「貯蓄(つまり消費の先送り)という供給」と、「資本投資に対する需要」との均衡が維持される。
この均衡が維持されることで、資源は現在と未来の時間の全体にわたって効果的に配分され、財の生産量と人々の需要量が一致する。
人々が貯蓄を増やすと金利は低下し、長期プロジェクトへの投資が促進される。一方、人々がすぐに消費したければ(※貯蓄が少なくなるので)、金利は上昇し、企業はすぐに消費される商品の生産に集中するようになる。
※上記については、現在の社会の仕組みとは違うので、理解しにくいかもしれません。つまり、オーストリア学派は、本来の「金利」は、人々の時間選好によって自然発生的に決まるものと考えますが、現在社会は実際には、金利は「政府が決定するもの(政府が決定に多大な影響力を持つ)」となっています。そのため、金利が高いと貯蓄のインセンティブがあがる(貯金時の利子がたくさんもらえる)、と真逆になっています。ここはややこしいので、またどこかで改めて書きたいです。
2. 中央銀行の介入と経済の歪み
フリードリヒ・ハイエクやルートヴィヒ・フォン・ミーゼスなどのオーストリア学派によれば、こうした金利の自然な調整は、中央銀行が人為的に低い金利を設定することによって歪められる。中央銀行は、実際の市場の相互作用によって設定される水準よりも低い金利を維持することによって、本来は実行不可能な長期的・資本集約的なプロジェクトにおいて、過剰な借入と投資を刺激する。
オーストリア学派が「投資の失敗」と呼ぶのは、このような「消費者の真の欲求」と「投資」とのミスマッチの結果である。つまり、資金が投下されたその計画が、そもそも消費者の需要、そして「貯蓄」によって裏付けられていないのだ。こうした人為的な低金利は、急速な景気拡大と投機的投資を特徴とする景気循環の好況期を加速させる。そして、投資に見合う十分な貯蓄がないことが明らかになると、そうした投資計画は崩壊し、不況と景気後退を引き起こす。
3. 歴史的証拠
金利操作の影響は、経済サイクルの歴史の中で数多く見られる。
例えば、1920年代には大規模な金融緩和と人為的な低金利政策が行われ、その後に大恐慌が起こった。2008年の金融危機の前にも、同様の低金利政策と安易な融資が行われ、住宅バブルとそれに続く金融崩壊を招いた。
4. 政策的な意味合い
オーストリア学派の理論によれば、自由市場に金利を設定させる(※市場に任せる)ことが長期的な経済発展の鍵である。そのためには、中央銀行の介入を減らし、貯蓄者(※貸し手)と借り手が自然に調整できるようにする必要がある。健全なマネーを維持し、金融市場への政府の介入を最小限に抑え、市場のシグナルが自由に流れるような雰囲気を作ることが、政策の中心的な目標であるべきだ。
さらに、個人の貯蓄と金融知識を育成することによって、力強い経済の基盤を支えることになる。人々が「賢明な貯蓄」と「投資の価値」を認識することで、経済全体がより安定した持続可能な成長を遂げることができる。
5. 結論
金利は、自由に変更できる単なる変数などではなく、経済内の人々の集合的な時間選好を表す基本的な市場シグナルである。
オーストリア学派は、市場に金利を設定させることの重要性を強調し、中央銀行の介入に伴うリスクを強調する。
これらのガイドラインに従うことによって、「好況と不況のサイクルに伴う罠」を回避し、真の持続的な経済繁栄の条件を作り出すことができるだろう。
■
最後までお読みくださりありがとうございました。
「金利」というものの考え方について、そもそもが主流派経済学とオーストリア学派では違うので、混乱されたかたもいらっしゃるかもしれません。「オーストリア学派は今の常識とは合わない」という意見も聞くことがあります。しかし、その常識だと思い込んでいるものが、悲惨な経済危機の根本原因となっている可能性もあります。物事の根本を考えてみることは、重要なことだと思います。
人々の時間選好に反した強制的な金利操作によって、市場シグナルが歪み、投資の失敗へつながることの詳しい解説は、「通貨・銀行信用・経済循環」(ヘスース・ウエルタ・デ・ソト著、蔵研也翻訳)の第5章(P177~P247)を御覧ください。
編集部より:この記事は自由主義研究所のnote 2025年3月24日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は自由主義研究所のnoteをご覧ください。