前回の「プーチン大統領の観測気球と停戦の行方」と題した記事で、プーチン大統領が国連暫定統治をウクライナに導入したらどうかというアイディアを披露した発言について取り上げた。

プーチン大統領は、1999年のコソボに関するNATO軍事介入の後に国連が暫定統治を行った事例に詳しい。当時、すでにエリツィン政権大統領府高官だった。同年後半に首相代行になってから、後継大統領候補に指名され、翌年に大統領になった。その後、演説の中で、欧米諸国の対外政策を非難する際、繰り返しコソボについてふれてきている。
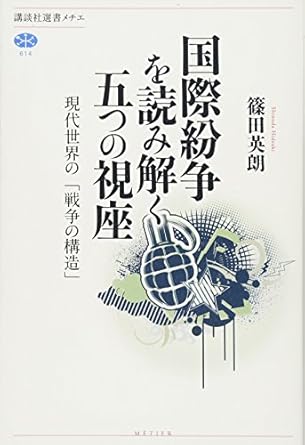
2014年にクリミア併合を発表した際にも、基本的に無関係のコソボの話ばかりをしていた。私は拙著『国際紛争を読み解く五つの視座』(講談社、2015年)を執筆するところだったので、よく覚えている。
詳しいはずのプーチン大統領なので、国連暫定統治の話を持ってきたりすることは容易にできるだろう。だが、今の状況で、実際には適用されるはずがないことも、わかっているはずだと思われる。そのため私は自分の記事に「観測気球」という語を入れてみた。
この「観測気球」に即座に反応したのが、トランプ大統領だ。暫定統治を導入して選挙をしてからでないと一切の交渉に応じない、とプーチン大統領が言ったのだとしたら、これは停戦調停に多大な努力を払っているトランプ大統領としては顔をつぶされたことになり、看過できない。そこで「私は怒っている(angry and pissed off)」といった表現で、プーチン大統領をけん制した。

日本のメディアは、「トランプはプーチンに騙されている!」キャンペーンを展開していたので、今回の発言は「遂にトランプは自分が騙されていたことに気づいた!」といった流れで受け止められているようだ。
だが、もし次の電話会談の後に、また少し違う雰囲気の発言があれば、「またトランプがプーチンに騙され始めた!」といった報道をするのだろう。残念なことに、学者・評論家層も、こぞってメディア報道にのっかることばかりを考えているように見える。
英語メディアなどで確認してみると、トランプ大統領が一連の発言の全体の趣旨が、少し異なっていることがわかる。トランプ大統領は、「われわれは良い関係にある、もし彼が正しいことをすれば怒りはすぐに霧散する、今週中に電話する」と言って、話を結んでいる。

トランプ政権登場によって大きく変わったことの一つが、国連安保理決議が採択されるようになった点であることは、前回の記事で書いた。2月24日の早期停戦を要請する国連安保理決議を棄権したイギリスとフランスは、「有志合同軍」派遣の構想の推進を急ぎ、停戦後の平和活動で、国連が主な役割をとることをけん制しようとしている。
しかし米・露・中が合意した国連安保理決議が出れば、その権威は絶大だ。欧州以外の諸国から反発あるいは懸念の声が上がるとは思えない。ウクライナ単独支援にこだわる欧州(とカナダ+オーストラリア)がむしろ少数派に追い込まれていく構図が、さらに強まっていくだろう。
プーチン大統領は、この情勢をふまえて、国連カードの最大限の有効活用を狙っている。もちろん、現在、戦場で優位を保って支配地を広げているロシア側に、早期の停戦を焦る動機がなく、引き延ばしを図っていることは、確かだろう。だがロシアがトランプ大統領の停戦調停努力に大きな関心を寄せていることもまた確かと思われる。時間を稼いでロシア軍の進軍の様子を見守りながら、交渉の落としどころも探っている。
落としどころの最終的な具体的詳細は、交渉を通じた人間的な作業の後に決まってくることなので、完全に予測することは難しい。
ただし前回の記事で参照したウクライナを三地域に分ける仕組みは、米露間では、もうほとんど叩き台のようなものだろう。その線引きの具体案が、駆け引きを通じた折衝対象になると思われる。
いずれにせよ、紛争当事者のトップ同士がお互いに会うのを拒絶しているような状況で、超大国アメリカが調停人となって間に入って、交渉が進められている。
その結果、注目度の高さもあり、ロシア、ウクライナ、そしてアメリカの首脳が、あえて第三者向けのメディア対応やSNSなどの機会を通じて、交渉に影響を与える発言をあえて行う「劇場型」の交渉となっている。毎日ニュースで報道されているロシア・ウクライナ戦争の特殊な性質によるものだ。

トランプ大統領(ホワイトハウス X)、ゼレンスキー大統領(同大統領インスタグラム)、プーチン大統領(クレムリンHP)
だが、いかに「劇場型」で進んでいると言っても、交渉は交渉だ。その点も忘れず、冷静に事態の推移を見守って分析していく態度が必要だ。万が一、見ている日本が浮足立ってきて、地に足の付かない発言や行動に引き寄せられてしまったりすると、大きなリスクを抱えこんでいってしまうことになる。
■
国際情勢分析を『The Letter』を通じてニュースレター形式で配信しています。
「篠田英朗国際情勢分析チャンネル」(ニコニコチャンネルプラス)で、月2回の頻度で、国際情勢の分析を行っています。














