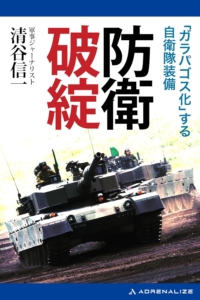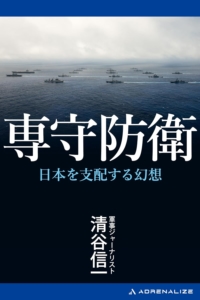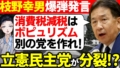以下の記事は海自輸送機の稼働率に関するものです。低稼働率自体を報道することは評価する。ですがいかに記者クラブメディアの記者が専門知識がなく、ないならばそれを補う努力をしていないかの見本のような記事です。
【独自】日本を守れるか? 飛べない海自輸送機、なぜ…【きっかけ解説】

海上自衛隊はC130Rという輸送機を6機保有しています。この輸送機が故障や不具合などで1機も飛べない期間が多いことが政府関係者への取材でわかりました。
近年6機中、1機も飛べないという状況が数週間続くことが複数回ありました。導入以来「飛べる機体を1~2機にするだけで大変な苦労をしている状況」だというんです。
離島への定期便が欠航することもあり基地への物資補給に影響が出ています。航空自衛隊に協力を仰いだり、運用担当者が事前に飛べる数を予測し、「物資を多めに送っておく」ことで、しのいでいるといいます。
主な原因は「機体の古さにある」といいます。そもそも、この機種の導入のきっかけは東日本大震災への対応でした。
支援物資などの輸送のため、海自の当時の輸送機YS-11の飛行時間が急増。想定よりも耐用年数が早まったため、急きょ選定を行いアメリカ軍ですでに退役し砂漠で保管されていた空中給油機に白羽の矢をたてたのです。
輸送型に改造して、1機およそ20億円諸経費こみで、6機約150億円で中古購入しました。航空機としては破格といえます。
海自のC-130Rは2011年の東日本大震災の補正予算の復興予算を使い、災害対処を口実にして、急遽調達されました。

実はこれは当時から怪しい人間が噛んでいた、胡乱な話だったと言われていました。
維持整備の費用がかなり高額なんです。直近ですと、2022年から5年間、およそ128億円で民間の会社と維持整備の包括的な契約を結んでいます。
それでも、機体から多くのさびやひび割れが見つかったり機内装備の経年劣化により現場からは「直しきれない」という悲鳴があがっているそうです。
これはおかしな話だと気が付けないといけないが、取材側に知識がない。空自のC-130Hだって30年選手ですよ。基本的に同型機です。それと比べてどうなんだ、という話ですよ。なぜ海自のRがそれほどひどいのか。そこは取材すべきでしょう。

海上自衛隊 C130R 防衛省・自衛隊HPより
率直に申し上げれば使いものにならない、クズを掴まされたということですよ。その経緯を防衛省は明らかにすべきです。
―新たな輸送機を買うなど、根本的な改善策はとれないのはなぜなんでしょう?
政府関係者からは「輸送という任務が軽視されてきたのではないか」との指摘が上がっています。「ミサイルやイージス艦など、直接戦闘に用いる装備品のほうが予算が通りやすい傾向にある」というんです。
その傾向がないとはいわないが、基本的には第日本帝国海軍海上自衛隊は誤りを犯さずという無謬と隠蔽体質があるからです。黙っていればバレないんだという組織文化があります。だから問題がある事自体を認めないから対策を取ることがない。稼働率が3割のP-1も同じです。
防衛省の今年度予算をみても概算要求に盛り込まれた戦闘機や艦船などの中で、財務省などとの折衝の結果、数が削られたのは輸送関連の船舶のみでした。輸送機をめぐっては別の懸念もあります。
別にこれは問題ない。輸送船舶は新設の部隊であり、多少減らされたところで体制に影響はない。
C130Rの代わりとは別に、関係者によりますと石破総理は大型輸送機C17の購入の検討を防衛省に指示しました。
C17はアメリカ製で全世界で使われてきましたが、離着陸に長い滑走路が必要で使用できる空港が限定されるとの課題が指摘されています。
また、C17は製造が終了している機種で、関係者からは「購入当初はよくても、修理を重ねるなかでC130Rと同様に修復不能な機体も出てくるのではないか」つまり「C130Rの二の舞いになるのでは」という懸念が出ているんです。
―このニュースで一番伝えたいことはなんですか?
先を見据えた機種選定です。
いや、基本的な専門知識もなく取材対象に嘘をつかれてもわからないあなた方がそれをいうか?しかもC-130RとC-17の話を一緒にするのは味噌もクソも一緒です。単に中古というだけで木に竹を接ぐようような記事になっています。
中古が駄目ならばなんで我が国は自衛隊で使っていた中古の練習機を他国に供与したのでしょうか?
記者は、中古機はすべて稼働率が低いと思っているのでしょう。ですがエアラインだって中古の機体を売買していますよ。そして民間旅客機は軍用機に比べて遥かに酷使されているわけです。だから相応の査定をして、コストに合う中古を買ったりリースしたりしているわけです。かつて英空軍ですら空中給油機は民間の中古旅客機を買って改造して使っていました。そのような中古機に関する知識が記者には欠如しているのでしょう。
C-17はSTOL機能が高く、その気になれば千メートル程度の滑走路でも運用できます。そのための機体ですから。単に空自関係者の世論操作目的の発言を事実であるかのように吹聴するのは記者クラブメディアの悪いところです。
修理を重ねるなかでC130Rと同様に修復不能な機体も出てくるのではないか
じゃあなんで空自のC-130Hの稼働率はそこまで低くなんですか?という話になります。ソースを話を頭から信じるのはリテラシーの欠如であり、記者としては落第レベルです。
航空機は何回離着陸をしたかによって寿命が異なります。例えば東京と大阪を日になんども飛ぶような機体は同じ飛行時間でも東京、パリ間を飛ぶ機体よりも痛みが激しいわけです。そういうところを精査する技術は確率されています。
そしてC-17の導入の是非はおいておいても、中古の機体を採用するのであれば、その機体の履歴や具合を事前にチェックするのは当たり前の話です。想定内の状態である機体を調達することに問題はない。更に申せば米空軍は今後も大型輸送機調達の予定はない。これから立ち上げても調達完了まで最低でも20年以上はかかるでしょう。そうであれば今後も機体サポートやアップグレードは行われるということです。
「海上輸送群」が新設されるなど輸送に光が当たりつつありますが、島しょ部への物資輸送を滞らせないために、検討時のニーズでその場しのぎの購入をするのでなく5年、10年後も見据えた機種選定が必要ではないかと思います。
ぼくは過去何度も歴代の空幕長には輸送機のポートフォリを聞いてきましたが、あなたがた記者クラブはなにかやってきたのか?あるいはぼくの質問の後追いの取材をしてきたのかと聞きたくなります。
別に新聞やテレビが専門記者と同じ視線である必要はありませんが、防衛省や自衛隊を取材するならば最低限の知識と教養は必要なはずです。
ところが記者クラブは自分たち意外の媒体やフリーランスを排除して来たので、そのような専門記者のアクセスを阻害してきました。自分たちが国民の知る権利の敵であることを自覚すべきです。
それから防衛省は主要装備の稼働率を公開すべきです。実際の調査は会計検査院の人員を強化して任せたほうがいいかもしれません。
同盟国の米国はやっていることです。
公開するデメリットよりも、公開しないデメリットが大きい。無敵皇軍のプロパガンダしかやっていないから、国民は自衛隊に過剰な信頼を寄せている。有事になったら実は役に立ちませんでした、では大問題です。
ですから稼働率やミッション達成率、飛行時間あたりコストなどの公開と同時に、問題があればそれはどこに問題があるのかをきちんと分析してい公開するべきです。
何かというと防衛省は「手の内を明かさない」といいますが、明かさないデメリットの方が圧倒的に大きい。
こういう基本的なデータを国会や納税者に示さずに、防衛費だけ上げろというのは詐欺みたいなものです。
同盟国がやっていることをなぜできないのか?
日本政府や防衛省は同盟国は間抜けで、保安体制がなっていなからだ、と思っているのでしょうか。
■
■
財政制度分科会(令和6年10月28日開催)資料
防衛
防衛(参考資料)
財政制度分科会(令和6年10月28日開催)資料
防衛
防衛(参考資料)
編集部より:この記事は、軍事ジャーナリスト、清谷信一氏のブログ 2025年4月11日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、清谷信一公式ブログ「清谷防衛経済研究所」をご覧ください。