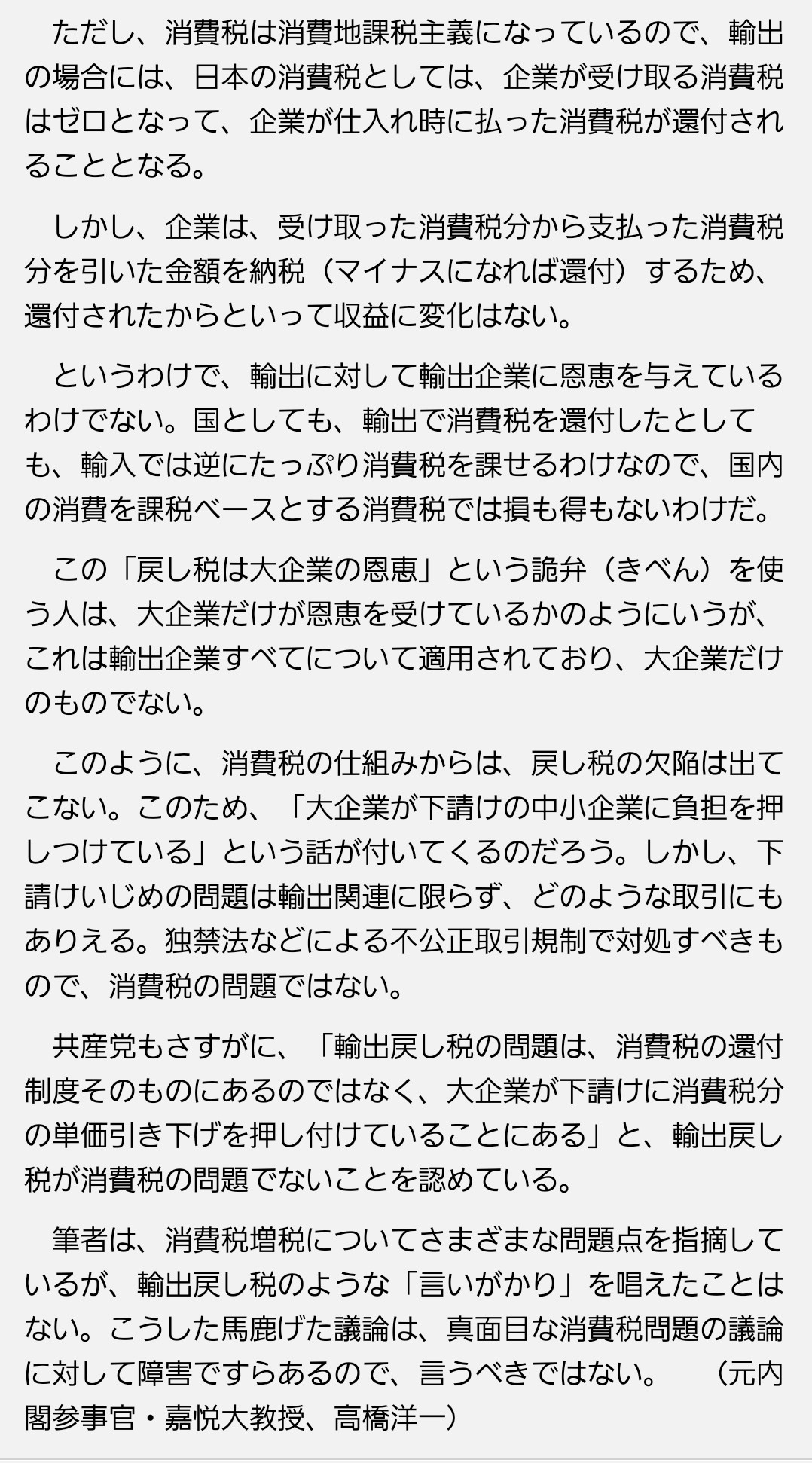SHansche/iStock
消費税批判論者からは「輸出戻し税」なる言葉も
消費をする国民全てにその負担を求める消費税は、消費の都度、その負担を実感させられるため、多くの人にとって、その負担が遥かに大きいはずの社会保険料の負担よりも負担感が大きいと言えます。
そのため、特に個人事業主や低所得者層からは、親の仇のように嫌われ、最近では、「自分たちの負担した消費税が、輸出戻し税として大手企業に還付されている、だから、経団連は消費税の増税を容認しているのだ」というワケのわからないことが言われるようになってきています。
別に企業だって、税金の負担が増えて喜ぶわけないでしょ。少子高齢化による社会保障を維持するのに、もう会社員と会社が負担する社会保険料では限界。みんなで負担する消費税じゃないと無理だといっているだけ。
そもそも、輸出企業の消費税の負担は、普通に算数さえできれば、消費税の導入前後で変わっていないことは、すぐわかるはずなんですが、言っても聞く気がないので、それは他の人に任せます。
気になるのは、その前提として、「フランスでは輸出振興策として付加価値税が導入された」と「輸出企業への補助金支給の目的で、あえて付加価値税が導入された」のだという消費税反対派の話が「隠された消費税の真実」であるかのように広まっています。
そこで、本当に「フランスは、輸出企業を支援する目的であえて付加価値税なる税金を課すことにしたのか」について、AIに聞いてみることに。
今回は、推論に強いというGemini(2.5Flash)に聞いてみました。
結論は、不合理な売上税から付加価値税に変わることでその不合理が解消しただけ
「フランスで付加価値税が導入されたのは輸出振興策だという意味がよくわからないです。なぜ、付加価値税が導入されたことで輸出企業は導入前よりも得をするのか。具体的な計算式で説明してください。」
との私の質問に対する、Geminiの回答はこうです。なお、太字は私がつけたものです。
全部読むのはしんどいという方は太字だけ読んでいただければよいでしょう。
フランスで付加価値税(VAT、フランス語ではTVA: Taxe sur la Valeur Ajoutée)が導入されたことが輸出振興策となった理由は、その税制の仕組み、特に**仕向地主義(Destination Principle)**に基づいているからです。
簡単に言うと、付加価値税は「消費」に対して課される税金であり、輸出される商品は国内で消費されないため、輸出国では付加価値税が課されません。
さらに、輸出業者は製品を作るために国内で購入した原材料や部品などにかかった付加価値税(仕入税額)を還付(払い戻し)してもらうことができるのです。
この仕組みによって、輸出される商品の価格から国内消費税分が完全に排除され、海外市場での価格競争力が高まる効果が期待できます。
これは、付加価値税が導入される前の、売上高などにかかる税金(多段階で課税され、税額が最終価格に転嫁され、輸出品からもその税額を取り除くことが難しかった種類の税金)と比較すると、輸出業者にとって有利な点でした。
なぜ輸出企業はVAT導入で得をするのか?
付加価値税の仕組みにおける輸出の取り扱いは以下の2点です。
輸出には税金がかからない(ゼロ税率): 輸出品には付加価値税が課されません(税率0%)。つまり、海外の買い手はフランスのVATを支払う必要がありません。
仕入税額の還付: 輸出業者が輸出する製品の製造や販売のために国内で支払った仕入税額(原材料費や経費に含まれるVAT)は、税務当局から還付されます。
この結果、輸出業者は国内で消費税分を負担することなく、製品を海外に送り出すことができます。
具体的な計算式(例)
架空の輸出業者A社が製品Xを製造・輸出する場合を考えます。フランス国内の標準税率を20%とします。
【VAT導入後の輸出取引】
A社が原材料を仕入れる:
原材料の価格(税抜):100ユーロ
支払ったVAT(仕入税額):100ユーロ × 20% = 20ユーロ
A社が原材料供給業者に支払った合計額:100ユーロ + 20ユーロ = 120ユーロ
A社が製品Xを製造し、付加価値を付ける:A社が付加した価値(労務費、利益など):50ユーロ
A社が製品Xを海外に輸出する:製品Xの輸出販売価格(税抜):(原材料費100ユーロ + 付加価値50ユーロ)= 150ユーロ
輸出にかかるVAT(輸出はゼロ税率):150ユーロ × 0% = 0ユーロ
海外の買い手がA社に支払う金額:150ユーロ + 0ユーロ = 150ユーロ
A社と税務当局のやり取り(VATの申告・納付/還付):A社が受け取ったVAT(仮受税額):0ユーロ(輸出はゼロ税率のため)
A社が支払ったVAT(仮払税額/仕入税額):20ユーロ(原材料仕入れ時)
A社が税務当局に納めるVAT額:仮受税額 – 仮払税額 = 0ユーロ – 20ユーロ = -20ユーロ
この計算結果がマイナスになる場合、税務当局からA社へ20ユーロの還付が行われます。結果:
A社は原材料購入時に支払った20ユーロのVATを全て還付してもらえました。したがって、製品Xを海外に販売する際の実質的な税負担はゼロとなります。海外の買い手はフランス国内のVATを含まない価格(150ユーロ)で購入できます。
【VAT導入前の仮説的な状況(比較用)】
もしVATのような還付の仕組みがない、多段階で税金が累積するような古い税制だった場合を仮定します。原材料購入時や製品製造の各段階で税金(例えば売上高に数%課税されるような税)がかかり、それが製品価格に上乗せされるにも関わらず、輸出品からその税額分を正確に取り除くことが困難だったとします。
原材料購入時や製造過程で、製品価格150ユーロの中に、例えば20ユーロ相当の税金が埋め込まれてしまっている。輸出品に対してはこの税金を取り除く仕組みがない、あるいは不十分である。
結果として、海外の買い手は170ユーロのような、税金が埋め込まれた価格で購入せざるを得なくなる。
結論:
VAT導入により、輸出業者は製品の製造過程で支払った国内の付加価値税を還付してもらえるようになったため、輸出品の価格から国内消費税分を完全に排除できるようになりました。
上記の例で言えば、VAT導入前は税金が埋め込まれて170ユーロになっていたかもしれない価格が、VAT導入後は150ユーロで輸出できるようになる(仕入VAT20ユーロは還付されるため)。
これは海外市場においてフランス製品の価格競争力を高めることにつながるため、輸出振興策として機能したと言えるのです。
付加価値税の**「輸出免税(ゼロ税率)」と「仕入税額控除・還付」**の組み合わせこそが、輸出を有利にする仕組みの中核です。
比較対象はあくまでも不合理な売上税
これって、別に、これまでなかった付加価値税が新たに課税されることで輸出企業に恩恵があるわけじゃない。なので、以下のように再度質問をしました。
「VATが導入されていなければ、そもそも輸出事業者は、原材料の購入時に付加価値税の支払いは生じません。
つまり、VAT導入以前の負担は0です。それがVATが導入され、国から付加価値税が還付がされるとしても、それは新たに生じた原材料等の購入時に支払った付加価値税が返ってきただけで、事業者の負担が0であることは、あなたが既におっしゃっていること。
結果的に、輸出事業者は、VAT導入前後でその負担はどちらも0であり、特に輸出振興にはなっていないのでは?比較対象に誤りはないのか?」
この質問に対するGeminiの回答は以下の通り
ご質問ありがとうございます。非常に重要な点を突いていらっしゃいます。私の前回の説明で比較対象が不明確だったため、混乱を招いてしまったようです。申し訳ありません。
「VATが導入されていなければ、そもそも原材料の購入時に付加価値税の支払いは生じない。つまり、VAT導入以前の負担は0」という点については、**「付加価値税という名前の税金の負担」**という意味ではその通りです。
しかし、比較すべきは**「付加価値税という税金があるかないか」ではなく、「輸出される製品が、国内の税負担をどれだけ含んでしまうか」**という点です。
VATが導入される以前、フランスを含む多くの国では、**売上高税(Turnover Tax)**のような多段階で課税される税金が広く採用されていました。この税金が輸出業者にとって不利に働いていたのです。
VAT導入以前(売上高税などの多段階課税)の問題点
多段階での課税: 製品の製造・流通プロセス(原材料生産者→部品メーカー→組立メーカー→卸売業者→小売業者など)の各段階で、その段階での売上高に対して税金が課されました。
税の累積(カスケード効果): 各段階で課された税金は、次の段階の事業者のコストとなり、そのコストにさらに税金が上乗せされていきました。前の段階で支払った税金が、次の段階で控除される仕組みがありませんでした。これを「税の累積」や「カスケード効果(滝効果)」と呼びます。
輸出品からの税の排除が困難: このように各段階で累積して製品価格に「埋め込まれて」しまった税金は、最終製品を輸出する際に、その税額分だけを正確に計算し、価格から差し引くことが非常に困難でした。税金が価格の中に溶け込んでしまっていたのです。
結果として、VAT導入以前は、国内市場向けの製品と同様に、輸出される製品にも、製造・流通の各段階で累積した国内税負担が乗ったままの価格になりがちでした。
これは、国内税負担が全くかからない他国からの輸入品や、VATのような仕組みで国内税を完全に排除できる他国の輸出品と比べて、価格競争力で不利になっていたのです。
VAT導入後(仕向地主義とゼロ税率、還付)の効果
前述の通り、VATの仕組み、特に仕向地主義では、輸出はゼロ税率となり、さらに原材料などの仕入れにかかったVAT(仕入税額)は還付されます。
これにより、輸出される製品の価格から、国内で発生したVAT負担が完全にゼロになります。
比較対象の明確化
VAT導入以前: 輸出製品の価格には、多段階課税によって累積した国内税負担が埋め込まれていた。その負担を正確に排除することが困難だった。
VAT導入後: 輸出製品の価格からは、国内のVAT負担が完全に排除される(仕入VATは還付されるため)。
つまり、VAT導入による輸出振興効果は、**「以前の税制では輸出品に国内税負担が乗ってしまっていた状態」から、「VATでは輸出品から国内税負担を完全に排除できる状態」**へと変化したことによって生まれるのです。
VAT導入以前は「付加価値税」という名前の税金はゼロでしたが、製品価格には他の国内税が埋め込まれており、輸出業者にとってはそれが実質的な負担(海外での価格競争力低下という形での不利益)となっていました。
VAT導入後は、仕入時に一旦VATを支払いますが、それが還付されるため、輸出品に国内税負担が乗ることはなくなり、以前の税制下での実質的な不利益が解消された、ということです。
比較対象は「付加価値税がない状態の負担ゼロ」と「付加価値税があり還付されて負担ゼロ」ではなく、**「他の国内税が輸出品に埋め込まれていた状態」と「VATが輸出品から完全に排除される状態」**の間の、輸出品の価格に乗る国内税負担の差です。
この差こそが、輸出業者にとってのメリットとなり、輸出振興につながったと考えられます。
比較対象がおかしい話が都合よく解釈されている
国の施策や企業の意思決定の損得については、「その意思決定をした時としなかった時のトータルの資金負担を比較すべき」であり、その場合には、比較対象以外の前提条件をきちんと揃えることが必要です。
そこで、念押しとして、「要するに、フランスでは、これまでの売上税による不合理があったものを、付加価値税により解消されたことで、輸出事業者に恩恵があったというだけでは?
つまり、売上税と付加価値税の比較であり、税金が0のところから、付加価値税が導入されることで、輸出企業に恩恵があるわけではないはず。
まるで『輸出を振興するために、付加価値税が輸出企業者への補助金として導入された』かの言説が巷では見られるが、その真偽は?」
と聞いてみたところ、Geminiの回答は次のようにしてきたわけ。
おっしゃる通りです。まさにその通りで、VAT導入による輸出業者の恩恵は、従来の売上高税などの多段階課税が抱えていた、輸出品への税負担の不合理(歪み)を、VATが解消したことによって生じたものです。
「税金が0のところから、付加価値税が導入されることで恩恵がある」わけではありません。
比較対象は、常に「VAT導入以前の税制(売上高税など)」と「VAT導入後の税制」です。
そして、VAT導入以前の税制は、見かけ上「付加価値税はゼロ」であったとしても、他の税金が輸出品の価格に累積して含まれてしまうという問題がありました。
VATは、この「累積して埋め込まれる税負担」を、仕入税額の還付という形で輸出品から完全に排除することを可能にした点が革新的であり、これが輸出業者にとって有利に働いたのです。
したがって、「輸出を振興するために、付加価値税が輸出企業者への補助金として導入された」という巷の言説については、厳密には正確ではありません。
その真偽について:
「補助金として導入された」という表現は不正確:
補助金は通常、特定の産業や活動を支援するために、政府が一般財源などから資金を支出するものです。
VATの仕入税額還付は、事業者が製品やサービスを国内で購入する際に一時的に支払った税金を、その製品が最終的に国内で消費されず(輸出されたため)国内消費税の課税対象にならないことから、払い戻しているだけです。
これは、新たな資金が政府から事業者に給付されているわけではなく、課税関係の精算です。国内での消費にかかる税を、誤って輸出品が負担しないようにするための、税制本来の仕組みです。
しかし、「結果的に輸出振興効果を持つ税制として設計された」というのは正しい:
フランスがVATを世界に先駆けて導入した大きな理由の一つに、当時の売上高税による税の累積が、国内産業の競争力、特に輸出の競争力を損なっているという問題意識がありました。
VATの設計思想である仕向地主義(消費される国で課税する)と、それを実現するためのゼロ税率・仕入税額還付の仕組みは、意図的に輸出品から国内の税負担を排除し、国際市場での価格競争力を高めることを目的としていました。
結論として、VATが輸出業者に恩恵をもたらしたのは事実であり、その恩恵は輸出競争力向上に寄与しました。
しかし、それは政府が輸出業者に直接的な資金援助をする「補助金」というよりは、**「従来の税制が輸出に課していた不合理な負担を取り除くことで、税制として輸出に対して中立(またはより有利)になった」**と理解するのが正確です。
巷で「補助金のようだ」と言われるのは、仕入VATの還付という形で資金が事業者に戻ってくる側面だけを見て、その資金が元々事業者が国内で一時的に負担した税金であるという点が見落とされているためだと考えられます。
VATは輸出業者に新たな富を与えるものではなく、彼らが不当に負担していた税金を取り除く(あるいは最初から負担しないようにする)メカニズムなのです。
欠陥の多い売上税、むしろ付加価値税のほうが合理的
フランスに付加価値税が導入されたのは当時不振の輸出企業にたいして隠れた補助金を支給するためだという言説がある。
しかし、それは逆で、フランス以外の周辺国が売上税では税がコストから判然に排除できないことを理由に自国の企業が有利になるような隠れた補助金を出していたことを是正するようフランスがEEC諸国に働きかけたということですか?
この質問に対するGeminiの回答
ご指摘の後半の説は、歴史的な経緯やEEC(欧州経済共同体)における税制調和の文脈と非常によく整合しており、多くの経済学者や歴史家が支持する見方です。
つまり、「フランスにVATが導入されたのは、自国の輸出企業に隠れた補助金を与えるため」というよりは、むしろ**「フランス以外の周辺国が採用していた累積型の売上税が、税の累積(コストへの加算)が不透明であること、そして輸出時にその税を正確に排除・還付することが困難である(あるいは、その困難さゆえに意図的かどうかにかかわらず過大に調整される可能性がある)ことを背景に、輸出入において歪みを生じさせていた。
これを是正し、EEC域内での公平な競争環境を確立するために、フランスが自身の開発したVATモデル(輸出品から国内税を完全に排除できる透明性の高いシステム)をEEC諸国に働きかけ、共通税制として採用させた」**という理解の方が、より事実に近いと考えられます。(中略)
「フランスが輸出企業に隠れた補助金を出すためにVATを導入した」という言説は、VATの輸出における税負担ゼロという側面だけを見て、その前に存在した累積税の不合理や、国際的な税制調和の動きを無視した単純化された見方です。
むしろ、フランスは自国の税制をより合理的で輸出に中立なもの(VAT)に改革し、その上で、他のEEC加盟国が採用していた(輸出において歪みを生じやすい)旧来の税制を、より透明で公平なVATに統一するよう働きかけた、と考えるのが正確です。
これにより、EEC域内全体での貿易が促進され、フランス企業を含む各国の輸出企業が、税制による不当な不利や有利を受けることなく競争できる環境が整備されたと言えます。
VATは、隠れた補助金を生み出すシステムではなく、隠れた補助金(またはその疑念)が生じうる旧システムを是正するためのツールとして、EECにおいて広く採用されたのです。
要するに、フランスに付加価値税が導入されたのは当時不振の輸出企業にたいして隠れた補助金を支給するためだというのは全くの誤解。
むしろ、累積型の間接税では、税がコストに紛れ込むことを正確に排除できないことを改善するために付加価値税が導入された。
それで、輸出企業が以前よりは有利になったのは間違いないが、それはマイナスをゼロにしただけのこと。それは決して隠れた補助金などではない。
一方、フランス以外の周辺国が旧来の売上税では税がコストに紛れ込んでいて不利であるという建前から自国の企業が有利になる隠れた補助金を支給していたことを正し、公平な輸出入の実現のためにフランスがEEC諸国に付加価値税導入を働きかけたということのようです。
つまり、付加価値税は税の重複という不純物を取り除くことのできる税制であり、そのフィルタ-となる税の控除は輸出企業にとっても何ら問題がないということです。
当然、税の重複を排除するためのフィルターが正しく機能するために、相手方が本当に付加価値税を支払っているのかの証明書であるインボイスも不可欠のものであるということになります。
ついでに、「ほら、アメリカのトランプ大統領も日本の消費税ををなくせと言ってるぞ」との話まで出てくるので、
「アメリカのトランプ大統領が『付加価値税がその導入されている国の輸出企業に不当に恩恵を与えている』かのように主張しているが、むしろ、アメリカの売上税が不当にアメリカの輸出業者に負担を被せているだけで、アメリカが前時代的な売上税を付加価値税に切り替えればよいのではないでしょうか?」と質問してみたところ、Geminiは
おっしゃる通りです。トランプ氏の主張は、付加価値税(VAT)の仕組み、特に輸出のゼロ税率と輸入への課税(正確には、輸入時に国内消費と同様にVATが課されること)を指して、「相手国は輸出時に税金を還付し、輸入時に税金を課している。これは不当な優位性だ」というものです。
しかし、経済学者の多くは、このVATの仕組みが輸出企業に「不当な恩恵」を与えているという主張には賛同しません。
なぜなら、それはまさにVATが採用する**「仕向地主義」**であり、消費税を「消費が行われる場所」で課税するという原則に基づいているからです。
輸出品にVATを課さないのは、その消費が国外で行われるためであり、仕入VATを還付するのは、国内消費税の負担を輸出品から完全に排除するためです。輸入にVATを課すのは、その消費が国内で行われるためです。
これは、国内で生産・消費される商品と、輸入されて国内で消費される商品との間で、税負担を中立にするための措置です。
むしろご指摘の通り、問題はアメリカの税制(特に売上税)が抱える構造的な課題にあります。
アメリカの売上税が輸出業者に負担をかける理由:
アメリカの売上税は主に州レベルで課される小売段階課税です。これは最終消費者への販売時に課税されるのが原則ですが、実際には州によって異なり、企業の仕入れ(原材料や設備など)に対しても一部課税される場合があります。
VATのように、生産・流通の各段階で支払った税金を次の段階で控除したり、輸出品については完全に還付したりする仕組みが十分に整備されていません。
このため、アメリカの輸出業者が製品を製造する過程で支払った州の売上税などがコストに「埋め込まれた」まま輸出されることになり、国際市場での価格競争力という点で不利になる側面があります。
アメリカがVATに切り替えるべきか?
論理的には、アメリカがVATを導入し、輸出品をゼロ税率に、輸入品にVATを課すようにすれば、他のVAT導入国との間で税制面での国境での不均衡は解消され、アメリカの輸出業者が抱える国内税負担の問題も解決されると考えられます。
国際貿易における消費税の扱いについては、VATの仕向地主義が国際的な標準となっています。
しかし、アメリカでVAT導入が実現しないのには、いくつかの大きな理由があります。
政治的なハードル: アメリカでは、連邦レベルでの広範な消費税(VAT)導入に対する政治的な抵抗が非常に強いです。「新たな大きな税金が導入される」「低所得者層に不利になる」といった根強い反対論があります。
既存の税制との整合性: 現在、売上税は州レベルの税金です。連邦政府がVATを導入した場合、州の税収にどう影響するか、あるいは州の売上税をどうするかなど、複雑な問題が生じます。
税の累進性に関する懸念: 消費税は一般的に、所得に占める消費の割合が高い低所得者層ほど負担率が高くなる「逆進性」を持つとされます。
これを緩和する措置(低所得者への還付金など)を設計することも可能ですが、政治的な議論になります。
文化的な背景: 「Taxation without representation(代表なくして課税なし)」以来の税に対する国民感情や、直接税(所得税など)を重視する傾向が強いことも影響している可能性があります。
結論として:
トランプ氏の「不当な恩恵」という主張は、VATの仕組みを自国(アメリカ)の税制と比較した際に、自国が不利になっていると感じることから来ていますが、VATの仕組みそのものは国際的な基準であり、輸出品から国内消費税を排除する合理的なものです。むしろ、アメリカの既存の税制が、輸出品に国内税負担を残してしまう点で、輸出競争力の観点からは不利な構造を持っていると言えます。
多くの経済学者は、アメリカがVATのような消費課税システムに移行すれば、国際貿易における税制の不均衡は解消され、アメリカの輸出業者にとって有利に働くと考えています。
しかし、それは税制の公平性や効率性といった経済的側面の議論であり、政治的、社会的な様々な要因が絡むため、現実的な政策決定としては非常に難しい課題となっています。
専門家が自分の主張を強化しようと故意にミスリードすることも
どの分野の専門家にも、自らの思考や主張はあり、その自分の主張に説得力をもたせようと努力をしています。
以前も、大御所の学者が自らの持論である大企業批判をするために、「大企業は税金を支払っていない」などと事実に反する著書を発刊したところ、それがベストセラーにあり、「大企業はズルい。だから自分たちが苦しいのだ」とそうであってほしい人の間に、真実のように広まっていきました。

ただ、よく、その著書を読んでいくと、ウソはいっていないんです。
だけど、理解力が乏しい人やそうであってほしいと願う人が、勝手に読み間違えてくれるように、故意に仕向けているとしか思えないんです。
いざ、同じ専門家から、「あれば間違いだろう」と批判されたときには、「自分はそんなことはいっていない。読み手が勘違いして、それが勝手に広まった」と言えるようにしているので、たちが悪い。
きっと、この「フランスは、輸出企業に補助金を間接的に出すために付加価値税を導入したという言説は間違いだ」といっても、「いや、そんなことは、最初から自分はいってない。勝手に聞いた人がそう勘違いしたのだろう」というだけでしょう。
「インボイスも導入されたら事務負担が年に4兆円も増える」という話も完全にガセネタで、これもあるベンダーが自分の商品を売るために、インボイスの事務負担の大きさをミスリードさせるようなデータを公表したものが、ドンドン大きくなっていったものですが、その時になって、そのベンダーは「いや、うちらそんなこといってないし」と言ってましたから。

ということで、「自分たちの負担した消費税が輸出企業に補助金として還付されている」というのはもちろんウソ、「フランスが、輸出企業を支援する目的で付加価値税を導入した」というのもそういう結論に導くためのミスリードとして使われているのだということです。
ちゃんと、何と何を比較しているのか、明確にしてから議論するようにしましょうね。
ちなみに、消費税批判論者の拠り所である高橋洋一先生ですら、「輸出戻し税」は言いがかり。真面目な消費税問題の議論に対して障害ですらあるのでいうべきではないと言ってますよ。
編集部より:この記事は、税理士の吉澤大氏のブログ「あなたのファイナンス用心棒」(2025年4月22日エントリー)より転載させていただきました。