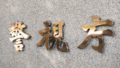黒坂岳央です。
部下が上司を選ぶ「上司選択制」という新しき制度が一部の企業で始まっている。いわゆる「上司ガチャ」を防止し、若手退職理由の「上司との相性が悪い」を解消する狙いがあるのだろう。
だが制度を導入する企業はまだ少なく、評価も割れている。果たして組織の足腰を強くする「神制度」になるのか、それとも現場を混乱させるだけの「ダメ制度」なのか。国内外の事例とデータをもとに、多面的に検証したい。

Peshkova/iStock
さくら構造の取り組みと初期成果
日本企業で最初期の事例が、さくら構造株式会社だ。
2019年に社員数40名規模で始めたあと、離職率が一年目に6.1%→2.5%へ低下したと同社は公表している。
選ばれた上司は人事評価に加えて部下満足度も査定項目となり、結果として「教え方がうまい」「フィードバックが速い」マネージャーが高く評価される傾向が強まったという。
海外はどうなのか?
まず考えたいのが、この制度が日本特有の「ガラパゴス制度か?」という点である。
結論から言うと制度名こそ違うものの、上司やリーダーを社員が選ぶ文化は海外にも存在する。
ブラジルのSemco社は従業員が新しい管理職候補を面接し、最終的に「自分たちの次の上司」を投票で決定する制度を採用していることで知られる。
また、イギリスのHappy社は社員が「この人に上司になってほしい」と指名でき、合意が取れればその場でライン変更。尚、管理職になりたくない人は専門職コースに転籍できる。
多くの企業で採用されているような制度ではないが、調べると海外で類似の事例は存在するようなのだ。
上司選択制度はアリか?なしか?
SNS上では上司選択制度に対して、大きく意見が割れている。
賛成派の意見としては、自ら上司を選ぶことで、「上司ガチャ」を回避でき、仕事のモチベーションや満足度が向上し、生産性の向上につながる。また、上司側も部下から選ばれる人材を目指すので企業がホワイト化する。ざっくりこのようなものだ。
その一方で反対派の意見は上司の選択が頻繁に行われると、組織の安定性が損なわれるというリスクや、上司の選択が人気投票のようになり、実力や適性よりも「気楽な人間関係」が重視されるリスクがあるというものだ。
筆者は「反対」
賛成・反対両派の主張を踏まえた上で、筆者は「上司選択制度は、安易に導入すべきではない」という立場を取りたい。理由はシンプルで、企業という組織において“働きやすさ”と“成果責任”はしばしば相反する緊張関係にあるからだ。
多くのビジネス現場では、ある程度の強制力や目標プレッシャーがなければ、組織全体のパフォーマンスは維持できない。これは制度への賛否以前に、組織行動論やマネジメント論で繰り返し語られてきた前提でもある。
たとえば、過去記事で何度か書いたが、リモートワークも、数年後には多くの企業が「出社回帰」へと転じた。特に米国のメガテック各社がその先陣を切った事実は、「自由度と成果責任の両立」がいかに難しいかを象徴している。
企業の目的は利益の創出と持続的成長であり、「働きやすい環境」や「上司との相性の良さ」はあくまでその目的達成のための手段である。もちろん離職率の低下やエンゲージメント向上は重要だが、それらが“企業存続の前提条件”を脅かすようであれば、本末転倒になりかねない。勤務先が消えれば「働きやすさ」など吹き飛んでしまう。
特に、サービス業・小売・物流・製造といった現場重視の産業では、生産性向上=現場負荷の増大という構図が避けられないことも多い。
もし、部下の選好に応じて「厳しくマネジする上司」が敬遠され、「これまでの半分のペースに落とし、気持ちにゆとりを持って仕事をしましょう」と言い出す「迎合型の上司」が好まれるようになれば、部下にとって快適さは得られても、組織全体の競争力は確実に削がれる。
企業が高い報酬を支払って求めるマネージャー像とは、「一定の快適さを保ちつつ、成果に責任を持てる人材」である。その意味で、全方位から好かれる“理想の上司”が、企業にとっても最良の上司であるとは限らない。
むしろ、時には不人気を恐れず、厳しくも結果を出せるリーダーが不可欠な場面は少なくない。実際、往々にして結果を出すリーダーは厳しく、冷徹な判断をすることも少なくない。
◇
上司選択制度が機能するには、「働きやすさ」と「成果」を両立できる上司像を全員が共有し、その実現を支える制度設計と透明な評価プロセスが不可欠だ。そうでなければ、この制度は“組織の民主化”ではなく“組織の空中分解”を招く危険性すらあるだろう。
■最新刊絶賛発売中!





![[黒坂 岳央]のスキマ時間・1万円で始められる リスクをとらない起業術 (大和出版)](https://agora-web.jp/cms/wp-content/uploads/2024/05/1715575859-51zzwL9rOOL.jpg)