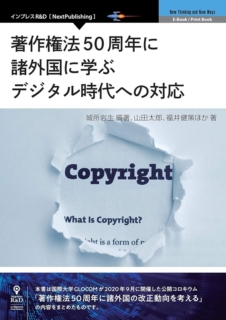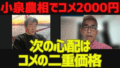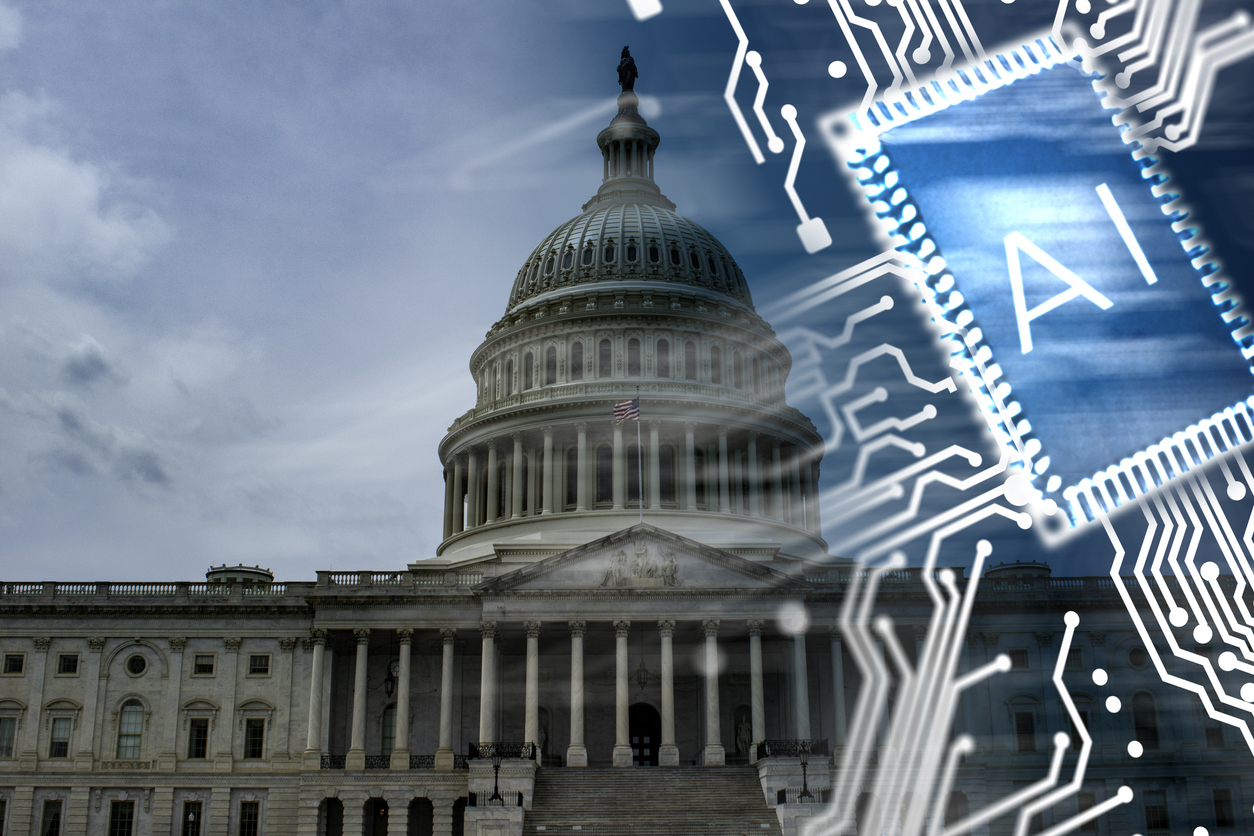
Greggory DiSalvo/iStock
前回 「米著作権局『AI訓練とフェアユース』報告書を出版前に発表」で報告書の「第4章 フェアユース」「第5章 AI訓練のためのライセンス」の概要を紹介したのに続いて、「第6章 結論」をこちらは短いので全訳する。
結論:生成AIもフェアユースで対応可能
著作権法はその歴史を通じて新たな技術に適応し、創造的活動へのインセンティブを維持しつつ、その進歩を促進してきた。これにより、米国の創造産業および技術産業は、それぞれの分野において世界的なリーダーとなることができた。
現在の生成AIシステムにおける著作物の利用は、その規模と範囲において前例のないものであるかもしれないが、既存の法的枠組みは、これまでの技術革新と同様にこれに対処することが可能である。特にフェアユースの法理は、こうした変化を柔軟に受け入れる役割を果たしてきた。われわれは、今回も同様に対応可能であると考える。
現行法の適用において、われわれは生成AIの開発の複数の段階が著作権者の排他的権利を侵害する形で著作物を使用していると結論づける。核心的な問いは、多くの意見提出者が同意するように、これら一見して侵害と見える行為がフェアユースとして正当化され得るかどうかである。
フェアユースの判断には、すべての関連事情を踏まえたうえで、複数の法定要素を衡量する必要がある。個別の事案について予断を持つことはできないが、判例に基づき次のような一般的な見解が支持される。すなわち、AIの訓練における著作物の多様な利用は、変容的(transformative)である可能性が高い。ただし、それがフェアであるか否かは、どの著作物が、どのようなソースから、何の目的で使用されたか、そして出力にどのような制御がかけられているかといった要素に依拠し、それらは市場への影響に関わる。
モデルが分析や研究といった、国際競争力にとって重要な目的で運用される場合、その出力が訓練に使用された表現的著作物の代替となる可能性は低い。しかし、既存市場において著作物と競合する表現的コンテンツを、大量の著作物を用いて商業的に生み出す行為、とりわけ違法なアクセスを通じてそれが行われる場合には、確立したフェアユースの範囲を逸脱する。
フェアユースに該当しない可能性のある利用については、継続的な革新を支えるための実務的な解決策が不可欠である。AI訓練に関するライセンス契約は、個別的または集団的な形態で特定の分野において急速に出現しているが、その普及は未だ一様ではない。自主的なライセンスの顕著な成長と、法改正に対する関係者の支持の欠如を踏まえれば、政府による介入は現時点では時期尚早であるとわれわれは考える。
むしろ、ライセンス市場は発展を続け、初期の成功事例を他の文脈にも迅速に広げるべきである。残されたギャップが埋まらないと見込まれる分野においては、市場の失敗に対応するため、拡大集中許諾のような代替的アプローチを検討すべきである。
集中許諾制度は権利集中管理団体が著作権者に代わって著作権を管理する制度で、団体の構成員のみが対象だが、これを構成員以外にも拡大するのが拡大集中許諾制度。日本では多くの音楽家が著作権の管理をJASRACに委託しているが、JASRACが権利者から管理を委託されていない楽曲についても、権利者に代わって管理できるようにする。利用者はこの制度によって権利者を探し出す手間が省けるので、権利者の身元あるいは所在が不明な孤児著作物問題の有効な解決策にもなる。
欧州は2019年に成立したデジタル単一市場著作権指令によってこの制度を採用した。米議会著作権局も2015年に「孤児著作物と大規模デジタル化」と題する報告書を発表。拡大集中許諾制度を創設するパイロット プログラムを提案して、パブコメを募集したが反対が賛成の5倍近くを占めたため、著作権局は立法を断念した。
グーグルが図書館や出版社から提供してもらった書籍をデジタル化し、全文を検索して利用者の興味にあった書籍を見つけ出す書籍検索サービスに対し、フェアユースが認められた直後だった。このため、反対理由として、大規模デジタル化はフェアユースで十分対応可能であるとする意見が約半数を占めた(詳細は城所 岩生 (著, 編集), 山田 太郎 (著), 福井 健策(著)『著作権法50周年に諸外国に学ぶデジタル時代への対応』の拙稿「第5章 フェアユース規定の解釈で対応した孤児著作物対策先進国・米国」(NextPublishing)参照)。
このように新技術に柔軟に対応できるフェアユースの存在が、今回、著作権局が生成AIについてもフェアユースで対応可能とした背景にあることは間違いない。
報告書結論に戻る。
われわれの見解では、AI分野における米国のリーダーシップをさらに促進するためには、経済的・文化的発展に多大な貢献をしているこの二つの世界的産業を共に支援することが最善である。効果的なライセンス手段は、知的財産権を損なうことなく、革新の継続的発展を可能にする。これらの革新的技術は、それを設計する革新者、コンテンツを提供する創作者、そして一般市民の全てに利益をもたらすべきである。
最後に、本報告書の前半部と同様、著作権局は現場の事実が急速に進展していることを認識している。われわれは今後も、技術、判例、市場の動向を注視し、これらの問題について議会が検討を進める際に、さらなる支援を提供していく所存である。
日本の著作権法30条の4
2018年改正により新設された30条の4「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」は以下のように定める。
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りでない。
① 略 ② 情報解析 ③ 略
非享受利用については著作権者の利益を不当に害しないかぎり、必要と認められる限度において許諾なしの利用を認めたわけだが、30条の4ただし書きの「著作権者の利益を不当に害する利用」は、フェアユースを判定する際に考慮すべき第4要素「原著作物の潜在的市場または価値に対する利用の影響」、つまり原作品の市場を奪うかどうかなので、こうした利用が認められないのは日米共通している。
問題はフェアユース判定の際の第1要素「利用の目的および性質」に対応する「『非享受目的』に該当するか」だが、文化庁は「主たる目的が非享受目的であっても享受目的が併存しているような場合は、30条の4は適用されない」としている。
元裁判官の高部眞規子弁護士も以下のように指摘する(2024年3月19日 文化審議会著作権分科会議事録より)。
今の条文は、情報解析というものを30条の4の第2号で、享受し又は享受させることを目的としない場合の例示として挙げています。そのような条文構造からは、情報解析に当たるとしながら享受目的が併存するので30条の4に当たらないという説明の仕方というのは、ちょっと難しいような気がいたします。
必要と認められる限度という、別の要件のところを考えるとか、あるいは、そもそも情報解析に当たらないという場合もあるのかもしれませんけれども、そういったことも今後考えていっていいと思いますし、著作権者の利益を不当に害するかどうかというただし書の要件を非常に狭く解釈すべきだというような説明の仕方も、いまだ判例があるわけではないので、もう少し自由な考え方が今後出されてもいいのかなというふうに感じました。
享受目的が少しでもあれば、30条の4は適用されないとする文化庁の見解は、技術面、資金面で米国や中国に太刀打ちできない日本の生成AI事業者を法制度面でも縛ることになり、競争上不利な立場に追いやりかねない。
著作権局報告書は結論の冒頭で、「著作権法はその歴史を通じて新たな技術に適応し、創造的活動へのインセンティブを維持しつつ、その進歩を促進してきた。これにより、米国の創造産業および技術産業は、それぞれの分野において世界的なリーダーとなることができた」としている。中国の追い上げが激しい生成AIでもリードを保つべく躍起となっている。
対して、日本はデジタル敗戦に象徴されるように技術産業で遅れを取った。その結果、拡大したデジタル赤字を埋めるためにコンテンツ産業に期待がかかるが、享受目的が少しでもあれば30条の4は適用されないとする文化庁の厳しい解釈に加え、前回投稿でも紹介したとおり、パロディもまだ合法化されていない。こうした法制面での制約を解消しないと、クールジャパン分野を基幹産業と位置付ける「新たなクールジャパン戦略」の成功もおぼつかない。
なお、生成AIに対しては、40件もの著作権侵害訴訟が提起されている。拙稿「米地裁 生成AIの著作権侵害訴訟に初の注目すべき判決」で紹介した事件では、当初、判事は法律解釈を示した上で陪審の事実認定に委ねた。しかし、今年2月、判事は法解釈のみで判示する略式判決でフェアユースを認めなかった。今後の著作権侵害訴訟の行方を占う上でも示唆に富む判決なので、別稿で紹介する。
■