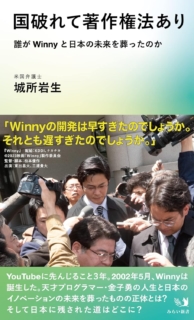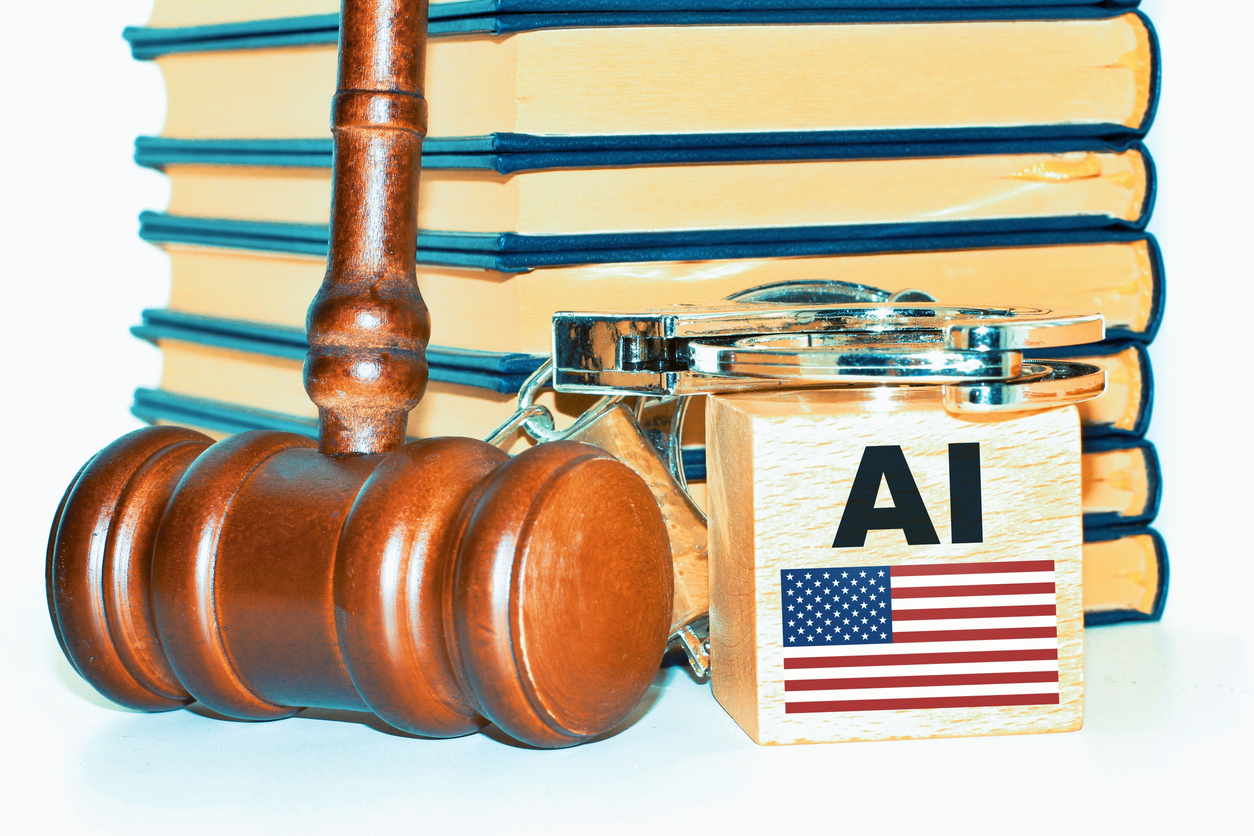
Rafmaster/iStock
米国では40件に上る生成AIに対する著作権侵害訴訟が提起されている。判決はまだだが、2月に非生成AIによる著作権侵害訴訟の判決が出た。
判決文で判事も「AIを取り巻く環境が急速に変化していることから、今回の事案は非生成AIを対象にしていることを読者に注意喚起したい」と指摘したとおり、非生成AI案件だが参考までに紹介する。
ロイター社 AIスタートアップを訴える
法律情報サービスウェストローを所有するトンプソン・ロイター(以下、「ロイター」)が、AIスタートアップのロス・インテリジェンス(以下、「ロス」)を訴えた事件で、ロイターはロスがウェストローの表現を生成物に複製するようにAIを訓練したと主張。
対して、ロスはAIが判決のヘッドノート(要約)やキーナンバー・システム(分類方法)を学習したのは表現を複製するためではなく、言語パターンを分析するためだったと反論した。
2023年、デラウェア州連邦地裁判事はまず、ロスの主張するように創造的な表現を複製する目的ではなく、言語パターンを学習する目的で、著作権のある作品を摂取し、それらをAIの訓練用に使用することは変容的利用(transformative use)であるとする法解釈を示した。その上で、変容的利用であるかどうかの判断については事実審理が必要であるとして、陪審の事実認定に委ねる判決を下した。
変容的利用は1994年、最高裁がパロディのように別の作品を作るための著作物の利用は、変容的利用あるとして、パロディにフェアユースを認めた判決が生んだ法理。今年2月、判事は上記判決を変更、法律解釈のみで判示する略式判決を下した。
フェアユースを判定する際の4要素について分析した判事は、第2要素「著作物の性質」フェアユースに第3要素「使用された量および実質性」ではフェアユースに有利と判定したが、この2要素よりも重要な第1要素と第4要素について以下のようにフェアユースに不利と判定した。
第1要素(利用の目的および性質)➡フェアユースに不利
判事はロスによるヘッドノートの利用は「商業的」性格を有しており、ロイターの利用とは「異なる目的や性格」を持たないと判定、ロスはウエストローと直接競合するツールを作成するためにヘッドノートを利用したため、変容的利用は認められないとした。
ロスは、「ヘッドノートを数値データに変換し、それをAIに入力したが、検索ツールの出力としてヘッドノート自体を表示することはなかった」と主張したが、判事は、中間的利用であっても最終的な目的が判例を検索することにあり、これはロイターのヘッドノートや
キー・ナンバー・システムが意図した目的と同じであるとした。
ロスは過去にコンピュータ・プログラムの互換性を確保するために中間的なコピーが認められた判例に依拠した。つまり「競合他社がイノベーションのためにコピーが必要だった」場合である。しかし、判事はこの理屈はコンピュータ・プログラムに関するコピーのケースに限られると判断した。
たとえば、判事はグーグル 対 オラクル事件の米最高裁判決とは異なるとした。この判決では、グーグルによるオラクルのコードのコピーがフェアユースと認められたが、それは異なるプログラム同士が連携するためにそのコードが必要だったからである(詳細は拙著『国破れて著作権法あり~誰がWinnyと日本の未来を葬ったのか』第5章「オラクルの1兆円の損害よりも社会全体の利益を優先させた米最高裁」みらいパブリッシング 参照)。
一方、今回の件では判事は、「著作権において、コンピュータ・プログラムは書籍や映画、その他多くの文学作品とは異なり、ほぼ常に機能的な目的を持つ」とするグーグル判決からの引用を紹介し、「こうしたプログラムにおけるフェアユースの考慮点は、書かれた言葉をコピーするケースには必ずしも当てはまらない」と述べた。
第4要素(著作物の潜在的市場や価値への影響)➡フェアユースに不利
ロスの製品はウェストローの市場代替物となることを目的としており、ロイターがヘッドノートをAIの訓練データとして、ライセンス供与するという潜在的な派生市場に悪影響を与える可能性があると判事は強調した。法律意見に関する情報へのアクセスに公共的な利益があるとしても、そのことは第4要素の分析には影響しないと判事は述べた。
判事は、「一般市民にはトムソン・ロイターによる法の分析を享受する権利はない。著作権は優れた法律リサーチツールのように社会に役立つものの開発を促す。開発者はそれに見合った報酬を受ける権利がある」と説明した。
以上により、判事はロスによるヘッドノートの使用はフェアユースに該当しないと判断し、ロイターの申立てに対して略式判決を下した。
判決の影響
第1要素の分析で判事は、ロスが競合するリーガルリサーチ用ツールの開発を容易にするためにヘッドノートを使用したため、変容的利用にあたらないとした。そして、冒頭でも紹介したとおり、「AIを取り巻く環境が急速に変化していることから、今回の事案は非生成AIを対象にしていることを読者に注意喚起したい」と付言した。
確かにロスはロイターのヘッドノートを利用して、ウェストローと直接競合するサービスを開発した。しかし、大規模言語モデル(LLM)は様々な情報源からの大量のデータを使用して生成AIを訓練している。
裁判所がフェアユースを判定する際、最も重視する第4要素の原著作物の市場を奪うかどうかについても、ロスのサービスはウェストローの実質的代替物となることを目的としているので、ロスの市場を奪うことになるとした。
参考までに日本法では、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」を認めた著作権法30条の4は、ただし書きで「著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りでない」としている。フェアユースのない日本でも、このただし書きが適用され著作権侵害とされる可能性は高い。
もともと、フェアユースの判定は事実に依存する部分が多いため一概には言えないが、以上から、40件に上る生成AI関連訴訟では裁判所が異なる判断を下す可能性は十分ある。
■