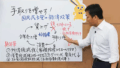トランプ大統領の報道官のレビット氏が「ハーバード大でLGBTQを学んだ人より、電気工や配管工などの人材がもっと必要だ」と述べたそうです。私は別の意味でこの言葉に激しく反発しません。先日の「AIで仕事が奪われるか」という話題ではないですが、この先、単に大学を出ただけでは食っていけない時代になるかもしれません。その時、手に職業を、と声高に叫ばれる時代が来ると確信しているのです。

metamorworks/iStock
中国や韓国も苦しんでいますが、アメリカやカナダでも「大学は出たけれど…」という問題が生じています。かつては院卒ブームもあったほど高学歴=高収入というイメージが強かったのですが、それこそハーバードを出ても役に立つかは本人次第、という時代なのだと思います。その一つの理由は知の部分においてAIが代用されるからで、一流大学卒業で賢いだけでは意味をなさなくなりつつあるのです。もしもその賢い学生たちがプラスアルファで何かのスキルを持っていればベターでしょう。
ある能力において100人の中のトップになるだけではだめだ、2つの技能の掛け合わせで100人のトップになったら100x100=10000人のトップになれる、そうすればかなり優位に人生を謳歌できるという生き方論を述べる人がいました。確かにその通りで高校、大学で中庸な成績で大学時代はバイトしてそのカネで仲間と飲んでいました、では生き残れない時代になってしまったのです。「大学生 冬の時代」の予感すらします。
レビット氏が電気工や配管工といったのは意味あることなのです。正直現場仕事は楽ではありませんがあれほど必要とされる業務もないのです。私は建設業とは新入社員の時以来ずっとお付き合いしていますが、建築物は専門職集団が力を合わせてようやく出来上がるものです。ところが時としてその一部の専門職が来ない、休む、他の現場に取られた…といった理由で穴が開くと全体が全部止まる事態になります。特に北米は建設現場で複数の専門職が同じところで同時に作業するのを嫌いますのでその専門職の穴は全体の穴につながり、工期はいくらあっても足りないことになります。
ところが日本も北米でも建設業には人気ありません。それでも北米は新移民層により業務の補完が可能なのですが日本はそれがあまり期待できず、今後、日本で電気工や配管工は貴重な存在になるでしょう。
私は日本にはそのような人材不足に陥る業種はそれ以外にもかなりあると思うのですが、その中で介護職の不足が気になっております。厚労省の発表によると23年10月時点で介護職の従事者が212.6万人で前年比2.9万人と初めて下落に転じました。この統計の発表が24年12月25日であり1年以上たってからの発表ですがトレンドから見れば大幅減少に転じていく予兆に見えます。
一方、要介護認定者は同年で705万人と伸び続けています。単純計算で一人の介護士さんが3.3人の面倒を見なくてはならないのです。また日本は介護保険の制度上の問題で訪問介護でも介護士さんが何か目的をもって作業をしに来るケースが大半です。いわゆるコンパニオンシップ(話し相手など時間を共に過ごすサービス)を提供しているところもありますが、人材不足の折、かなり厳しい状況にあると理解しています。
私は当地で介護事業の会社を支援していますが、多くのクライアントさんは初めは週2回ぐらい1回2時間ぐらいでスタートします。恐る恐るというか、サービスそのものが未経験なのでやむを得ません。が、しばらくすると半数ぐらいのクライアントさんは必ず頻度も時間も伸びていくのです。もちろんクライアントさんの健康状態の悪化故のサービスの長時間化もありますが、おひとりでお住まいの方々にとって話し相手が欲しいのです。またそこに人がいると安心感もあるでしょう。そうすると一人のクライアントさんに対する訪問介護が介護士と一対一の関係から複数人といったチーム対応を要求されるのです。長時間サービスのクライアントさんだと6名体制でシフトを組むこともあるのです。そうするとスタッフは何人いても足りないという事態が生じるわけです。
私たちがグループホームを作ったのも一つには訪問介護では介護効率が上がらないからです。グループホームなら介護士1人で3人ぐらい介護できるのですがこれはビジネス上の効率化という観点ではなく不足する人材に対応する措置なのです。
いわゆるベービーブーマーの方々は70台後半に差し掛かり、これから5年ぐらいのうちに介護を必要とする方がぐっと増えます。日本の健康寿命は男性72.6歳、女性75.5歳です。健康寿命とは心身ともに健康で自立した生活ができる人を指します。割と低いなという印象があります。
一方、寿命を表す統計は平均、中央値、最頻値の3つがあります。(中央値はデータを並べた時の真ん中、最頻値はデータの中で最も多い値です。)最頻値で見ると男性は88歳、女性93歳と出ます。健康寿命と寿命の最頻値の差で見ると男性15年、女性17年もあるのです。その間、何らかのテイクケアが必要になる可能性が高くなるということです。更にご夫婦で考えた場合、男女の差は単純で5年の差がありますが、昔は男性の方が女性より数歳年上のケースが多かったので実質7-10年程度は女性のおひとり様ライフが待っている公算があると読み取ることもできるのです。更に言えば、困ったことに認知症になるケースは女性の方が多いのです。(ひとくくりにできませんが、80歳代前半で2割の差があります。)
もっと言いましょうか?一人っ子世代が今後主流になり、親の面倒を見られない人も当然出てくるのです。その時、介護士が不足していればご本人もご家族も生活すべてのリズム狂ってしまうのです。その手の本は何冊も読みましたが、実録話を読めば泣けてくるようなケースばかりです。
私は配管工より介護士と申し上げます。社会を支えられなくなるのです。そしてロボット介護士とかAI技術と言いますが、それは施設の一部の作業に留まるのです。実態はほとんどが人間と人間同士のふれあいです。
AIで仕事が無くなるかもしれないと申し上げましたが、無くなるというよりミスマッチに近いのだっと思います。世の中、残念ながら美しい仕事ばかりではないのです。
では今日はこのぐらいで。
編集部より:この記事は岡本裕明氏のブログ「外から見る日本、見られる日本人」2025年6月8日の記事より転載させていただきました。