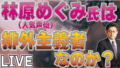黒坂岳央です。
ChatGPTが数秒で要約を示し、業務フローを自動化する時代になった。OpenAIのo3はIQ130超えですでに多くの人の知性を上回っている。そして恐ろしいことにこれはまだ序章に過ぎず、これからその進化は加速することが確実視されているのだ。
このような時代において、旧来の知性の象徴であった暗記力や学歴だけでは優位に立つことは難しい。誰もがAIを使う前提に立ち、「AIありき」で戦略的に動き、他者に優位性をつけられる人こそが「頭がいい優秀な人」と評価される時代となる。
これからの時代、頭のいい人の特徴はAIの変化でどう変化するのか?

ConceptCafe/iStock
1. 質問力
これは生成AI黎明期の頃から言われ続けていることだが、「問い」こそが最良の答えを引き出す分岐点となる。
かつてはまるで呪文のようなプロンプトを入力する「職人」がいた。今では過去の応対履歴まで参照し、こちらのクセやニーズを理解した上で対応するように変化した。その結果、昔ほどテクニカルに質問の必要はなくなったのだ。しかし、依然として問いの質が解の質を決める「決定的要素」であることは疑いようがない。
たとえば自社サービスの売上低迷の原因を「広告費の最適配分は?」と抽象的に雑投げするのではなく、「離脱顧客が最後に接触したタッチポイントは?」と掘り下げてAIに分析させる。これはそもそも広告ビジネスにおけるユーザーの動線を理解した上で問いを立てる必要があることを意味する。
さらに、AI時代の質問力において重要なのは、「初めから答えを前提とした問い」を避けることである。多くの人は、自らの仮説や思い込みに基づいた思い込みの強い質問をしがちだ。
しかしその場合、AIはその前提に沿った“想定内の回答”しか返せない。真に賢明な問いとは、事象を一方的に解釈するのではなく、現象の「症状」そのものを具体的に提示し、AIに広い探索空間を与える問いである。
たとえると医者に「風邪を引いたのでこの漢方薬を飲んでも大丈夫ですか?」と聞くようなものだ。そうなればYesかNoでしか返ってこない。そうではなく、「自分は今、体調がこのように悪い」と時期、体調変化、症状、熱、過去の症例などを医師に伝える方が良い回答を引き出せるのだ。
AIを真に使いこなす者とは、問いによってAIの可能性を最大化できる人間のことである。そして問いの力はAI抜きに「本質的知性」と言っていいだろう。
2. 人格とコミュ力
情報処理やデータは完全にAIに主権が渡った。これはAIにアクセスできる人のこの分野のスキルは差がつきにくくなったことを意味する。
そうなれば、人間関係においての付加価値は「人格やコミュニケーション力」ということになる。そしてこれはコンピュータが出せない付加価値だ。
たとえば商品サービスを購入する時、人は常に「スペックだけ」で購買を決めているわけではいない。担当者の人となりやコミュニケーションを通じて信用し、そして「この人からなら買っても大丈夫」と意思決定をしている。
筆者も買い物をする時、ついてくれる担当者の対応が気持ちよければ、「この企業やお店にお金を落としたい」という気持ちになり、たくさん注文をしたくなるということはよくある。
また、直接金銭の授受を伴わなくともSNSは信用経済の数値化したものであり、間接的にビジネスや社会的信用につながる。AIがどれだけ優れていても、人となりや歩んできた過去の生き方、コミュニケーション力までは提供できない。今後は魅力的な人格やコミュ力は確実に「知性」としてカウントするべき要素になりえるだろう。
3. 変化対応力
これまでも「生き残るのは変化に対応したものだけだ」という本質があったが、これからはそれがますます顕著に、そして極めてスピーディーになる。
既存産業の破壊と新たなる創造の連続が想定されるこれからのAI時代において、レガシーにしがみつく生き方はマイナスだ。大企業にしがみついても母体ごと消えてしまえば自分も一緒に沈んでしまう。
そのような変化の早い時代においては、AI由来の新たなビジネスチャンスに乗る気概のある人こそが強い。「これまでこの仕事や分野でやってきたから」というサンクコストバイアスをはねのけ、新しい時代には不要となった不要なスキルや知識、思い込みをアンラーニングをして必要なことをオンデマンドで学ぶバイタリティが必要になる。
筆者も現在進行系でまったく未経験の新しい仕事にチャレンジしている。知識ゼロ、経験ゼロからの出発だがそんなことは関係がない。マーケットは個人の事情など無視して動く。常に変化する市場に求められることをやり続けるだけだ。
4. アジリティ
アジリティとは、「素早さ、軽快さ」という意味だ。ここでは「ただ速い」という物理的速度をいっているのではなく、行動力という概念的速度も含めての速さを示している。
たとえば、これまでは1つの商品サービスを市場に投入するまで膨大なコストと時間をかけていた。しかし、今は違う。生成AIでプロトタイプを数日で作り、市場にテスト投入。外れたらやり直し、当たったらそれを育てるという高速PDCAを回していく。
これまでの時代は「ミス=コスト」だったが、試行回数をAIが代わりに稼いでくれるようになったことで、他者との差は「行動の質」以上に「行動の量」が決定的になる。つまり「やらないと損」なのだ。
もちろん、ある程度の質がなければ話にはならないが、粗はAIがカバーする。筆者も成果物はパパッと作って細かい修正はAIがカバーするやり方に変えてから生産性は倍以上早くなった。これからの時代、ミスを恐れる期間はそのまま巨大な機会損失になると考えるべきだ。
5. AIを味方と考える
これまでの人類の歴史とは破壊と創造の連続だった。AIに限らず、新たなる世界は脅威と敵視で迎える人、その逆に好機と捉える人にわかれていた。いうまでもなく、優位性があるのは後者である。
「AI=敵」という被害者意識を手放し、ツールとして人生やビジネス全体としての設計図を描けるかが問われている。
・PCを敵視してFAXを使い続ける。
・スマホを敵視してガラケーを使い続ける。
今どき、こんなことを言えば愚かだと言われるが、5年先、10年先に「AIは敵」などいえば知性を疑われる時代を我々は生きている。上手に使えばこれほど便利になるものはないからだ。
知性とは所与の条件ではなく、態度から生まれるのだ。
◇
AI時代の「頭の良さ」は、データを暗記する力ではなく、AIと協働しながら創造性・共感力・行動力を爆発させる総合スキルだ。変化を恐れず問いを磨き、AIを使いこなすことで、次の価値創造の主人公になるのは自分自身である。
■最新刊絶賛発売中!





![[黒坂 岳央]のスキマ時間・1万円で始められる リスクをとらない起業術 (大和出版)](https://agora-web.jp/cms/wp-content/uploads/2024/05/1715575859-51zzwL9rOOL.jpg)