
一見むちゃくちゃなトランプの高関税政策を支える思想として、「改革保守」という語を耳にすることが増えている。Reformoconの訳語なのだが、4月にご一緒したTV番組でも先崎彰容さんが、時間をとって詳説していたのが印象的だった。
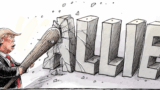
ただ日本語の「改革」には平成期に(まさに保守派によって)多用された、グローバルな市場での競争にすべてを委ねる新自由主義的な含意が強く、トランプ流の保護貿易とは真逆だ。なので、訳は工夫した方がよい。
英国で台頭する右派政党のReform UKを、そのままカタカナ書きするように、「リフォーム主義」と直訳した方がニュアンスが伝わるように思う。代表的な識者であるオレン・キャスは、会田弘継氏の取材に応えて、自らの現状認識をこう語る。

キャス 若者たちを無為に海外に送った対テロ戦争は失敗し、共産主義の中国にまで自由貿易を拡大したことで米国の雇用も奪われた。財政赤字を積み上げてまで減税策を続けた結果、足元の米国の地域社会と家庭は犠牲にされてしまった。
(中 略)
教育水準の低い中高年、特に白人の平均寿命が自殺や薬物・アルコール乱用などで急激に低下している……。これに匹敵するような現象は、ソ連崩壊後のロシアにおけるアルコール乱用での死亡率増加だ。国家破綻による現象だといえる。
強調は引用者
(初出は『中央公論』2025年6月号)
キャスは、ヴァンス副大統領とルビオ国務長官がともに頼るブレーンで、とくにヴァンスが「若者たちを無為に海外に送った対テロ戦争」に従軍したことは、大ヒットした有名な自伝で知られる。そうした人が、冷戦に「勝った」はずのアメリカを「負けた」ソ連になぞらえるとは、歴史の転換も来るところまで来た感がある。

冷戦終焉後に「調子に乗りすぎた」アメリカの保守派が、謙虚になるのは結構なことだが、しかし統計上の貿易赤字を減らすだけでなく、個人の健康や生き方まで俺らは改善できると公言する姿には、また別の傲慢さを感じて不気味である。
厳密には和製英語らしいけど、日本人がリフォームと聞いて連想するのは、ボロ家をピカピカに改修する工事である(原語のReformは、むしろ精神的な「改心」に近い)。似たノリで、住み始めのクリーンな住宅を再現するように、老衰した国家も青春期と同じ状態に戻す「社会改造」が可能だと、トランプ政権の幹部は信じているようだ。
1998年の有名なこの映画は、そうした社会的な回春欲求のグロテスクさをパロディとして描いたけど、政治家がベタにそれをめざして、強権を振るうのはぞっとしない。逆にいうとそこまで、アメリカという国は追い込まれているのだろう。
しかし日本にも、社会の隅々まで「設計図通りに改造できる!」と信じられた時代があった。首相候補の田中角栄が出してベストセラーになった、『日本列島改造論』(1972年6月)がそれである。
かねてご紹介してきた『潮』誌の読書座談会が完結し、発売中の7月号では開沼博さんの提案で、角栄の同書の今日性について議論した(参加者は他に、岩間陽子・佐々木俊尚・東畑開人の各氏)。
一般には角栄というと、規制政策による衰退する地方への再分配といった、まさしくReformoconのイメージで語られるが、著書のトーンは意外と違う。ぼくの発言から引くと――
平成末に地方衰退を止める鍵として「車の自動運転」を求める議論が流行りますが、しかし角栄は本書で、むしろ都市生活をそれで優雅にしようと書いている。テクノロジーへの期待も実は、昭和より寂しくなっている。
今回再訪しても、国土の均衡を説く角栄の筆致には、地方を救えというより「都心の過密がヤバすぎて、今のままはイヤでしょ?」というトーンが強いですよね。
58頁
そうなのだ。当時の日本は高度成長を爆走し(ただし、ピークアウトには達していた)、財源は無尽蔵にあるという自信が、「なんでも自由に改造できる」と思わせていた。ここは、国家予算を組むのに毎年苦労する、いまの米国とはまるで異なる。
しかし、その自信満々な角栄は、首相として満を持した解散総選挙にあっさり敗れてしまう(72年12月)。この点は、既成政党が提供する選択肢が国民に飽きられ、現状否定の気分と多党化への欲求を呼ぶ、今日の日米の現状にけっこう近い。
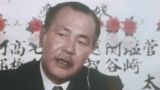
2021年に『平成史』でも書いたとおり、平成の終わりに「角栄なら現状を打破できる」的な再評価のブームはあったけど、ガチンコでもう一度「社会を改造して黄金時代を取り戻せ!」とまで唱える政治家は、そこまで見ない。なぜそうした、和製トランプは出てこないのか。
『潮』の座談会では、こんな風に分析した。
力ずくで「再び偉大な国家を!」と夢を押しつけると、トランプやプーチンのような強権政治になる。よくも悪くも、日本は今のところ逆ですね。
むしろ消費税の減税や「手取りを増やす」のように、一人ずつバラバラに財布を膨らませて、「全員で夢を見よう」みたいに暑苦しいことは言わない。そうしたポピュリズムは平和な半面、国民が互いに関心を持たず、ケアし合わない究極の個人主義にもなります。
63頁
個人の自由を最優先にする国の典型とされてきたアメリカが、国の強権を振りかざしてでも「家族や共同体を復興せよ!」と叫び出す半面、集団主義と伝統志向がこれまで強かった日本人の方が、かえって「そんなことより俺にカネを!」としか言わなくなっている。
戦後の80年、とくに冷戦後の35年ほどを通じて、日米の社会はそれぞれ、既存のセルフ・イメージとは正反対の場所まで来た。そう確認する上で、古典に親しみ、歴史を振り返るのは役に立つ。

『潮』の読書会は、今回でいったん幕となるが(来月の号に、クロージングの原稿も載る予定)、それに相応しいアクチュアルな議論になったと思う。ぜひ選挙の夏をいま前にして、多くの人が考える機会になれば幸いです!
参考記事:



(ヘッダーは、2023年末のNHKの番組より)
編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年6月12日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。













