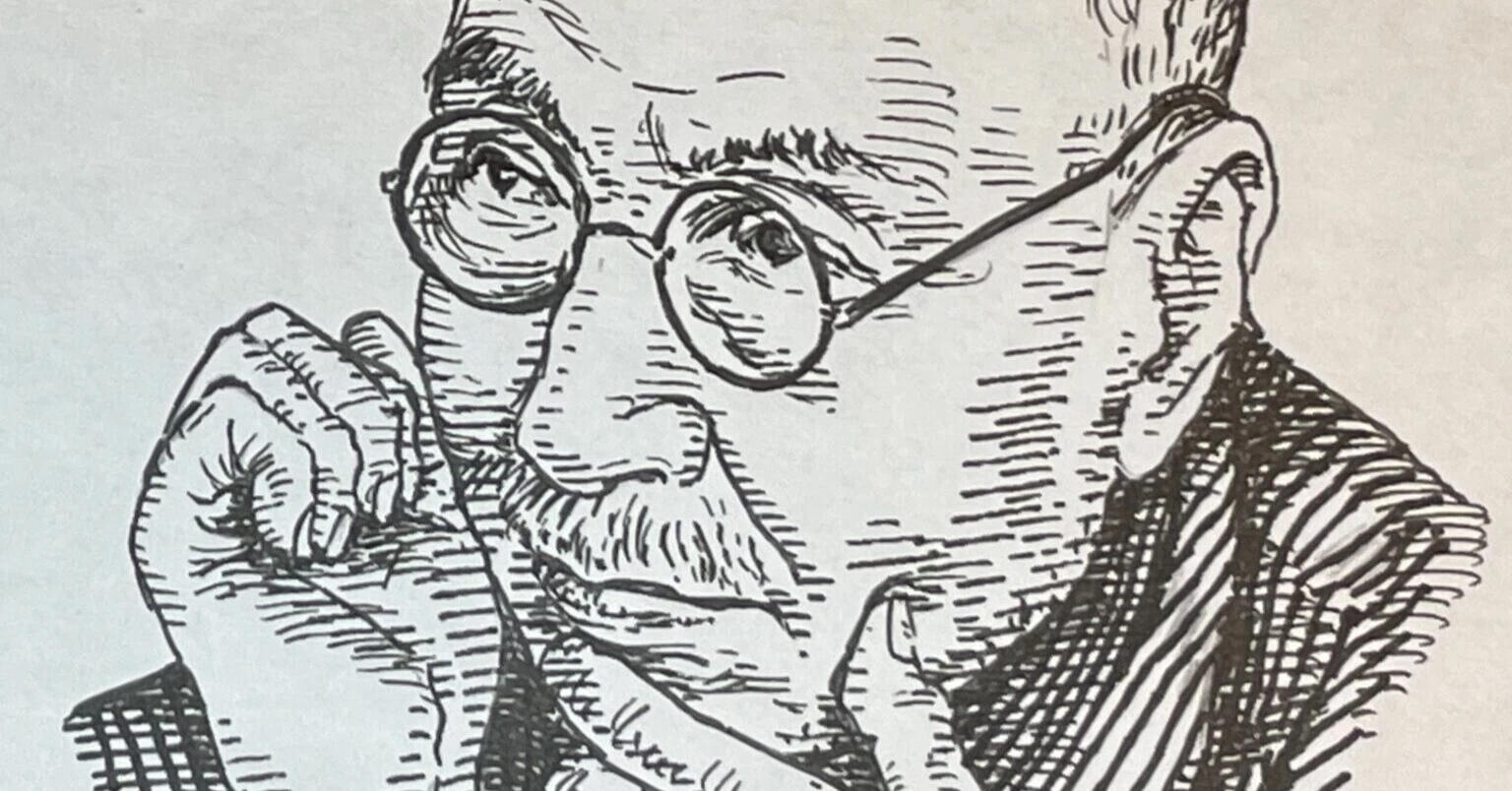
教養動画サービス・テンミニッツTVにて、新しい講義の配信が始まりました! ずばり、タイトルは「AI時代に甦る文芸評論 江藤淳と加藤典洋」。

先日はヴァンス副大統領ら、トランプ周辺の反知性主義を理解するために「夏目漱石を読もう」とお話しさせていただいたのですが、今回はむしろイーロン・マスク対策。これはもう今日の世界を生きる上で、見ないことはあり得ないレベルに必聴の授業ですよね(笑)。

いま増刷中の新刊『江藤淳と加藤典洋』のPRも兼ねつつ、同書には収めなかったふたりの業績を通じて、AI時代に求められる「ほんとうの知性」を考える内容です。なので、Wで触れていただいても、損しません。約束します。
うち加藤さんの事績を扱う部分は、5月に頭出ししたことがありますので、今回は「AI時代の江藤淳」について、講義で採り上げるテキストとともに、中身をチラ見せしましょう。
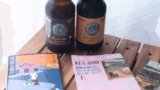
江藤淳が最も愛した日本の作家は、むろん夏目漱石ですが、同じくらい好きだった人に、俳人の高浜虚子がいます。正岡子規の後継者で、そもそも漱石が最初の小説『吾輩は猫である』を載せたのも、1897年から子規・虚子が始めた文芸誌『ホトトギス』の誌上でした(1905年)。
それで、江藤は自分のベストと認める評論「リアリズムの源流」(1971年)に、1904年に虚子が書いた「写生趣味と空想趣味」という論考を、絶賛しつつ引用します。虚子が、師である子規との口論を記録した文章ですが、書かれている事件は1895年頃のエピソード。
子規と虚子が茶店で休息中、夕暮れ時に夕顔の花が咲くのが目に入った。それをどう俳句に詠むべきかで、ふたりの意見が食い違います。
通行の字体に改めつつ、別の記事でもご紹介した「リアリズムの源流」から、重引で抄録すると、

その時子規子の説に、「夕顔の花というものの感じは今までは源氏その他から来ておる歴史的の感じのみであって、俳句を作る場合にも空想的の句のみを作っておった。今親しくこの夕顔の花を見ると以前の空想的の感じは全く消え去りて、新たらしい写生的の趣味が独り頭を支配するようになる」と。
(中 略)
そこで余は大に子規子に反対せずにはおられなかった。それは、夕顔の花そのものに対する空想的の感じを一掃し去るという事は、せっかく古人がこの花に対して附与してくれた種々の趣味ある連想を破却するもので、たとえて見ると名所旧蹟等から空想的の感じを除き去るのと同じようなものである。名所旧蹟は一半の美はその山水即ち写生的趣味の上にあるが、一半の美は歴史的連想即ち空想的趣味の上にある。……全く空想的趣味を除き去るという事は花の一半の美を削ぎ去るもので、また名所旧蹟から歴史的連想を除去するのと何の異るところもない、というような事を繰りかえして論じた。
しかし子規子の結論はこうであった。「それは仕方がない。写生趣味の上に立脚する以上は、自然の結果として空想趣味を排斥せねばならぬようになる。一方では甚だ殺風景な感じがするが、その代り一方ではまだ古人の知らぬ新たらしい趣味を見出す事が出来るではないか。」しかし当時、余はこの論にどこまでも不平であった。
江藤淳『リアリズムの源流』28-9頁
強調と段落を改めたほか、
一部漢字をかなに開き、句読点を付与
師匠の子規は、自然科学のように「客観的」に見たものを写しとるのが写生であって、夕顔の花を見た際に「あぁ、『源氏物語』の夕顔を連想するなぁ」といった人文的な教養はこの際捨てろ、と言っている。そうすることで初めて、新しい時代にふさわしい表現が生まれる、というわけ。
対して虚子は、先生はまちがっている、歴史的な遺跡では風景のみでなく、過去にそこで起きた物事も含めて味わうように、人間として夕顔の花を見たときに自ずと湧く主観的な連想を捨てたら、俳句の表現は貧しくなる、と反論する。
まさに、人間でなくAIに観察させた方が「ファクトベースで公平な結論が出るんじゃないすかぁ?」と、いやいや、そんなうまく行くはずないだろ。これまで大事にしてきた価値観を失って、ふつうの人にとっては生きづらい社会になるだけだ、な今日の議論と同じですよね。構図としては。
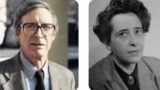
で、子規は「そんな犠牲はやむを得ない。俺たちは過去の常識に囚われないNew Normalに進むんだ!」と、AI加速主義みたいな答えを虚子に返したわけですが、江藤はこれを評していわく、
子規はいうまでもなく、偶像破壊的な革新家として極論しようとしていた。これに対して虚子は、この偶像破壊的革新家の、イデオローグとしての一面を衝いたのである。
同書、30頁
はい。そういうことです。俺は客観に徹して「空想を排している!」と主張する人ほど、人間が完全な客観に立てるとする空想に溺れていて、まぁ子規の場合はイデオローグとして「わかった上で」やってたんですけど、それをベタに信じちゃうと痛い目を見るわけです。

こちらの記事以来の登場。
信じたら大変なことになります
実は私、安直なAI未来主義を批判する上で、1950年に三島由紀夫が書いた『青の時代』をヒントにしたことがあります(『危機のいま古典をよむ』にも再録)。……なんだけど江藤さんの場合は、そこからさらに半世紀前の明治の挿話から、いまを考える手がかりになることを、抜粋して書き残しちゃうんだから、すごいですよね。

ここに、AI時代こそ必要になる「本物の人文知」があります。逆に、俺も研究にIT使ってるとか、AIで昔の写真に色塗ってもらえばレキシガクも最先端に絡める! みたいなニセモノの人文知は、誰も必要としません(笑)。
ホンモノの人文学は、時代の潮流を根底から疑うことで輝く。ニセモノの人文学は、折々のバズワードをつなげるだけだから、今後は生成AIに代わってもらえば、リストラで別にいい。
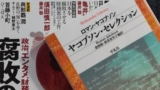
江藤と加藤という、戦後の文芸評論の頂点ふたりの知恵から、生成AIが大流行のいまを生き延びるモデルが見つかる。そんな最も「アクチュアル」な講義が、多くの方に届きますなら幸いです!
参考記事:


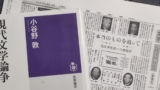
(ヘッダーはこちらの素材集から。文豪ぞろいで素敵です)
編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年6月26日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。













