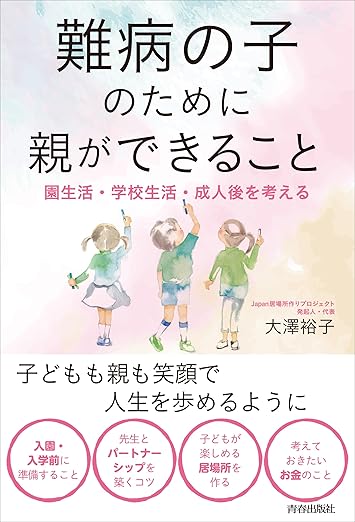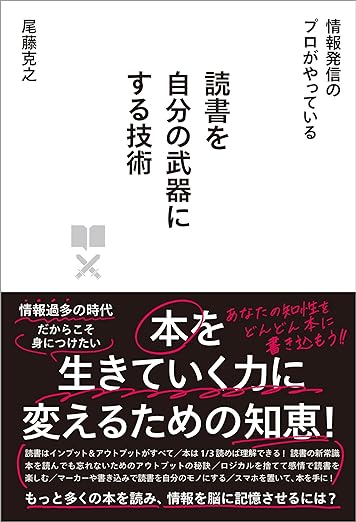FatCamera/iStock
障害や病気の診断を受けた子どもの保護者は、深い悲しみと不安に直面することがあります。しかし、適切な支援と情報があれば、子どもの可能性を最大限に引き出すことができます。
今回は「難病の子のために親ができること」(大澤裕子著、青春出版社)を参考に、障害のある子どもの教育選択と家族支援について考えてみたいと思います。
すべての子どもに教育を受ける権利がある
障害のある子どもの教育について考えるとき、その原点となる重要な理念があります。
1972年、米国のペンシルバニア州裁判所は「障害のいかんを問わず、すべての子どもはその能力に応じて教育を受ける権利を有する」(PARC判決)と宣言しました。これは、知的障害のある子どもたちが教育から排除されていた状況に対して下された画期的な判決でした。
この判決は世界中の障害児教育に大きな影響を与え、日本においても、すべての子どもが教育を受ける権利を持つという理念の確立につながりました。現在の日本の特別支援教育制度も、この「教育を受ける権利の保障」という考え方を基盤として発展してきたのです。
就学先選択のプロセス
発達障害や知的障害など、教育的支援が必要な子どもの就学先選択は、保護者にとって重要な決断です。地域の学校の通常学級で学ぶか、特別支援学級に籍を置くか、あるいは特別支援学校を選ぶか。この選択は、単に教育の場を決めるだけでなく、子どもの将来の社会参加への第一歩となります。
大澤さんは著書の中で、就学先について相談したい場合は、市町村の教育センターで行っている「就学相談」に申し込むことを勧めています。
就学相談では、保育園や幼稚園の先生、療育機関の意見と、本人・保護者の希望を考慮して最終的に就学先を判断していきます。特別支援学級は知的障害学級と自閉症・情緒障害学級に分かれており、通級指導では通常学級で学びながら必要な支援を受けることができます。
選択における心理的な課題
しかし、この就学先の選択の過程で保護者が直面するのは、社会に根強く残る「心の壁」です。家族や親戚から「地域の学校に入れるべきだ」「特別支援学校に入れるなんて」という声を聞き、傷つくケースもあります。
こうしたケースについて、大澤さんは著書で次のようにアドバイスしています。
「何が正解かではなく、よく考えて選択したことが正解だったと思えるようにしていく気持ちでいいと思います。違和感や、子どもにとって望ましいと思えない場合は、臆することなく環境を変えるのも一つの道です」
そして、
「学校選択は、親と子どもにとってかなり重要な決断。渦中にいる方は、悩むことでしょう。子どものためにあなたが出した結論は、尊重されるべきものです」
と述べています。
社会の「壁」を取り除くために
厚生労働省が公表した「令和6年障害者雇用状況」によると、2024年6月1日時点の民間企業における雇用障害者数は約67万7千人で、21年連続で過去最高を更新しました。雇用障害者数の内訳は、身体障害者が約36万9千人、知的障害者が約15万8千人、精神障害者が約15万1千人と、いずれも前年より増加しています。
この数字は希望を示す一方で、学校で適切な教育を受けた子どもたちが、卒業後に社会で活躍できる場がまだ限られていることも示しています。
心身に障害を持つ人が社会参加を果たすためには、さまざまな「壁」があります。物理的な壁や制度上の壁は、政治や行政の努力で取り除くことができます。学校のバリアフリー化や、事業者による合理的配慮の提供などは、その具体例です。
しかし、偏見や差別といった「心の壁」を取り除くためには、より長い時間と社会全体の意識改革が必要です。障害を持つ人が社会の一員として等しく尊重される「ノーマライゼーション」の実現には、教育現場から始まる地道な取り組みが欠かせません。
特別支援教育の選択に悩む多くの保護者は、実はこの大きな社会変革の一端を担っています。どのような選択をしても葛藤はあるでしょう。しかし、よく考えて選択したことが正解だったと思えるようにしていく、その積み重ねが、すべての子どもが尊重される社会への道筋となるのです。
子どもたちの教育から始まる社会参加への道のりは長く、課題も多いです。しかし、一人ひとりの選択と努力が、より良い共生社会の実現につながっていくことを信じて、歩みを進めていきたいものです。
困ったときは一人で抱え込まず、専門家や支援団体、同じ立場の保護者とつながることで、より良い道を見つけることができるでしょう。
尾藤 克之(コラムニスト・著述家)
■
22冊目の本を出版しました。
「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)