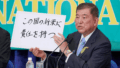Iryna Dobytchina/iStock
減税の議論が花盛りだけど、その裏で決まった防衛特別法人税
参議院議員選挙もあり、与野党入り乱れての減税、給付金合戦が繰り広げられています。
その一方で、実は、増税が、しれっと決まってたんですよ。それが、令和7年度税制改正で正式に決まった防衛特別法人税というものです。
ウクライナ・ロシア間での紛争だけでなく、中東での紛争もあり、アメリカも介入。
トランプ大統領は、NATO加盟国に、GDPの5%の防衛費支出を求めています。
日本の防衛費は、だいたいGDPの1%以内とされてきたものの、今後、台湾はどうなるのかということを踏まえると、自国の防衛について、日本だけはこのままでよいというわけにはいかなそうです。
そういう点では、防衛特別法人税の創設もやむを得ないことなのかもしれません。
ということで、今回は、令和8年度からの導入が決まっている防衛特別法人税について、今わかっていることをまとめておこうと思います。
防衛特別法人税の経緯
日本を取り巻く軍事・安全保障環境が一段と厳しさを増している現状。この状況に対応するため、日本の防衛力を抜本的に強化し、必要な水準の予算措置を講じる必要性から導入が決定されました。
令和5年度税制改正大綱において、防衛力強化に必要な追加支出約4兆円のうち、残りの1兆円を法人税・所得税・たばこ税の増税で賄う方針が示されました。
当初は所得税の増税も検討されていましたが、物価高に直面する国民への配慮から所得税の実施時期は引き続き検討とされ、法人税とたばこ税については令和7年度税制改正大綱で具体的に法制化が盛り込まれることになったのです。
防衛特別法人税の概要
導入時期
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用
防衛特別法人税の仕組み
(法人税額ー500万円)×4%相当の新たな付加税
これは既存の法人税に上乗せされる形で課税される税金です。
納税義務者は、各事業年度の所得に対して法人税を課される法人が対象となります。
しかし、中小企業に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から500万円が控除されます。
この基礎控除により、自民党の見込みでは、今回課税される法人は全体の6%〜7%程度であり、残りの9割以上の法人には影響がないと報じられています。
実質的には、法人所得800万円以下の所得部分が多い中小法人については、大半が課税されない結果となると見込まれています。
なお、防衛特別法人税が適用されるであろう法人の法人税の税率23.2%ですから、その4%を乗じると約0.928%となります。
もし課税対象となる場合には、その対象部分について、課税所得の1%弱の増税に相当することになります。
計算例で見る実際の負担額
ケース1:課税所得2,400万円の中小企業の場合
中小企業の場合、年800万円以下の所得は税率15%、それ以上の所得は税率23.2%が適用されます。
法人税額
= 800万円 × 15% + (2,400万円 - 800万円) × 23.2%
= 120万円 + 371.2万円 = 491.2万円
この基準法人税額491.2万円は、基礎控除額500万円を超えません。
したがって、防衛特別法人税額は0円となります。
ケース2:課税所得5,000万円の中小企業の場合
法人税額
= 800万円 × 15% + (5,000万円 - 800万円) × 23.2%
= 120万円 + 974.4万円 = 1,094.4万円
この基準法人税額1,094.4万円から基礎控除額500万円を差し引きます。
防衛特別法人税額
= (1,094.4万円 - 500万円) × 4%
= 594.4万円 × 4% = 約23.8万円
この場合、基準法人税額のうち500万円を超える金額に対して4%が課税されることになります。
税効果会計の実効税率に影響も
防衛特別法人税が「税効果会計」の計算にも影響を与える部分もあります。
税効果会計とは、会計と税務の認識の誤差を埋めるための調整措置のことです。
例えば、事業税のように、会計上は当期の費用にはなるものの、税務上は翌期の損金になるなど、タイミングにズレが生じるものがあります。
それをそのまま放置して決算書を記載すると、会計上の税引前当期純利益に対してやたらと当期の法人税が大きくなったり、少なくなったりすることで、正しい当期純利益を表示することができなくなってしまいます。
そこで、これらの会計上と税務上では、費用計上と損金算入のタイミングがずれるようなものについて、その法人税額相当額の加算減算することで、正しい当期純利益を表示しようというのが税効果会計です。
その際に用いる「実効税率」というものが、この防衛特別法人税導入により変更が必要になります。
たとえば、東京23区内の外形標準課税適用法人の場合、これまでの実効税率は30.62%に対し、防衛特別法人税が開始されたあとは31.52%となるとされているのです。
防衛特別法人税導入後の法定実効税率
= [法人税率 × (1 + 地方法人税率 + 住民税率 + 防衛特別法人税率) + 事業税率※] / (1 + 事業税率※)
※事業税率は特別法人事業税率を含む。
課税所得2,500万円以下の中小企業には関係ない
税効果会計をあえて適用する中小企業はそれほど多くなく、うちでも適用を求められるのは、上場子会社くらいです。
ですから、今回の防衛増税は、課税所得が約2,500万円以下の中小企業であれば、ほぼ無関係とは言えます。
しかし、課税所得約2,500万円を超える課税所得の法人については、その課税所得が2,500万円を超えた部分には、税率約1%分の法人税が増税がされるのだと思っておいてください。
まあ、今回は反発の少ない高所得法人向けだけの増税ですが、所得税については今も検討中であり、どこかのタイミングでしれっと増税はされるでしょうね。
編集部より:この記事は、税理士の吉澤大氏のブログ「あなたのファイナンス用心棒」(2025年7月3日エントリー)より転載させていただきました。