日本から来る若者の採用面接を一定の頻度で行っている中で気になることがあります。「なぜカナダに?」という質問に対して日本の勤め先への不満を口にする方がいらっしゃる点です。日本の多くの企業はガバナンス強化、社員のメンタルヘルスに注力しているというのが一般的な企業姿勢のはずですが、実態は企業側の対策と従業員側の温度差は埋まっていないようであります。
カナダに新天地を見つける、あるいは自分探しや居所探しを求めてやってくる方はまだ健全な意志を持っていると思います。実際にはほとんどの方が逃げにくい日本の社会の閉塞感の中でもがいているのかもしれません。
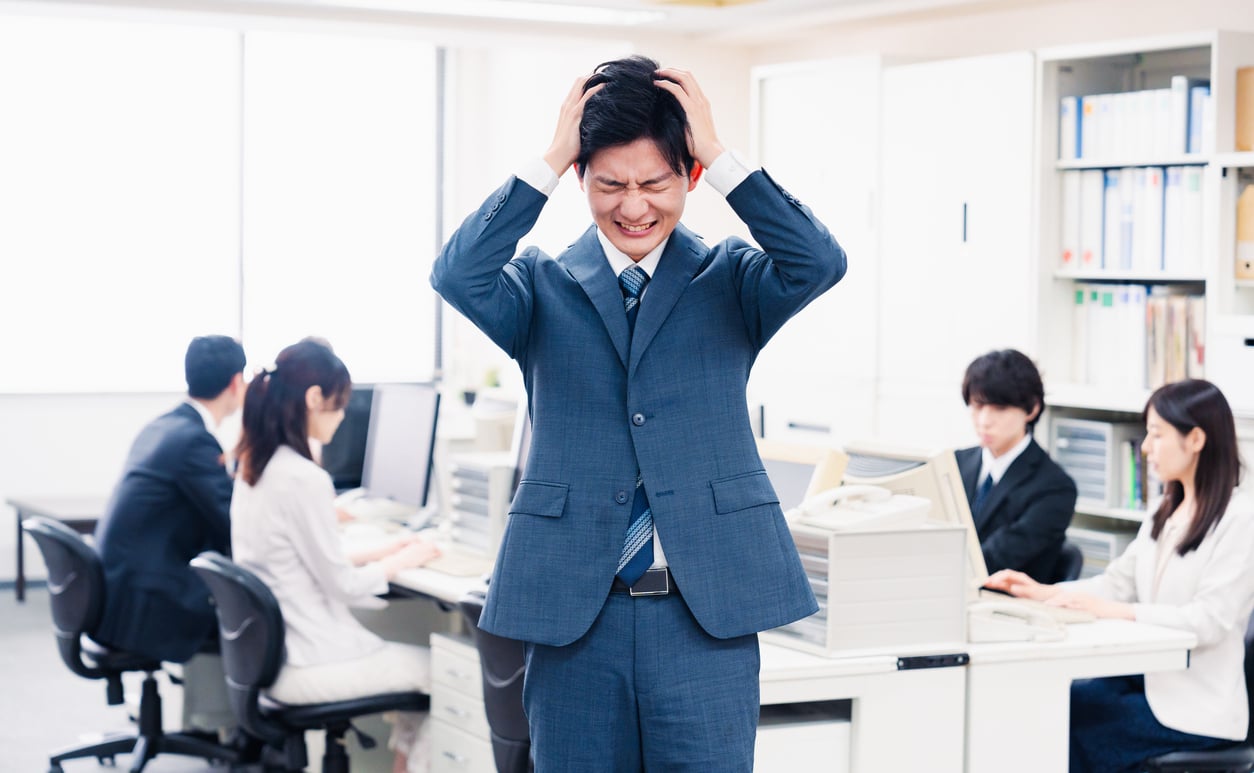
maroke/iStock
若者のメンタル問題、いったい何が理由なのでしょうか?チャットGPTに聞いてみたところ、以下の5つが出ていました。
1 若年発症の傾向 (若年者は脳の発達時期でありストレス耐性が十分ではないの意)
2 いじめや二次障害 (学校や発達障害が引き金となる精神疾患)
3 現代型うつ病 (若年者に強い傾向のある感情の抑え込みと他者への配慮)
4 社会的プレッシャーと孤独 (SNSと比較文化が将来への不安を煽る)
5 メンタルヘルス教育の不足 (家族や学校での早期発見や支援の遅れ)
なるほど、いかにも正しそうです。ただ、これだけ読んでも「ふーん」で終わってしまうのでもう少し自分の考えを掘り下げてみたいと思います。
私の周りには女性が圧倒的に多いので多少意見に偏りがあると思いますが、その点はお許しください。うつ病は男女の疾患比率でみると女性が男性の2倍あるそうで、それ以外に女性に多いのが不安症、摂食障害だそうです。一方、男性が抱えるのは自閉症や注意欠陥多動性障害、アルコール依存。
新入社員3年3割の退職率は昔から当たり前とされますが私の頃は仕事がつまらない、組織に同化できない、仕事について行けないという理由が主体でしたが、最近はミスマッチ、期待と相違した、キャリアパスが不十分が理由とされます。 つまりかつてはどちらかといえば自身の能力に退職原因があったものが近年は自身の期待と選択肢が間違っていた理由に変わってきています。責任所在の転嫁とも言えなくはないです。特にキャリアパスへの不満とは将来の昇進への失望というわけですが、入社してさほど経っていない若者が自分の10年、20年後の姿を想像してしまうところが私にとっては空想の域にすら感じるのです。
この傾向が強まった背景に「社会の同一化、均質化」の可能性を考えています。小学生のころからスマホが当たり前になったZ世代からアルファ世代への移行期である現代において多くの人が同じ情報を同じように読み、すべての事象がITデバイスを通じて誰でも瞬時に同じ答えを引き出すため、没個性化が起きているのが本質的背景ではないかと疑っています。
就活を終えた大学生はネットではわからない実社会のギトギトねっとりした世界を知らず、スマホから得られるキラキラした話に胸を躍らせているのです。ところが入社した途端に「違う!」というのは何時の時代でも同じですが、問題は現代人はスマホから得た均質な情報しか知らないため、メンタルの耐性がはるかに不足している可能性があるのです。
その上、企業はガバナンスと称してより細かい社内ルールを設定します。それらは一般的な企業行動規範や法律全般を元に各企業が業務に合わせて具現化した規定ですが、これがうざいわけです。言い方を変えると縄で手足を縛られ、お前の好きにはさせないぞ、というがんじがらめ状態を作るのです。
もう一つが組織内で調和がとれないことがあります。私の数々の採用面接歴でこれが退職の理由で一番多い点です。端的に言うと自分が所属する組織に嫌な奴が必ずいてその嫌な奴は避けても必ず、攻撃してくる(ように感じる)のです。語弊があるといけないのですが、大した攻撃はされていなくても本人はその一撃がとてつもなく衝撃的でメンタルの回復に時間がかかるというわけです。ここは個人差があり、先ほどのチャットGPTの理由につながる部分であります。
私どもで採用した若者(多くは女性)がカナダに求めるものは解放感であり、組織の呪縛から逃れることです。実際、私の直轄事業では超放任主義だし、他の部門でも自主性を重んじています。故に失敗も往々にしてあるのですが、我々は失敗しないような防御策ではなく、失敗した時、なぜ失敗し、どう回復させるかを学ばせる方針なのです。もちろんこのやり方は現代社会では異質かもしれませんが、皆さんがのびのび仕事をし、生活されてるのが何よりだと思っています。
メンタル問題は海外でも同様に増えています。結局、それは我々のコミュニケーション相手が割と限定されているのが背景ではないかと仮説を立てています。皆さんの業務や私生活においてお付き合いある人は思った以上に限られているはずです。そして最大のポイントは嫌な奴は自分がプライベートでコミュニケーションする中にはいないのです。同様にバーチャルな世界、つまりネット上でのコミュニケーションに励むZ世代やアルファ世代はフレキシビリティが少なく閉塞された社会に自らの居場所を求める傾向があり、故に「井の中の蛙」となりやすいと考えています。彼らがカナダに来て全く生活環境が変わった時、まるで浦島太郎のように目覚める方もいらっしゃるのです。
お前はITやAIが社会の閉塞感をより強め、人間の精神力が弱まると言いたいのだろう、とおっしゃるでしょう。それは疑えると思っています。以前にも申し上げましたが人間は長い時間をかけてようやく今のレベルに達したのですが、科学技術の飛躍的発展に人間のメンタルが追い付いていないギャップの認識は重要だと思います。その差こそ、現代が抱える問題であろうと察します。
では今日はこのぐらいで。
編集部より:この記事は岡本裕明氏のブログ「外から見る日本、見られる日本人」2025年7月6日の記事より転載させていただきました。













