アゴラでは日々多くの記事を配信しており、忙しい方にはすべてを追うのは難しいかもしれません。そこで、今週の特に話題となった記事や、注目された記事を厳選してご紹介します。
政治や社会保障を中心に、国際情勢やビジネス、文化に至るまで多岐にわたる内容を網羅。各記事のハイライトを通じて、最新のトピックを一緒に深掘りしましょう!
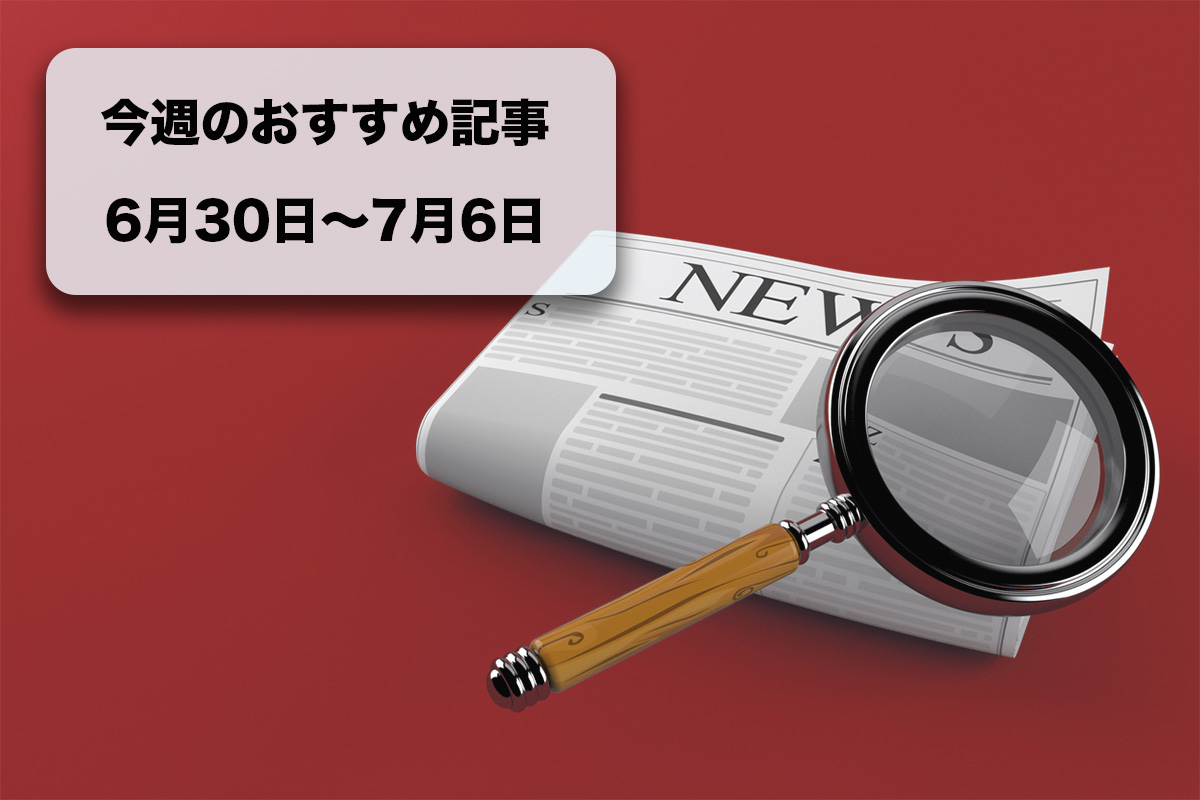
政治・経済・社会保障
複数調査で参政党の支持率が5〜8%に急上昇し、国民民主に肩を並べています。既成政党への不満や物価高への危機感から、特に若年〜中堅層の無党派層を中心に草の根支持が広がっています。ただし、一部では誤情報や過激発言への懸念も示されています。
参政党の支持率が急浮上し国民民主と並ぶ:現役世代は政治になにを望む?(アゴラ編集部)

■
東京都が1969年に導入した「老人医療費無料化」は全国に広まりましたが、社会保障費の爆増や財政赤字を招き、現役世代への重い負担が固定化されました。著者は、この“善意”の再考を提案し、社会保険料や給付の見直しで制度の持続可能性を確保するべきだと論じています。
地獄への道は「福祉」と善意で舗装されている:無料医療が残したツケ(音喜多 駿)

■
国民年金保険料を税金負担へ転換し、国庫負担率を現在の50%から75%へ引き上げる案を提案しています。これにより保険料(年額20万円→10万円相当)が半減し、消費税増分で財源を確保しつつ、生活保護や雇用保険と医療扶助を整理統合することで、社会保障費を効率的に削減するという具体策です。
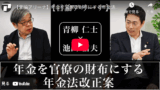
■
日本維新の会が掲げる「医療費を年間4兆円削減し、社会保険料を現役世代1人あたり年6万円引き下げる」という公約について、削減可能なのは主にOTC類似薬除外と病床削減の2兆円分であり、実際の削減見込みは約3兆円前後と分析されています。追加策や目標修正が不可欠で、制度運用・財源確保の観点から実現には多くのハードルがあると説かれています。
維新公約の「医療費4兆円削減で社会保険料を6万円安くする」を精査する(永江 一石)
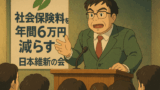
■
蓮舫氏は都知事選後「国政には戻らない」と明言していたにもかかわらず、1年足らずで参院選比例代表へ再出馬を表明しました。自身の発言の矛盾に対し有権者や立民党内から不信の声もあり、「政治家としての信念と責任」が問われています。
渡り鳥になって優しくなれるはずの蓮舫氏、他の立民候補には優しくなれず(アゴラ編集部)

■
自民・立民・維新の主要政治家(石破・野田・前原)が“石野前連合”を形成し、政党が責任ある体を失いつつあると強く批判しています。党首討論は空虚で、NATO総会出席回避や年収制限見送りの協力姿勢など政治家の無責任ぶりが「最悪の体制」へとつながると訴えています。
「石野前連合」という悪夢:劣化政党の末に来る最悪の無責任体制(澤田 哲生)

■
日本の医療保険制度では年齢が上がるほど窓口負担が軽くなり、多く医療を使う高齢者に不公平が生じていると指摘しています。保険本来の「万が一」に備える機能へ戻すため、一律3割負担の再導入を提案しています。
世界で異例、年齢で負担が軽くなる日本の医療保険を正す(音喜多 駿)

■
参院選が7月3日に公示され、与党は給付金、野党は消費減税を掲げています。どちらも「物価対策」を謳うものの、実際は追加給付や減税で可処分所得を増やし消費を刺激し、結果的には物価を押し上げやすいと解説。目に見える支持策ばかりが選挙公約になっている背景やその矛盾に注意を促しています。
与野党とも物価を上げる政策ばかり公約するのはなぜ?(池田 信夫)

今週のVlogです。
国際・エネルギー
石破首相がNATO首脳会議に外相のみ派遣した判断について、日本が非加盟国にもかかわらず過度にNATOを重視する現状に疑問を提示しています。欧州安全保障との関連を冷静に再考し、外交と防衛のバランスある議論の重要性を訴えています。

■
赤沢経済再生担当大臣は、4月以降7回にわたって米国へ直接交渉に赴いたものの、トランプ政権に「相手にされず」苦戦しています。焦点は自動車25%関税の容認、自動車産業・財務省の対応、参院選への影響で、勝敗の帰趨が政権の命運を左右するとの見方が示されています。
日米関税交渉が不調になったらどうなるか?:相手にしてもらえない赤沢大臣(岡本 裕明)

■
宥和政策(譲歩外交)はミュンヘン会談以降、悪印象で語られがちだが、歴史上イギリスが合理的妥協で長期的平和を維持した手法でもあったと指摘しています。現代の国際関係理論では「恐怖からのスパイラル」の場合に宥和が有効とし、ウクライナ危機への反省を踏まえて、「宥和」の正しい使い方を再考する必要性を訴えています。

■
政府の脱炭素政策により、再エネ導入や火力抑制が進めば、家庭用電気料金は2040年に36円/kWhまで上昇し、ウクライナ戦争時と同水準になります。省エネや蓄電の補助にも限界があり、負担増の可能性が高まっています。
脱炭素政策はウクライナ戦争時の電気料金暴騰の再来になる(杉山 大志)

■
杉山大志氏と宮崎正弘氏の書籍を通して、気候変動や脱炭素、ポリコレといった「正義」が人々の常識と直感を奪い、批判的思考力を失わせると指摘しています。真の“常識”を取り戻すために、固定観念に挑む姿勢が必要だと訴えています。
あなたの常識を奪う「正義」と戦え! 常識を考えるための2冊(川口 マーン 惠美)

■
「再エネ100%の日」の報道は、ゴールデンウィーク中の東北電力管内で一時的に需給がほぼ一致した数日を過度に強調したものです。実際には出力制御や蓄電未整備などで真の100%は達成されず、「虚構的表現」としての見直しが求められています。

ビジネス・IT・メディア
攻撃的な相手には、相手ではなく周囲の“観客”の印象を優先し、品性ある対応で冷静に交わすことが重要です。感情に乗らず、相手に合わせないことで、相手が自滅し自身の印象を守れると論じています。

■
パーソル総研の調査で、従業員300人以上の企業の約4割が50~60代社員を「人材過剰」と認識していることが明らかになりました。年齢を理由に処遇を見直され、意欲や生産性が低下する悪循環も浮き彫りです。企業は高齢社員の能力を見極め、適材適所の配置と待遇改善が求められています。
空前の人手不足なのに50〜60代は「人材過剰」の現実(アゴラ編集部)

■
職場で高く評価される人には実力・成果だけでなく「誠実さ」「信頼関係」「適応力」が備わっていると説明されています。約束を守り相手を尊重し、変化に柔軟に対応できることが、長期的に信頼される評価につながるとしています。

■
現代はパワハラ回避で注意が減り、間違いに気づけないまま「モンスター化」する人々が増えていると論じています。組織や社会の中で適切に指摘される“強制力”の重要性を訴え、AIも自身の改善ツールとして活用する意識改革を提案しています。
「誰も注意しない社会」でモンスター化する人たち(黒坂 岳央)

■
体調不良などで会社を休む際、「欠勤」は労働契約違反に該当し、会社は必ずしも許可する義務はないですが、安全配慮義務の観点から病欠は認めるべきと解説しています。また、欠勤控除・有給振替・懲戒処分の仕組みやルール整備の重要性についても丁寧に説明しています。
体調不良で欠勤。これって労働契約違反なの?(桐生 由紀)(シェアーズカフェ)

科学・文化・社会・一般
パリの名門ホテル「リッツ・パリ」の中庭に設けられた期間限定バーでは、草花をテーマにした7種の涼やかなカクテルと、備長炭焼きシーフードなどのグルメを楽しめます。緑に囲まれた優雅な空間での夏のアペリティフ体験が魅力です。8月初旬までの開催です。
ラグジュアリーな夏時間:リッツ・パリが贈る庭園の極上カクテル体験(加納 雪乃)

■
2025年6月11日に日本学術会議の法人化法案が成立し、議論の中心だった任命拒否問題は4年半ぶりに区切りを迎えました。学者らの抗議が自己正当化のためのパフォーマンスであり、世論支持を失ったと喝破。今後は「責任ある学問」や学術会議の真の再生に向けた検証が必要だと訴えています。

■
障害や発達障害のある子どもを育てる家庭は、通常学級・特別支援学級・支援学校など教育の選択肢に直面します。市町村の就学相談で支援を受けながら、最適な環境を選ぶことが重要です。社会的バリアを軽減するには、制度だけでなく偏見を取り除く意識改革も必要であると論じています。
障害のある子どもを育てる家族への支援と教育の選択(尾藤 克之)

■
文部科学省は、2030年度から次期学習指導要領で「主体的に学習に取り組む態度」を成績評定から外し、通知表の所見欄で記述する形式に変更します。これにより、非出席児童や発言が少ない生徒が内申点で不利にならず、教員の主観評価のばらつきを軽減する狙いです。一方で、主体性を数値化しないことで内面の育成が軽視される懸念や、現行の内申点重視の選抜制度自体の見直しも求められています。
小中高の成績から「主体性」評価が外れる:先生は生徒の内面を評価できるのか?(アゴラ編集部)














