
読まれた方は気づいたと思うが、5月に出した『江藤淳と加藤典洋』は「実を言うと、わたしなりのフェミニスト批評の企て」なのだった(317頁)。それについては、上野千鶴子さんとの対談でもダメを押している。
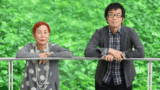
與那覇 批評家を自称する人も含めて、過去との接し方が悪い意味で「検索エンジン化」していると思うのです。江藤淳で言えば、WGIPへの批判が行き過ぎて陰謀論になったり、私生活では奥さんを殴った挿話もあったり、そこだけ「切り取り」すれば悪者に見える要素はいっぱいある。
しかしそれは「いま」の基準を自明視しつつ、マウントを取りやすい過去に「当たり屋」をしかけているだけで。……江藤に寄り添って読んだら、即ちフェミニズムに反する行為だといった、安易な風潮にはノーを言わないとな、と。
上野 妻を殴った男だから業績を評価しない、なんてことはぜんぜんないですよ。私がフェミニスト “なのに” 江藤を評価していると批判される理由はまったくない。
『文學界』2025年7月号、104頁
(強調を付与)
この「悪者に見える要素」が、曲者だ。Google検索のように文字面=目に見えるうわべの表記だけをひろって、アリ/ナシ、味方/敵の判定を下し、見えない文脈は無視するあり方は、いわば言葉のルッキズムと呼ぶべき事態である。
今回、美術誌『Art Collectors’』の9月号が「現代の女性」像の特集を組むということで、ルッキズムに関し寄稿させてもらった。タイトルは「視覚過敏という文明病の、これまでとこれから」。
「フェミニスト批評」をも企てる戦後批評の正嫡であるから、ルッキズム悪いっすよね~でオワリみたいな、安直な議論はしない。実効性のある解決策をも提示しているので、行ってみよう。

ペーパーテストの点数が低いのに、見た目がよいからと大学に合格させるのは、ルッキズムである。「学力」を問うべき場面で、容姿を優先しているからだ。しかし最初から「容姿」を問うている仕事に、ルッキズムの概念をあてはめて批判するのは、用語の使いすぎなのだ。
もちろん「容姿を問う仕事」なるもの自体があってはいけない、とする立場もありうる。ではどうするか。イスラム原理主義の国のように、女性全員にブルカをかぶせれば、見た目で女性が差別されることはなくなるが、もっと大きな差別が生まれる。
あるいはこの際、むしろ男性にかぶせてみるか。女性の権利の伸長を示すとともに、「弱者男性」にもワンチャン選ばれるチャンスを与える、一挙両得の策である。むろん完全な平等をめざすなら、男女双方にかぶせることが望ましい。
48頁
いやぁ、まさにフェミニスト批評である。というか、弱者男性や職業差別の問題もちゃんと扱ってるから、インター・セクショナリティーでもある。もはや死角なしの、カミ(神)ニスト批評かもしれないとさえ思う。

大事なのは、これがネタで済まないことだ。引用を続けると――
気づいてほしいのは、これがジョークでない世界が、生まれていることだ。それも中東やアフガニスタンではなく、日本に住むあなたの、すぐそばに。
多くのSNSでは、アイコンに自分の顔を使う義務はない。リアルで誰とも「対面」せず、仕事も娯楽もすべてSNS経由で享受することにすれば、全員がブルカ着用で暮らしているのと同じことになる。
ところがルッキズムはしぶとい。ようやく「顔で評価される」不自由を免れたと思ったら、今度はフォロワーや「いいね」の数での査定が待っている。

2021年8月のAFP通信より
(撮影は17年4月、パキスタンにて)
ここに、オンライン社会の罠があった。動画配信ならまぁ聴覚も入るとはいえ、ネットでつながるかぎり嗅覚・味覚・触覚は遮断され、五感のうち視覚で捉える情報に対してのみ、突出して過敏な人間が作られてしまう。
こうなるとテキストにブルカをかぶせてもダメで、鍵アカウントの「読めない」領域で自分がどう評価されているかまで、気になりすぎてガマンできない人格さえ生まれることは、有名な事件で広く知られるようになった。

じゃあ、どうしたらいいんだろうか。
今回の寄稿の依頼は、2022年に出した『過剰可視化社会』を踏まえてだったけど、同書についてはこれまでもちょくちょく、取材を受けてきた。以下の電子書籍も一例だけど、あえてそちらからヒントを引いてみよう。
先日、新型コロナウイルス禍で3年間、中断していた地元のお祭りがありました。お子さんに色とりどりの浴衣を着せて、街を歩くご家族が多い。
「かわいい子に育ちましたね」と、お互いに声を掛けあって、承認しあう機会なわけですね。リアルな対面の関係では、「誰に承認してもらいたいか」という範囲が、触覚(=街での実際の出会い)によって自ずと限定されます。
ところが、SNSになると大変です。同じ場所で対面してはいない人と、触覚抜きで、「視覚のみ」で承認してもらわないといけない。……街を歩いて5人から「かわいいですね」と言われたら、大満足でしょう。しかしSNSでは「500いいね」くらいもらっても、まだ少ないとしか思えない。
初出は2023年9月のNewsPicks
(段落を改変)
値段のインフレも大変だけど、その前からぼくたちは評判のインフレに悩まされてきた。広義の触覚(リアルな対面での感覚)がもたらす「いま十分楽しいし、いっか」な満足感が効かないと、無限に数値を上げないかぎり承認を得られない。
数値だけではない。文字列のルッキズムに支配されると、文脈的には自分に配慮してくれている文章まで、「私の気持ちに合っていない!」と怒り叫ぶ人が出てくる。散々暴れた後で誤読に気づき、「発達障害だから人の気持ちは知りません」と言い出す例もある。

これが個人どころか、国と国の問題になると大ごとだ。最初は「謝罪」って文字面は自虐、と言っていたのが、いつしか「反省」って文言も自虐! みたいになって、なにも言えなくなる。もはや国として終わりである。
そんな教養もない無学か、わかった上で隠す詐欺師が持て囃してきたのが、「うおおお面倒くさいから全部AI!」みたいな話だ。バラバラにAIとお話しすれば対面は要らないでしょ、というわけだが、AIはもちろん明示的に可視化されたデータしか読めないので、もっと症状はひどくなる。
2020年の5月に出した斎藤環さんとの対談集でも、ぼくはそのことをはっきり言っている。まさにコロナ最初期の大混乱のさなかでも、「対面」の不可欠性を説いてきたから、オンラインのルッキズムには騙されない。
人間が社会を維持するには、ニュアンスという媒体を噛ませないとダメなんです。……「慰安婦の前に “従軍” をつけますか?」「“侵略” や “謝罪” の語は入ってますか?」のように、AIでもチェックできるやり方で内容を判定していたら、どんな文面を書いても「その言い方は認められん」という壁にぶち当たる。
そうではなく談話を発表する総理大臣の表情や所作といった身体性の次元も含めて、ニュアンスの形で「追悼と反省の念を伝える」ことで、なんとか互いにコミュニケーションできている。
『心を病んだらいけないの?』182頁
ホンモノは、視覚だけを過敏にする不健康な「対面なし」に反対する。ニセモノは、視覚しか使えない状況の方が自分が商売しやすいとして、いつまでも危機を引き延ばし、不安に駆られた顧客たちに貢がせる。
『Art Collectors’』への寄稿の最後は、こう結んだ。社会を分断してでも自分の承認がほしい、視覚過敏のモンスターたちに食い荒らされた数年間から回復するために、ぜひ多くの人が、手に取って考えてくれるなら嬉しい。
一緒にいることを相手が許容しており、悪いことは「なにも起きない」という安心感を、対面する人は触覚で感じとる。それが初めて、視覚だけで接した際に抱いた敵意や不安を、和らげる。
(中 略)
「認めてくれる居場所が、ここにあるから、もういいか」。そうした充足は、触覚を通じてしか得られない。現前する人いきれの匂いを嗅ぎ、脱線に満ちたノイズを聴き、それでも壊れない関係を味わったときに、ルッキズムという「視覚の専制」は終わるのである。
49頁
参考記事:



(ヘッダーは1970年代のアフガン。タリバン支配の再来を報じた2021年8月の中央日報より)
編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年8月28日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。














