本書は、タイトルが示す通り「株で儲けたければ社長を見ろ」という、きわめて単純だが、実践されることの少ない命題を正面から掘り下げた一冊である。財務諸表やマクロ環境、テーマ投資といった「定量分析」がときに過剰に推奨されるなかで、企業の最終的な意思決定主体である「社長」という存在に焦点を当てる姿勢は、むしろ古典的とも言える。だからこそその内容は新鮮だ。
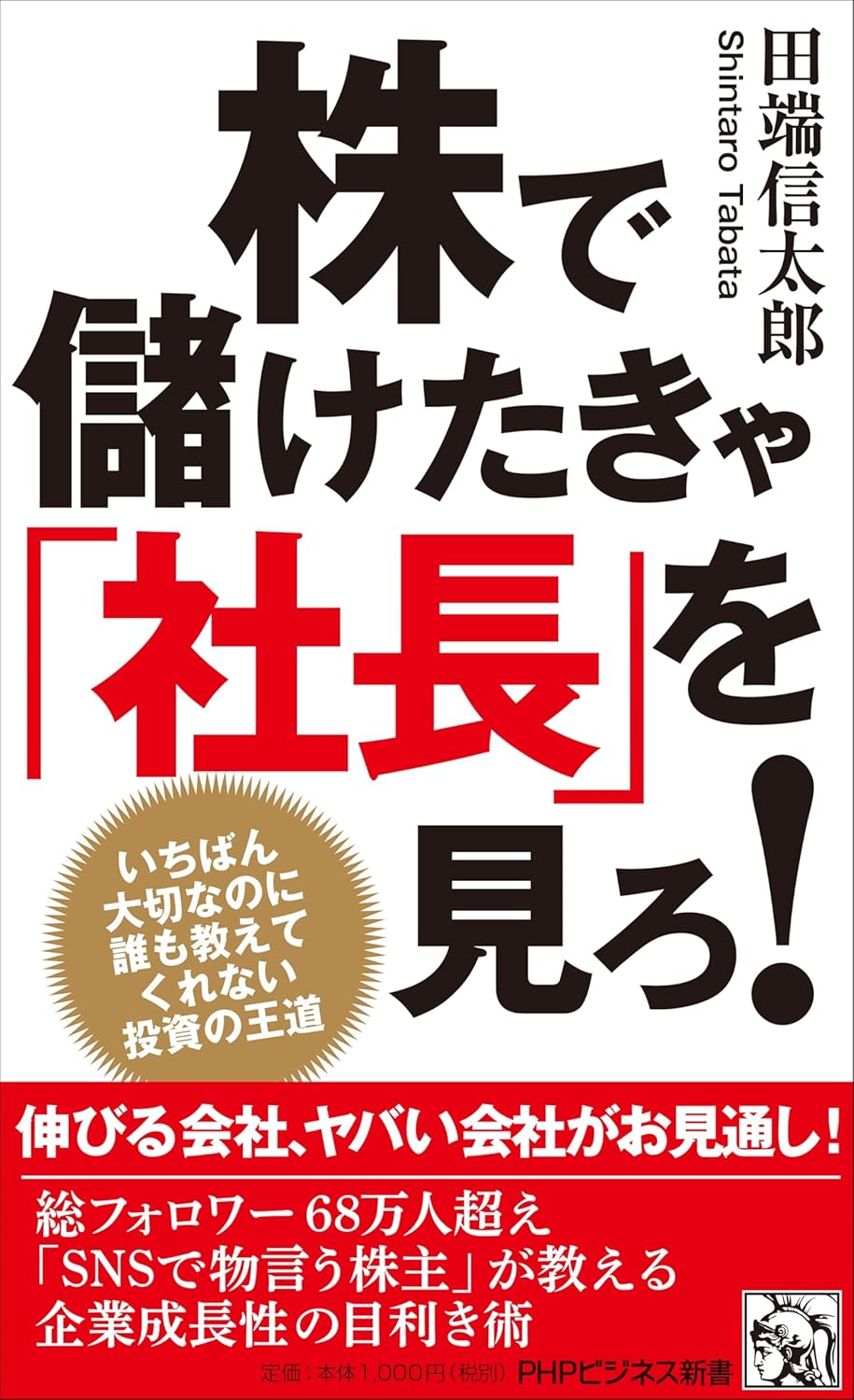
著者は個人アクティビスト投資家としての経験を踏まえ、株主を「社長の上司」と位置づける。この比喩は乱暴に見えて、実はコーポレートガバナンスの本質を突いている。会社は株主のものであり、経営者は委任された存在にすぎない。日本ではこの当たり前の前提が、長らくその「空気」によって曖昧にされてきた。本書は、その曖昧さを明確な言葉にし直す作業でもある。
興味深いのは、著者がアクティビズムを「企業を叩く行為」ではなく、「社長を理解し、変化を促す行為」と再定義している点だ。社長の弱点やコンプレックス、価値観の源泉にまで踏み込む必要があるという主張は、きれいごとでは済まない現実をよく示している。だが同時に、これは投資を「人間理解」の営みとして捉え直す試みでもある。
本書の構成は、社長のプロフィール、側近、組織、心理、対外的な振る舞いへと、観察の距離を変えながら企業の本質に迫っていく。その方法論は、ある意味で社会学的であり、心理学的でもある。特に創業オーナー社長を「現代の戦国大名」と捉える視点は、日本のスタートアップや新興企業を理解する上で有効ではないだろうか。彼らは合理的経営者というより、強烈な欲望と物語を背負った存在だからだ。
もちろん、本書のアプローチは万能ではない。社長個人の存在に過度に意味を見出せば、属人的なリスクを過小評価する危険もある。だが著者自身も、光が強ければ影も濃くなることを繰り返し強調している。その点で本書は単なる成功法則本ではなく、「社長を見るとはどういうことか」を考えるための思考の補助線を提供する哲学書とも言える。
本書の射程は投資だけにとどまらない。就職や転職、取引先選びにおいても、「社長を見る」という視点は有効である。企業文化はトップの価値観の反映であり、その影響は規模が大きくなっても簡単には消えないのだ。数字だけを見て企業を判断することの危うさを、本書は繰り返し説いている。
結局のところ、著者が言いたいのは非常にシンプルだ。投資とは数字のゲームではなく、人に賭ける行為である、ということだ。社長の美学や価値観に共感できるかどうか。それが、長期的に納得のいく投資を行うための最重要条件だという主張には、首肯せざるを得ない。
日本では、いまだに「会社はみんなのもの」「社長は偉い人」といった曖昧な認識のまま企業統治などの議論がなされていることが多い。本書は、その前提を静かに、しかし確実に揺さぶろうとしている。社長を神格化するのでも、悪魔化するのでもなく、一人の人間として直視する。その姿勢こそが、本書の最大の価値であり、投資冥利というものなのだろう。
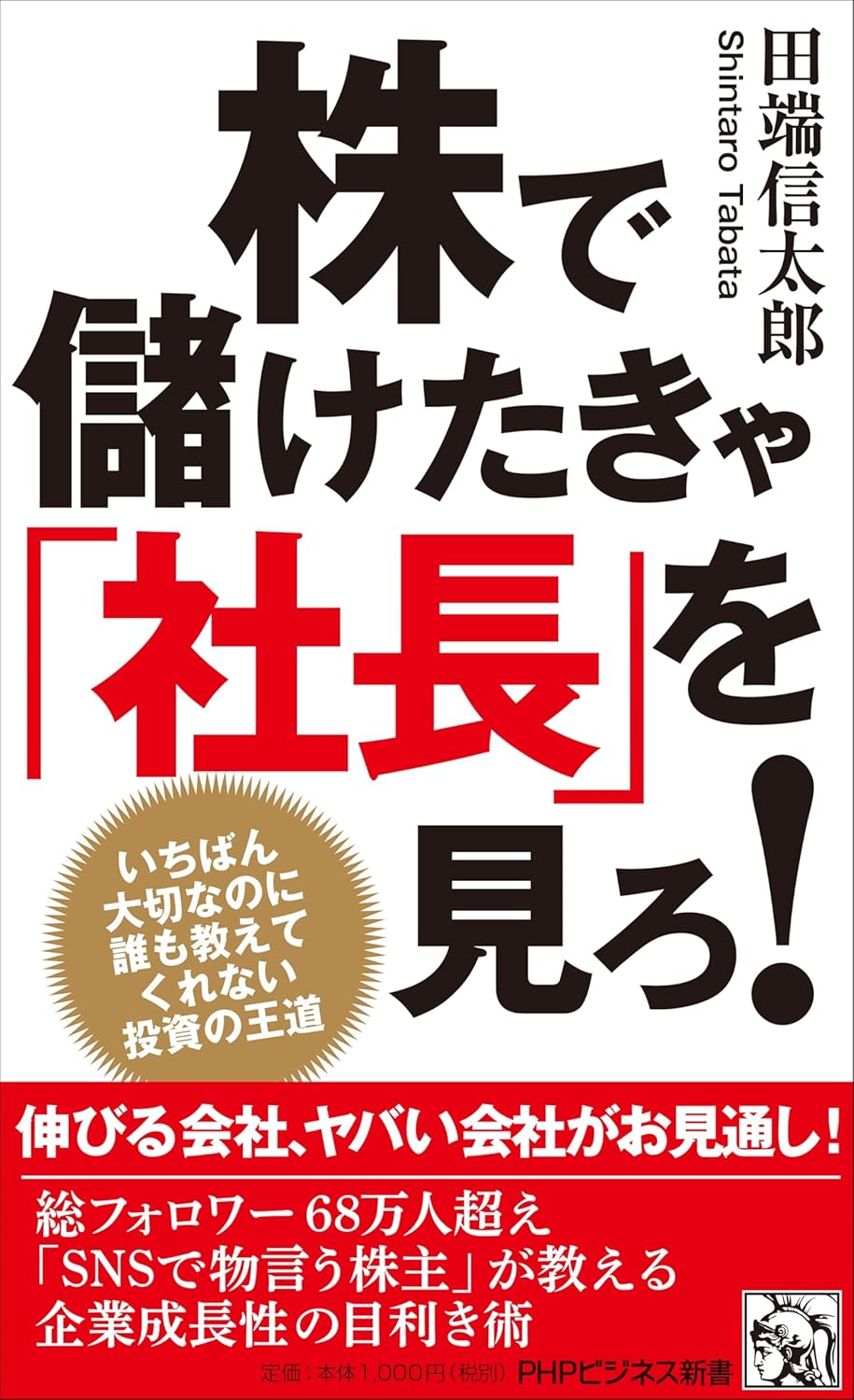
株で儲けたきゃ「社長」を見ろ!
【目次】
序章 社長という人種を知る――会社を左右する「イズム」
第1章 まずは「プロフィール」を見ろ――社長の「価値観」
第2章 半径3メートルの人間関係から見える〝危険〟と〝可能性〟――社長の「本性」
第3章 組織という鏡が映す「マネジメントの器」――社長の「人徳」
第4章 「無自覚のモチベーション」が生む成長と暴走――社長の「心理」
第5章 外側から覗くリアルと演出――社長の「危機管理」

metamorworks/iStock














