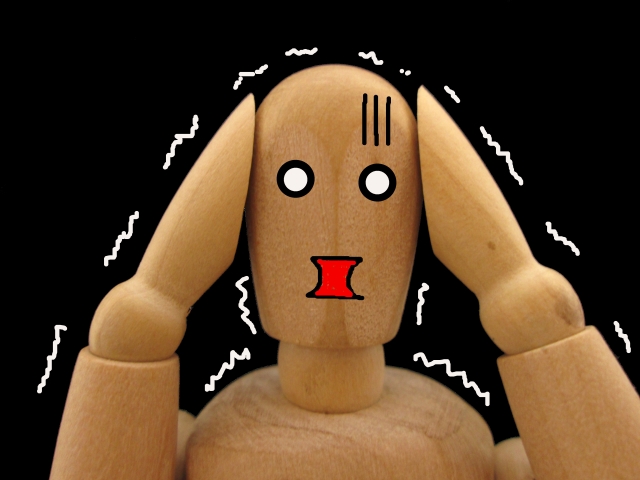当方は15日、仕事部屋で窓から入ってくる早朝の微かな風を肌に感じながら、このコラムを書きだした。15日は日本では72回目の「終戦の日」だが、オーストリアを含む欧州カトリック教国では「聖母マリアの被昇天」の教会の祝日であり、同時に休日だ。教会に通わない労働者も15日の休日をもたらしてくれた聖母マリアに感謝する一日だ。

▲「無原罪の御宿り」=バルトロメ・エステバン・ムリーリョ画(ウィキぺディアから)
「聖母マリアの被昇天」といってもキリスト教圏外の人々にとってピンとこないだろう。簡単にいえば、聖母マリアが霊肉と共に天に昇天したという日で、ローマ法王ピウス12世(在位1939~58年)が1950年、世界に宣布した内容だ。もちろん、聖書にはそのようなことは一切記述されていない。その意味で、キリスト教会の伝承に基づいた教義といえる。
ポーランドやスペイン、ポルトガルなどの南欧諸国では熱心な聖母マリア崇拝が広がっている。聖母マリアを“第2のキリスト”のように崇拝する信者も少なくない。キリスト信者でない人にとって、「マリアの処女懐胎」と共に、霊肉と共に天に昇天したという「霊肉被昇天」という教義は少々荒唐無稽だろう。キリスト教会の中でも、東方正教会はマリアの肉身昇天ではなく、霊の昇天と受け取り、マリアの昇天を教義とは受け取っていない。
参考までに言及すると、キリスト教社会で長い間、神は父性であり、義と裁きの神であったが、慰めと癒しを求める信者たちが、母性の神を模索しだしたのは自然の流れだった。そこでイエスの母親、聖母マリアが第2キリストとして母性の神を代行してきたわけだ。ただし、イエスが結婚して妻をめとっていたならば、イエスの家庭で神の父性と母性の両方の格位が完成していただろうから、聖母マリア崇拝といった現象は起きなかっただろう。その意味で、聖母マリア崇拝の背後には、イエスの家庭の悲劇が隠されているわけだ(「イエスが結婚できなかった理由」2012年10月4日参考)。
当方は京都の舞鶴出身だ。舞鶴といえば、当時海軍の基地があった湾岸都市だ。米国が舞鶴を原爆投下候補地の一つに挙げていたが、天候の問題から変更されたと聞いたことがある。第二次世界大戦後、ソ連による抑留から解放され、 引揚船で帰ってくる息子の帰りを待つ母親の姿を描いた二葉百合子さんの歌「岸壁の母」を聞く度、心が締め付けられる。15日の「終戦の日」にはさまざまな思いが脳裏に浮かんでくる日本人が多くおられるだろう。
同じ15日だが、「聖母マリアの被昇天日」は非常に観念的だ。ちなみに、聖母マリアの神性を称える祝日が年に2日ある。8月15日の「聖母マリアの被昇天」と12月8日の「聖母マリアの無原罪の御宿り」だ。両日とも教会の教義に基づいた祝日であり、実質的な意味は少ない。
ひょっとしたら、聖母マリアという存在自体がキリスト教会が構築してきた観念的な女性像かもしれない。キリスト信者の中には、イエスと共に生きたマグダラのマリアに理想的女性像を見出す信者が少なくない。ローマ・カトリック教会総本山、バチカン法王庁は昨年6月、マグダラのマリアの役割を評価し、彼女を典礼上、“使徒”(Apostle)と同列にすることを決めたばかりだ(「『マグダラのマリア』の人気急上昇」2016年6月12日参考)。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2017年8月16日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。