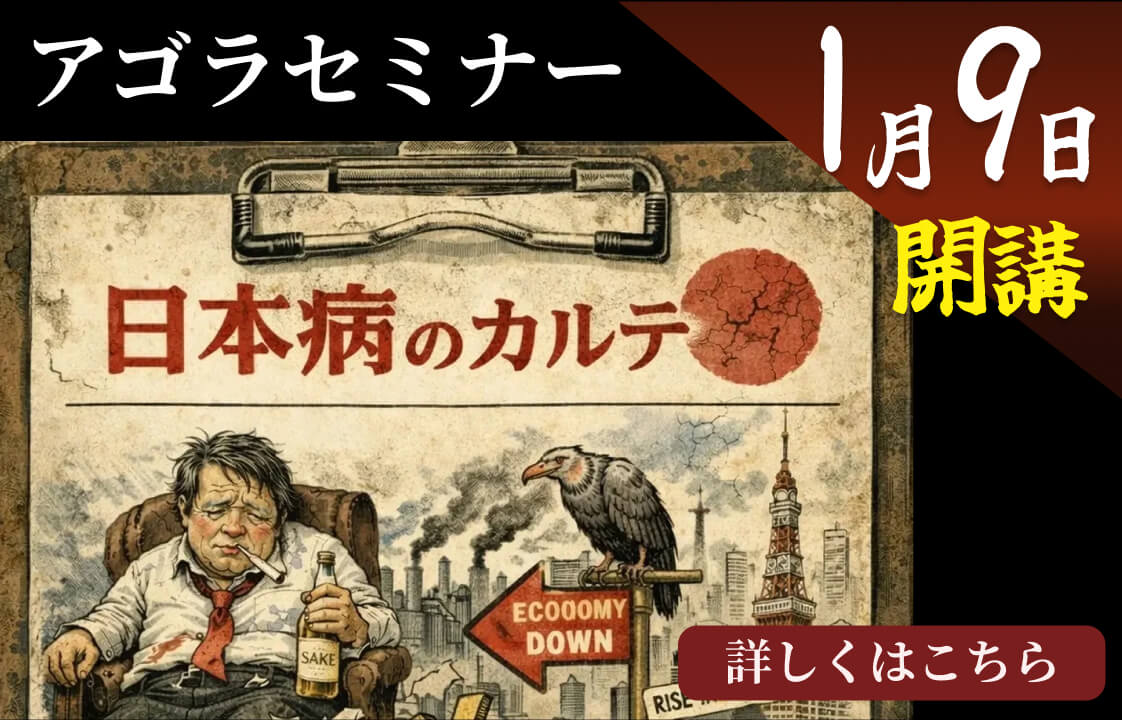国会では、予算案の修正をめぐって与野党協議が続いている。このうち日本維新の会は「高校無償化」を来年度から実施することで折り合う(予算案に賛成する)見通しだが、国民民主党は基礎控除を引き上げる交渉を続けている。
昨年、自民党税調は年収123万円まで引き上げる案を提示したが、国民民主は納得せず、18日にも新提案が政府・与党から出る見通しだ。
「年収の壁」税控除内訳で手取り変化 ポイントは住民税https://t.co/epgTtS2CQa
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) February 18, 2025
■ 政府・与党の提案
- 非課税枠を年収103万円から123万円へ引き上げる(所得税ベース)。
- 基礎控除と給与所得控除をそれぞれ10万円ずつ増額し、合計20万円引き上げる。
- 住民税の非課税枠の引き上げは10万円のみ(基礎控除は据え置き)。
■ 住民税の影響と財源問題
- 住民税は一律10%の税率のため、低所得者層への影響が大きい。住民税の控除も所得税と同様に増やせば減税額が倍になるが、地方財政への影響が懸念される。
- 政府案では、国・地方で6580億円の財源が必要となるが、住民税の減収分は750億円にとどまる。
- 地方自治体は財源減少による住民サービスの低下を懸念し、拡大に慎重な姿勢を示す。
■ 国民民主党の対案
- 所得税減税を重視し、非課税枠を年収178万円に引き上げる案を掲げる。
- 基礎控除を75万円引き上げる場合、年収600万円の人で年間15万円の減税が見込まれる。給与所得控除とのバランス次第で減税額に大きな差が生じる。
- 財源問題を考慮し、国民民主党からは年収156万円(基礎控除53万円増)とする妥協案も浮上している。
Q. 基礎控除を156万円に上げると、年金受給者はほとんど無税になるのではないか?
■ 政府案の非課税枠引き上げ
- 年収156万円まで非課税(所得税ベース)
- 基礎控除を48万円 → 58万円(+10万円)に引き上げ
■ 公的年金控除の適用
- 65歳以上の年金受給者は、公的年金控除が110万円。課税対象額は12兆円と、基礎控除の半分近い。
- 年収156万円 + 公的年金控除110万円 = 266万円まで無税。年金収入が266万円以下なら所得税ゼロ
- 厚生年金の平均月額は約15万円(月15万円 × 12か月 = 年間180万円)なので、これがすべて非課税になる可能性が高い
- 住民税の基礎控除は据え置き(43万円のまま)。住民税にも公的年金控除が適用されるため、多くの年金受給者が住民税非課税となる可能性
Q. 所得税の納税者が大幅に減るのではないか?
■ 年金受給者の影響
- 年金受給者4000万人のうち、約2400万人が所得税ゼロになる可能性が高い。
- 年金収入266万円以下の人は完全非課税になり、高額療養費制度などで最低所得者の扱いを受ける。
■ 現役世代の影響
- パート・アルバイト層(約500万人)も年収150万円以下なら非課税に。
- 「年収の壁」の影響で働く時間を調整していた人も、より自由に働ける可能性。
■ 納税者・税収の減少
- 5000万人(現在の納税者) – 2400万人(年金受給者) – 500万人(低所得者) = 約2100万人。
- 結果:納税者数は半減し、約2100万人に減少する可能性がある。
- 現在の所得税収は約20兆円。そのうち減税の対象は低所得者だが、納税者が半減すると、最大8兆円規模の税収減が発生する可能性。
- その財源について国民民主党は「税の自然増」などの一時的な財源しか示していない。
⚠ デメリット・懸念
- 納税者数の大幅減による税収不足。財源確保のために、消費税や他の税負担が増える可能性。
- 現役世代の負担増(年金受給者が免税される分、現役世代の負担が増す)。
- 減税の財源として基礎控除55万円の2倍もある公的年金控除の削減は削減しないと、現役世代の納得は得られない。
【追記】18日の協議で、自民党は「年収200万円以下は基礎控除を年収160万円まで引き上げる」という案を提示した。この対象者は300万人程度で、国民民主は納得していない。