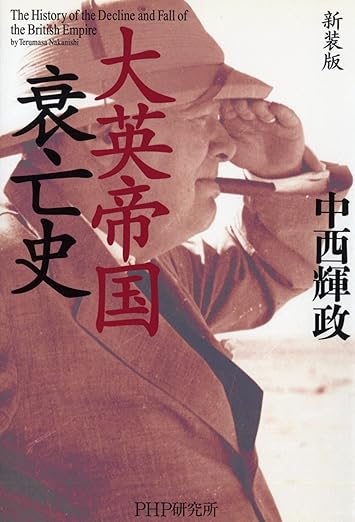19世紀後半に絶頂を迎え、世界の諸大陸に植民地を有し、「日の沈むことのない国」と称された大英帝国はいかなる興亡をたどったのか。本書は、帝国の興亡と人民の精神活動の観点から、英国人のアイデンティティの変遷に焦点を当てて大英帝国の衰亡を論じている。
大英帝国の基礎は、世界的に広大な国土や資源、人口に求められるものではない。筆者によると大英帝国の覇権は、歴史的変遷により生起した欧州のシステムに英国がうまく乗り、そのシステムを運営する能力に長けていたことに由来している。
著者は、英国の覇権を支えた対外政策を象徴的に「勢力均衡」と呼び、この政策を支えた英国人の発想、態度、思考様式の変遷に大国衰亡の因果があるとみている。自らが圧倒的に優位な国力を有することで均衡を形作るのではなく、欧州の大国の力学を巧みに利用することで少ない力(軍事力)で大きな成果(欧州大陸の平和)を生み出す、巧妙な戦略によって平和と安定を実現させたと説いている。
この時期、アメリカ独立からナポレオン戦争、第一次世界大戦まで続くいわゆる「長い19世紀」において、本来的に物理的小国である英国による勢力均衡が世界史に記憶される所以である(そこには工業技術力と海軍力が支えた植民地経営と自由貿易体制、欧州諸国の相対的な対英国劣後の事情があった)。
その心は、本書によると、強者に属して自国のその場凌ぎの安定を保つことではなく、強者間(スペインやフランス)の均衡状態の維持を対外政策の目標とし、同盟を組むとしても強者と組むことよりも、価値観を共有する国家との連携を志向することで国家存立の自由を維持することが目的とされていた。
このようなある種賢慮な対外政策は、19世紀後半にかけて経済力・軍事力においてドイツとアメリカの猛追を受ける過程で陰りを見せていく。英国の知識人は、この時期に大英帝国の覇権が衰退期に差し掛かっていることを自認する言説を隠せなくなっていった。この時代から第二次世界大戦、そしてスエズ戦争やインド独立にかけて、英国人は大英帝国が斜陽に傾いていく様を内心に感じながら、帝国の誇りと力を維持しようと努めた。
その歴史的実証は、戦争という形ではボーア戦争やスエズ紛争に、外交においてはいわゆる三枚舌外交やインド独立へのプロセスに見て取れる。これらの対外的事象において、英国は虚勢を示しながら、結果がどうであれ「帝国として振る舞う」ことに腐心する姿勢が一貫しているように思われる。
本書は、英国人の精神的活動の変遷から大英帝国の衰亡の因果を読み解こうとする作品である。帝国興亡の節目における英国人のナショナル・アイデンティティを写実的に切り取り、確かに英国人が帝国として世界を統治する自信を失っていく様が確認できる。しかし、本書の主題である覇権国の衰亡と国民精神の関係は、きちんと命題化されているとは言い難い。
20世紀をむかえ、第一次世界大戦、第二次世界大戦、戦後の中東紛争という節目において大英帝国の衰亡の契機を大きく捉えて全体としての物語を構成することで、大英帝国の覇権を形成した対外政策の伝統—大英帝国が覇権の基礎とした(精神的傾向としての)勢力均衡や自由貿易を基調とする国際経済秩序—が、帝国の経済・軍事上の新興国(ドイツ・アメリカ)に対する比較優位の損失からくる焦りから摩耗していくプロセスを概観することができる。
本書も指摘している通り、大英帝国の衰退プロセスにおける戦略的判断の一つ一つが、帝国維持/植民地再統合の観点でいかなる「帝国再興」の可能性を有していたのか、歴史のifを考察することで帝国衰亡の一般的な要因に対する洞察眼が磨かれていくと考える。
大英帝国とは何だったのか、歴史上の帝国(モンゴル、スペイン、ポルトガル、そしてアメリカ)との相違は何なのか、その独自性を問うことは、今日の日本国の繁栄と安全の長期的見通しを考察する上で依然として有意義な問いかけである。
資源や人口という所与の国家資源に必ずしも恵まれていないという意味で、近代英国と日本は基本条件が類似している。本来的に小国ながら帝国を形成した英国の知恵には、物理的国力では大国に伍することはないにせよ、地政学的立ち位置から地域・国際秩序の命運を握る現代日本にとって、自国の生存に加えて国際公共として望ましいステートクラフトについて歴史的知恵が見出せる気がしてならない。
編集部より:この記事はYukiguni氏のブログ「On Statecraft」2025年12月12日のエントリーより転載させていただきました。