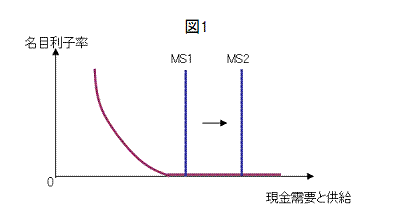著者:森岡孝二
発行:2010/4/15
販売元:桜井書店
表題が暗示しているように、「時代の終焉」は新たな「時代の開幕」を告げている。 主に1980年代以降の30年間の資本主義世界と日本経済の動態をトータルに検証した本作品は、経済学の専門家・研究者にとどまらない幅広い読者層に届くよう編まれた警世・エールの書だ。
論理と各種統計データから錯綜しあう多様な問題群を正確に分析し、その経済社会的含意を深く汲み取る著者のコア・メッセージは、楽観論でも悲観論でもない。「人間らしく働く」ことがいかに困難な時代に突入しているかを直視し、「まともな雇用・賃金・労働時間」の三要素の統合からなる 「ディーセントワーク(decent work)」 ― 著者は「まともな仕事・働き方」と訳出 ― の実現をめざす政策提言は、万人にストレートに響くのではないか。静かなる良識で説く経済学者の揺るぎない精神が論旨を貫く。
終焉を迎えるのは、ケインズ主義・福祉国家路線の挫折から、実際は強力な国家権力を行使して、市場化・民営化・規制緩和を究極的に推進する新自由主義の政策イデオロギーのグローバルな浸透により出現した<強欲な>資本主義だ。「これまで」と「これから」の分水嶺をなす2008年世界金融恐慌はまさに強欲資本主義の帰結であり、大胆にいえば、それは決して<まともな>資本主義ではなかろう。持続可能な労働環境、ひいては地球環境システムの再構築は、「ポスト新自由主義を超えて、ポスト資本主義に踏み出す可能性」(359頁)を中長期的に模索することを意味している。
本書でとくに焦点となる<雇用・労働の変容>の実質は、労働時間(短時間労働と長時間労働)と雇用形態(正規雇用とパート・派遣労働など非正規雇用)の両面において「多様化のなかの不安定化」を伴う二極分化とあわせ、雇用の女性化、過労死・過労自殺、ワーキングプアの増大による労働者階級の貧困化が顕著に加速していることである。日本が米国に次いで相対的貧困率ワースト2の先進国になったという2006年「OECD対日経済審査報告」は衝撃的で、「格差」から「貧困(化)」への関心のシフト自体が非人間的な労働環境の深度を象徴していよう。被害人口の規模と不払賃金総額から日本における最大の企業犯罪と診断されるサービス残業(労働者とその家族の貴重な自由時間の喪失)は、労務コンプライアンスの根本的不備の証左にほかならず、おのずと労働行政のあり方・責任問題にも波及する。
留意すべきは、自由競争の貫徹こそが効率的で公正な経済秩序をもたらすとみなす<市場個人主義>が、労働・雇用の諸変容の動因であることだ。それは、労働、消費、金融市場における個人の自由な意思決定を絶対視し、高度情報通信技術を物質的基盤とするグローバリゼーションに適合的なイデオロギーである。労働者は消費者や投資家としての主体性の拡大を通じ、いわば逆説的に、「市場個人主義が促迫する雇用の不安定化と長時間労働に決定的に抵抗することなく順応してきた」(121頁)という見解は、現代資本主義の多面性のなかの問題性の一端をうかがえる点で示唆に富む。
こうした雇用・労働の変容は、<企業のあり方の変容>をめぐる議論とも密接不可分である。バブル崩壊後の90年代の平成不況を介し、長期雇用慣行を柱とする日本型経営システム(ないしは利害関係者資本主義)から、短期の株主利益の最大化を理念とする米国型の株価至上主義経営(著者のいう株主資本主義)への転換が促進されたが、コーポレート・ガバナンスの変容は、労働分配率や労働者の福利厚生の大幅な低下、株主配当・役員報酬の大幅な増加という全く対照的な事態を誘発し、会社中心主義をより強化するものにほかならなかったからだ。働く人びとの人権はもちろん、自然環境・企業倫理などを尊重した社会的責任投資(SRI)への関心が高まる昨今、「雇用や労働に立ち入ったCSR(企業の社会的責任―評者)はほとんど語られていない」(246頁)日本の現状を想起すれば、終章における一連の企業改革論は実直といえよう。「まともな仕事・働き方」の実現はこれを端緒とする。
より広い視野からみて、世界の「政治経済の転換」は学問としての「政治経済学の変革・転換」という側面にいかなる影響を及ぼすか、イデオロギーとメソドロジーの関係を省察する意味でも、現代資本主義論争に再訪する意義は大きい(第1章)。次世代の政治経済学のストーリーは本書とともに歩むことになるのではないか。長年の研究成果を集約した筋金入りの力作である。
塚本恭章 愛知大学経済学部専任教員、(2011年4月から)日本学術振興会・前
特別研究員、 博士(経済学:東京大学)