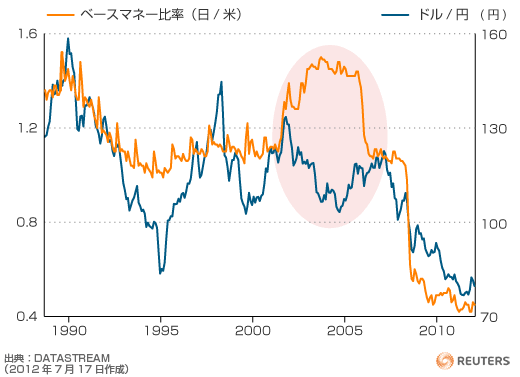予想通りの結果
自民党が公約として掲げている生活保護費の1割引き下げを巡って、その結果が注目されていた厚生労働省・社会保障審議会の生活保護基準部会の答申が、1月16日に公表された。
この部会では主に、生活保護受給世帯と、その比較対象とされる第1分位の低所得世帯(日本の一般世帯を所得順に並べて、10個の組に分けた場合、所得が一番低い組に入る世帯)を、2009年度の「全国消費実態調査」という大規模な家計調査を使って、比較分析してきた。
結論は、第1分位の低所得世帯に比べて、生活保護受給世帯の生活費が概ね高いというものである。ただし、世帯の種類によって、高いか低いか、あるいはその高さの程度にはかなりの差異が生じている。高齢者世帯では、生活保護受給世帯の方がむしろ生活費が低くなっている一方、比較的若い夫婦と子供がいる世帯や、母子世帯では、生活保護受給世帯の生活費の方が高くなっている。
この結果は、ある程度、予想通りというべきであろう。日本経済が20年近くもの間、デフレ状態に陥り、賃金減少も続いている中で、生活保護費の引き下げは、実はほとんど行われてこなかった。不安定就労や非正規化が進み、長期不況の影響を最も大きく受けている第1分位の低所得世帯と比較した場合、生活保護世帯の生活費の方が高いという現象が生じてしかるべきである。
また、前回の自公政権下において、やはり低所得世帯と生活保護受給世帯の生活費を比較して、生活保護の母子世帯と高齢者世帯に対する加算金(母子加算、老齢加算)が廃止されたが、民主党政権が誕生して、母子加算のみが復活している。老齢加算額は月額1万5千円から8千円ほどであったから、その影響は大きかった。生活保護の高齢者世帯が、低所得世帯よりも生活費が低かったことには、こうした背景があるものと思われる。
スケールメリットの適正化
このほか、基準部会では、長らく問題が指摘されていた生活保護費の1類と2類のスケールメリットについても、踏み込んだ分析が行われており、この点は高く評価ができる。生活保護費のうち、直接、生活費にかかわる費用を生活扶助費というが、これはさらに費目によって1類と2類に分かれている。
1類は、食費や衣服費のように、個人単位でかかる費用で、家族の人数が多くてもスケールメリット(世帯規模が大きいことによる節約効果)は、あまり働かないものとされている(4人以上の世帯で多少考慮されている)。一方で、2類は水道や光熱費のような世帯単位で支払う費目で、家族の人数が多ければ、一人あたりの費用を大きく節約できると考えられ、生活扶助費の算定にそれが反映されている。
しかしながら、ちょっと考えればわかるように、1類の費目もスケールメリットは大きいはずである。たとえば、一人暮らしでは、一人用の食事を作るにせよ、外食するにせよ、食費は高くつくが、家族の人数が多ければ、一人あたりの費用は安く上がる。衣服費も、上の子供の「おふる」を下の子に回すという形で、節約が可能である。
基準部会の報告書では、この点を「回帰分析」という統計的な手法を用いて厳密に分析しており、1類にかなりのスケールメリットが働き、現行の生活扶助費の計算方法が不適切であることが示されている。一方で、2類はむしろ現行の生活扶助費の方がスケールメリットを評価しすぎていて、現実はそれほどでもないことが示されている。スケールメリットの統計的な根拠に基づいて、1類費、2類費の算定方法を適正化する必要がある。
第1分位の低所得世帯を比較対象とすべきか
こうした基準部会の調査結果に対して、研究者の一部や生活保護受給者を支援する社会運動家等からは、「生活保護受給世帯の生活費が高いのではなく、比較対象の低所得世帯の生活費が低いのだ」という批判が挙がっている。この主張を裏付けることは難しいが、だからと言って間違ってもいない。確かに一理ある主張である。
もともと憲法25条で保障されている文化的最低限度の生活というものは、これ以下は認められないという「絶対基準」の最低生活費である。戦後、生活扶助費の算定方式は、「マーケット・バスケット方式」(買い物をバスケットに入れるようにして、最低限必要な物品の価格を合計して、生活扶助費を決める方法)や、「エンゲル方式」(生存に必要なカロリー数を足しあげたものを元に生活扶助費を決める方法)のような絶対基準で行われていた。
しかしながら、戦後の混乱期を抜け出し、高度成長時代に入ってからは、世の中の多くの世帯が成長して所得や消費が急増しているのに、生活保護受給世帯だけ、この最低基準に縛られておいてきぼりになるのは、あまりにかわいそうだということになり、一般の低所得世帯の所得上昇にリンクして、生活保護費を引き上げてゆく方法に移ってきたのである。
そして、現在は、生活保護受給世帯の生活費と、第1分位の低所得世帯の生活費を比較して、生活扶助費を決めるという相対評価の「水準均衡方式」に落ち着いている。しかし、ここで注意しなければならないのは、この方法は、第一分位の低所得者の生活費が右肩上がりで成長していることを前提としている方法だということである。
つまり、毎回、前回の生活保護費よりも今回の生活保護費の方が必ず高くなるのだから、相対評価の方法ではあっても、最低生活費の絶対基準を同時に満たしていることになる。仮に前回の生活保護費が最低生活費であれば、今回は必ずそれを上回るのだから、論理的に最低生活費の絶対基準を上回ることが保障される。
しかし、現在のような経済の長期停滞期、あるいは、これから人口高齢化と人口減少で経済規模が縮小してゆく中では、この相対評価の「水準均衡方式」が、必ずしも絶対基準の最低生活費をクリアしているかどうかは定かではない。マーケット・バスケット方式やイギリスなどで研究されている絶対基準の生活保護費の算定方式(MIS:Minimum Income Standard)等を用いた本格的検証を行うべきであったかもしれない。
国立社会保障・人口問題研究所の阿部彩さん、慶応大学の山田篤裕さんのような、絶対評価方法を研究している専門家が、せっかく基準部会の委員としてMISの紹介を行っていたことを考えると、この点は残念なことであった。今回、基準部会に問われていたものは、「水準均衡方式を前提とした比較」だけではなく、「現行の水準均衡方式で良いのか」という本質的な問題であったのである。
今回、生活保護費を引き下げるべきか
さて、目下の政策的焦点となっている生活保護費を引き下げるべきかという問題について、我々はどう考えるべきなのであろうか。筆者は、上記のような問題があるとしても、今回、ある程度の保護費引き下げはやむをえないと考えている。
その理由は、相対評価が適切か、絶対評価が適切かという議論とは関係が無い。以前から繰り返し主張しているように、デフレがこれだけ長く続いているのだから、その分を考慮すべきであるというものである。
デフレというのは、物価水準が持続的に低下していることであるが、この時もし収入額が変化しなければ、それは購入できる物の量が増えることを意味する。たとえば、月10万円の収入で、1食1000円の食事をすれば、100回の食事をとることができる。ここで、月10万円の収入が変わらず、デフレによって1食の値段が500円になれば、200回もの食事が可能となる。このように、デフレ下で収入が変わらなければ、購買力が増すのである。
実際には、デフレで物価が下がる中で、賃金や所得も低下しているので、普通の世帯はデフレで得をすることはない。つまり、購買力は増えない。しかしながら、生活保護費は長い間ほとんど変わらない金額に設定されているため、デフレによって買えるものの量が増えて得をしているのである。
これは、賃金や所得が低下している普通の世帯、特に低所得世帯に対して不公平である。さて、前回、2007年に決められた現在の生活保護費の水準については、今回の引き下げに反対している人々も、特に批判をしていない。ということは、適切な生活保護費の水準であるというコンセンサスがあることになる。
それならば、少なくともこの5年間分のデフレ分だけは、今回、考慮して生活保護費を引き下げることが論理的に望ましい。前回の生活保護費が絶対基準のぎりぎりの最低生活費だったとしても、デフレ分を考慮した引き下げは、その購買力を変化させないのである。
どの程度の引き下げ幅になるのであろうか。これは、物価水準をどの指標でとるかによっても変わりうるが、せいぜい2%~3%程度である。もちろん、今回検証されたように個別の世帯の状況ごとに配慮する必要があるが、全体として平均的に2%~3%の引き下げ目指してはどうか。もちろん、高齢者世帯については、引き下げにならない可能性が高い。
この程度であれば、それほど無理はないのではないだろうか。年金において2.5%の特例水準の解消に3年をかけることを考えれば、生活保護も3年ぐらいをかけて経過措置を作ると言うことでもいいだろう。それから、今後も、年金のように毎年の物価スライドをするようにしてはどうか。現在、安倍政権はインフレ目標を2%に掲げており、それがもし達成されるのであれば、5年に1度の改定作業では遅すぎて無理が生じる。物価水準の調整は毎年行うべきである。
生活保護受給者を支援する社会運動家にとって、最近の動向は「生活保護バッシング」ということであるが、やはりバッシングの背景には、一般の人々や低所得者の不公平感が高まってきていることがあるものと思われる。こうした不公平感を考えれば、デフレがこれだけ続いている中で、生活保護費だけが「びた一文まからん」というのは無理がある。
一方で、自民党が公約として掲げていた一律、1割削減というやり方は乱暴すぎる。世帯の状況に応じて丁寧に判断すべきであるし、1割がはたして絶対基準として適切かという問題がある。一方で、自民党も挙げた拳は下ろさざるを得ないだろうから、2%~3%の引き下げをするというあたりが根拠も明確で、政治的にも現実的な引き下げ幅のように思われる。
編集部より:この記事は「学習院大学教授・鈴木亘のブログ(社会保障改革の経済学)」2013年1月19日のブログより転載させていただきました。快く転載を許可してくださった鈴木氏に感謝いたします。
オリジナル原稿を読みたい方は学習院大学教授・鈴木亘のブログ(社会保障改革の経済学)をご覧ください。