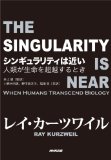産業に大きな変革をもたらすのは何時の時代でも技術革新である。経営手法、マーケティング手法の改革は、勿論一つのビジネスを大きく伸ばしたり、各企業の市場シェアを大きく変えたりはするが、産業構造を変えるところまでには行かない。だから、国にとっても各企業にとっても、技術の流れを先読みして、正しいタイミングで大きな投資をする事が欠かせない。
産業界では、常に成長する企業があり、また徐々に衰退していく企業があるが、その差を分けているのは、多くの場合「技術革新の大きな流れに乗れているかどうか」である様に思う。もしも技術革新の流れに乗る事を阻害しているような「組織運営」の実態があるとすれば、それはどういうものなのか? 私の見たところでは、意外にも「技術音痴の文系の経営者」ではなく、「権威主義的で独りよがりな技術部門のトップ」の存在に、より多くの問題があるような気がする。今回は、先回の記事に続き、この辺の「病理」の解明を試みてみたい。
全ての企業活動は、最終的に個々の消費者が何に金を払うかによって決まっている。例えば船舶や重機械を製造する企業であっても、最終的には「自社が造った船舶」が運ぶものや、「自社が造った機械」が作り出すものに金を払う消費者がいるから成り立っている訳である。
従って、どんな企業であっても、「世界中の消費者が最終的にどんな商品やサービスにどのくらい金を使うか」を正しく読み取ることが必要な訳だが、その一方で、「どのような技術のシーズがそのような商品やサービスを安価に提供する為に必要であるか」を見抜く事も求められる。言い換えれば、一つの企業の中で、常にこの二つが密接に絡み合い、スパークしている事こそが重要なのではないだろうか?
今回は、この点に注目し、日本の産業の明暗を分けた「自動車」と「半導体」の二つの分野に焦点を当てて、そのそれぞれが、何故上手くいったのか、或いは上手くいかなかったのかを考えてみたい。
まず「自動車」だが、これはほぼ上手くいっていると言って良いだろう。
その最大の原因は、各メーカーが始めから世界市場を意識した事にあるが、勿論それだけではない。自動車産業を支える技術は、多くの下請け工場に信頼性の高い部品を丹念に作り込んで貰い、それを効率よく組み合わせる事であるから、日本人の強みがここで十分に発揮出来たと言えよう。そして、飽く事なく改善を続け、信頼性の向上とコストダウンを極限まで追求した事も、この目的の為に生産ラインの自動化を徹底して進めた事も、その成功を支える大きな要因となったと言えよう。
しかし、その一方で、「消費者が自動車に何を求めるか」を読み取る事は、全ての自動車メーカーにとって、さして困難ではなかったという事も忘れてはならない。また、自動車メーカーというものは、トップから末端に至るまで、とにかく「自社が製造する自動車が世界中で売れる事」を目的に動いているのだから、「マーケティング戦略」には元々大きな揺らぎはありえないという事も、幸いしたと言うべきだろう(もっとも、これから「電気自動車」にどう対処するかについては、全ての自動車メーカーが色々と思い悩む事になるかもしれないが……)。
これに対し、当初は圧倒的な世界一を誇った「半導体」が、今日のような惨状を呈するに至ったのは何故だろうか?
初期において日本メーカーが世界をリードしたのは、徹底した品質管理(完璧主義)が日本人の性格に向いていたからだと思う。クリーンルームの整備でも、工程管理でも、日本企業に一日の長があった。
しかし、初期において半導体産業の中核をなした「メモリー」については、大手5社が横並びで雁行していた日本企業は、「需要がメインフレームからパソコンに移ろうとしている」という流れを何故か一様に見落とした。サムスンはいち早くこの流れを読み、製品寿命等を犠牲にしてもコストダウンを第一に考える体制に移行したのに、日本企業は、「韓国企業は技術が追いつかないので長い製品寿命が保証出来ないのだ」とタカをくくり、価格競争の現実に傲慢の鼻をへし折られるまで、意識改革を怠った。
(その後やっと規模の利益を追求出来る体制を作ったエルピーダでも、なお「独りよがり体質」は改められず、結局破綻した。現在、メモリーの分野で生き残れているのは、NAND Flashの将来性を読んでここに経営資源を集中した東芝だけである。)
一方、日本企業の先行に危機感を抱いた米国は、あっという間に日本から学ぶべきものは学び尽くし、メモリー分野を捨てて、より収益性の高いロジック(SOC – System-on-Chip)分野で世界をリードする地位を築いた。中でもIntelは、Windows OSを開発したマイクロソフトと二人三脚で世界中のIBM互換のパソコンメーカーを支え、結果として、世に言う「WINTEL時代」を謳歌するまでに至った。
一方でIntelに差を付けられたTIは、OMAP等の優れた汎用デジタルプロセッサーを持っていたにもかかわらず、躊躇なくこれを捨てて、今はアナログプロセッサーに特化しつつある。また、Qualcomm等の新興メーカーは、デザイン面ではこれまた新興のARMのプロセスを使い、製造(Foundry)は台湾のTSMCに一任する事によって、自らが得意とする携帯通信分野等で急成長を遂げた。
Qualcommに限らず、米国の他の殆どの新興半導体メーカーも、殆ど例外なくTSMCに製造を一任しているので、TSMCは今やインテルをも凌ぐ「規模のメリット」を享受しており、製造技術の水準でもIntelを脅かしつつある。サムスンは、製造とデザインの両方の能力を持ったままでIntelに追走しているが、製造部門はTSMC同様に受託製造も行っており、頑にVertical Integrationを追求している訳ではない。
この間、日本のメーカーは何をしていたか? 「これからはメモリーではなくSOCだ」と、各社一様に掛け声はかけたが、何の勝算もなかったにもかかわらず、Intel同様のデザイン・製造の一体運営体制を一向に変えようとせず、結果として、一社として「規模の利益」も「特定分野での圧倒的なデザイン力」も実現出来ないままに、今日の惨状を迎えた。
もしこの時に日本の半導体業界に強力な指導者が現れ、「製造(Foundry)は各社共同で新しい会社を作ってここに全て委託する事にし、各社はそれぞれユニークなデザインで勝負しようではないか」と呼びかけていたら、恐らく現在のTSMAをも凌ぐ強力な「受託製造会社(Foundry)」が出来ていたであろうし、5社の中の何社かは、特定の分野で「世界に通用する半導体メーカー」として生き残れていたかもしれなかったのだが、その事を考えると本当に残念だ。
メモリーと異なり、SOCは「どんな用途の為に作るのか」という事から考えなければならない。勿論、最大の市場はパソコンだが、米国での教育分野で先行したAppleも、日本で一時は圧倒的に強かったNECも、Windows OSを搭載したIBM互換機の前に簡単に屈してしまった(もっとも、Appleだけは、根強いMACファンに支えられ一定シェアを維持し、それが今日の復活につながった)。
結果として、日本の半導体メーカーは、自動車や家電、カメラ等の分野で一定の市場は確保したが、単純な機能にのみ対応するものが主だった為に、より強力な処理能力を求める技術革新の主流から外れてしまった。中でも痛かったのは、パソコンに続く巨大市場に成長する可能性を秘めた通信分野では、殆ど成果を上げる事が出来ず、Qualcomm等に対抗出来る勢力になれなかった事だ。
ここで、一貫してみられるのは、市場を見る目が鈍かった事だ。また、通信分野で典型的に見られた様に、世界市場に照準を定めず、居心地の良い自分たちの閉ざされた世界に安易に閉じこもってしまった事だ。更に思い切って言うなら、「多くの重要な決定が、技術系のトップに任されきってしまい、全社の経営のトップも、市場戦略の専門家も、殆ど蚊帳の外におかれてしまったのが敗因だった」とも、或いは言えるかもしれない。
早い時期に世界の半導体業界をリードした日本の大手5社、東芝、日立、三菱、NEC、富士通は、何れも半導体専業メーカーではなく、重電、家電、通信機、コンピュータ等を製造する総合電機メーカーのである。つまり、半導体部門は会社の中に多数存在する部門の一つに過ぎなかった訳だ。そして、必要とされる投資が巨額だったにも関わらず、そこで必要とされる技術力は他部門からは理解し難いものだったから、社運を賭けた巨額の投資は困難となり、部門レベルの経営判断に全てが委ねられたのではなかっただろうか? そして、多くの場合、この部門の長は「技術者集団のボス」であり、市場の先行きを読むのには、必ずしも長けていなかったかもしれない。
ここで、日本独特の「組織の病理」とも言えるものが、大きく影響してくる。日本の多くの企業では、文科系と理科系は必要以上に分離されている。米国等では、PhDの称号を持った頭脳抜群の技術者が、会社の経営にも興味を持ち、その為にわざわざMBAも取ったりするのがザラだが、日本の企業では、「技術部門」と「その他の部門」はあたかも「相互不可侵」を約束し合っているかの様に、全く別建てで動くケースが多い。
日本では、文系の社員は総じて勉強不足だが、技術問題に口を挟むと白い目で見られることが多いので、それが意欲を削いでいるのかもしれない。その一方で、有能な文系の社員が幅を利かすのは、「人事(労務)部門」や、政治的な動きが中心の「企画・業務(総務)部門」であり、マーケティングを担当する「営業部門」は、単なる「売り子」として総じて下に見られている事が多いようだ。
また、技術部門では、所謂「権威者」が必要以上に永続的に影響力を行使する傾向がある。技術的に優秀かどうかの評価は、上司である年配の技術者のお眼鏡にかなうかどうかで決まるので、柔軟なものの見方が出来る若い技術者が大胆に発想の枠を広げると、上司の不興を買い、活躍の場を閉ざされる恐れもある。これは、図らずも「原子力ムラ」の問題で白日の下に曝らされた「大学の理工学部の閉鎖性」にも近い現象だ。
日本の多くの企業の技術部門が、有能で意欲的な技術者にまで、どうでもいいような「管理者能力」を一様に要求するのも、全く馬鹿げた事なのに、一向に改まる気配はない。その為に、折角の有能な技術者も、「有能」故に「管理職に抜擢」され、現場から引き離されて、その後もずっと、退屈な「報告書作り」や、非効率な社内政治に振り回される事になる。
米国では、技術系の社員は、「技術者」として上を目指したいか、「管理職」をやってみたいか、或いは事業開発やマーケティングに転出したいかの選択を求められる。大部分は「技術者」として上を目指す道を選ぶが、第二、第三の道を選ぶ者も少なくはなく、彼等は彼等なりに良い仕事をしているようだ。日本では何故同じ事が出来ないのか、全く理解出来ない。