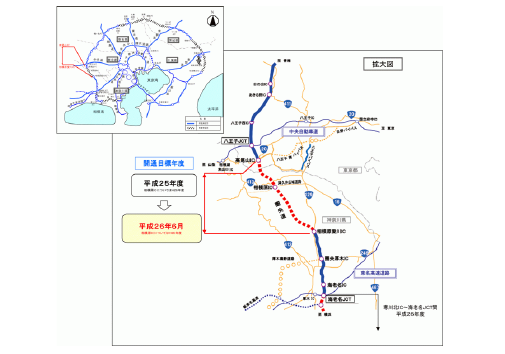本書は、拓殖大学総長の語る大学の歴史である。拓大というと今は駅伝の強い右翼系の大学というイメージしかないが、戦前は桂太郎が創立し、後藤新平や新渡戸稲造も学長をつとめた名門だった。その創立の目的は台湾の植民政策の担い手を育てることだった。
拓大の卒業生は台湾だけでなく朝鮮や中国へも渡り、アジアで初めて近代化をなしとげた日本の「ベスト・プラクティス」を各地に広めた。これはもともと何もなかった台湾では問題なかったが、民族主義の芽生えていた朝鮮半島では抵抗を受け、満州や中国では軍事衝突が起こったので、やむなく軍を派遣して鎮圧した。
――というのが本書の描く歴史だが、当時の日本人の主観的な歴史観に近いだろう。この観点から見ると、近代アジア史は「アジアを救った」日本と、その権益をねらうアメリカの闘争で、最大の分岐点は1923年の日英同盟解消だった。それまで日本は国際協調のもとに中国や朝鮮に地歩を築いていたのだが、アメリカがそこに割り込むために同盟を解消させて日本の孤立化をはかったのだという。
満州事変や日中戦争は、中国側の挑発に乗って日本軍が「大陸の泥沼に足を取られた」歴史として描かれる。日米戦争は、ハル・ノートでアメリカが最後通牒を突きつけて日本を「暴発」に追い込んだ結果、やむなく始めた戦争だった――と開戦までの経緯は1ページ足らずしか書いてない。
それは主観的には「自存自衛」の戦争だったかも知れないが、結果は自存にも自衛にもならない大失敗だった。その結果、戦略なき植民政策は「日帝の侵略」として断罪され、日本は中国と韓国からいまだに「歴史問題」で文句をつけられる。拓大は善意でアジアを開発したのだろうが、結果がすべてである。
たしかに本書もパル意見書を引用していうように、東京裁判の訴追国が主張した権益も侵略で得たものだ。不戦条約ではその権益に自衛権があるものとされ、それをおかす戦争を侵略と定義したが、1928年までの既得権が正しく、そのあとの権益が侵略だという理由は何もない。日本は周回遅れでゲームに割り込もうとして、たたき出されただけだ。
しかし日本がアジアで果たした積極的な貢献も、日米戦争で帳消しになった。その莫大な被害と愚劣さは、何をいわれてもしょうがない。だから本質的な問題は、日本の植民政策の「動機の純粋性」ではなく、それがなぜ暴発したのかということだ。この点について本書が何も語らず、「自虐史観」ばかり批判しているのは片手落ちである。
私は、それを考えるヒントは新渡戸にあると思う。キリスト教徒の彼が植民地支配の尖兵をつとめたのは意外だが、キリスト教では野蛮な国に「文明」を広めることは善である。全世界を支配するのは同じ神だから、宗主国は神の福音を植民地に伝道しているのだ。新渡戸は建学の理念をマタイ伝の「地の塩」という言葉で語った。
このキリスト教の自民族中心主義は、膨張主義を動機づける一方で、国家を法的にコントロールする規範にもなっていた。それが法の支配もなく、軍をコントロールできない欠陥国家に移植されたために、とんでもないことになったのだ。
しかし戦前には、グローバルな開拓精神が日本にもあったことは重要だ。内向きの「空気」も、海外に行けば変わる。それは本書も紹介しているように、戦前に多くの日本人がアジアで活躍したことからも明らかだ。そこには岸信介も石原莞爾も含まれるが、彼らを国際人として再評価するとともに、それがなぜ失敗したのかを検証する必要があろう。