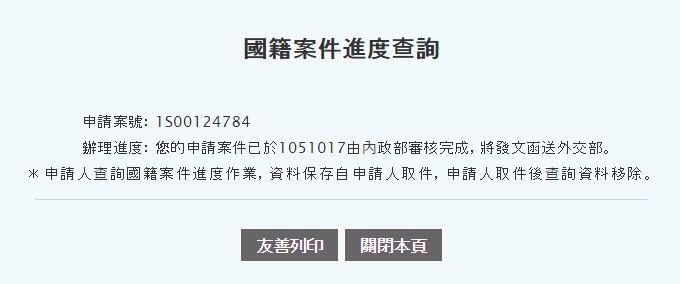各国の官僚には特徴がある。アメリカの官僚はフランクで、イギリスの官僚は貴族的だが、ブリュッセル(EU)の官僚は妙に学問的だ。政策の理論的根拠はくわしく説明するが、それがどう執行されるかは「各国政府の問題だ」となる。普通の官僚はその執行の部分をになっているから権力があるのだが、ブリュッセルにはないからだ。
Brexit(イギリスのEU離脱)は世界を驚かせたが、本書も指摘するようにイギリス人のブリュッセルに対する反感は根強い。EUの原型になったECSCが1951年にできたのは、武器の製造に不可欠な石炭と鉄鋼の生産を共同管理し、独仏の戦争再発を防ぐ軍備管理が目的だった(それがノーベル平和賞を受賞した理由だ)。
主権国家を超える超国家的な機関が各国政府に命令するEUは、政府の干渉をきらうイギリス人には好まれない。彼らが(肌の合わない)独仏と同じ舟に乗ったのは、アメリカという巨大市場に対抗するにはヨーロッパも市場統合する必要があるという経済的利益のためだった。この点で、戦争防止同盟としてのEUとは大きなずれがあった。
他方でEUは東欧の崩壊後に急拡大し、このずれは大きくなった。それを埋めるために工夫されたのが、著者のいうアラカルト欧州と2速度式欧州である。前者は市場統合には参加するがユーロは採用しないといった項目別のメニューをつくること、後者は東欧のように経済発展の段階に応じて市場統合の速度を変えることだ。
ところがアラカルト方式を要求して条件闘争をしていたイギリスが、その脅しだったBrexitを国民投票で決めてしまった。これは(離脱派を含む)ほとんどの人にとって誤算だったが、元に戻すことは不可能だ。しかしイギリスの騒ぎでEUのメリットがそのコストを上回ることが広く知られたので、これが連鎖反応を起こす心配はないという。
他方で、俗にいわれるようにEUが「ドイツ帝国」になる心配もない。よくも悪くもEUは民主的なので、ドイツは各国の調整役に徹している。むしろ国家を超える主権がないため、意思決定に時間がかかり、大きな決断ができない。ギリシャ問題はドイツの負担で乗り切ったが、難民問題ではメルケル政権が存亡の危機に立たされている。
カール・シュミットは「国際法とはヨーロッパ公法であり、キリスト教共同体を超える国際機関は不可能だ」と指摘したが、難民問題とBrexitはその共同体の中に大きな亀裂をつくってしまった。まして「東アジア共同体」などというのは笑い話にもならない。