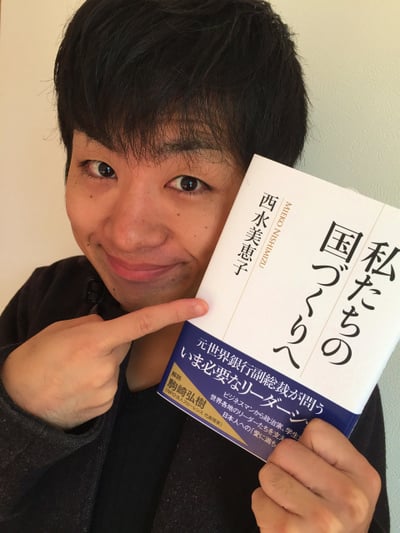
元世界銀行副総裁、西水美恵子氏の新作「私たちの国づくりへ」の解説文を、今回書かせて頂きました。
本当だったら買わないと読めませんが、今回は英治出版さんの許可も得て、無料公開。この解説を読んで読みたくなったら、こちらから!!
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N3TWLE4/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_2.JmybEDTCSC7
ーーーーーーーーーーー
解説
認定NPO法人フローレンス 代表理事 駒崎弘樹
あなたは、本書を手に取った時に、著者の名前を知らなかったかもしれない。
確かに著者は、誰でも名前を知っている人、というわけではないだろう。
しかし、彼女は、世界から最も尊敬さるべき日本人だと、私は思う。
【西水美恵子という人】
世界銀行元副総裁の西水美恵子氏。本書は文字どおりグローバル規模での仕事を行った彼女の、三作目の著作であり、他でもない我々日本人への愛に満ちた檄文である。
最初に彼女自身について触れたい。西水氏は世銀副総裁という超のつくエリートでありながら、いやなればこそ、開発途上国の最貧困地帯に自らホームステイして住民たちの生活を「体感」し、それを部下たちにも徹底して行わせた。
その徹底した現場主義から行われた世銀改革は、世界で最も有名な経営学者の一人であるP・センゲも著作でモデルケースとして取り上げたほど。
それは処女作「国をつくるという仕事」に詳しい。もともとは経済学者であった彼女が、貧困削減を使命とする世界銀行に入社した理由をこう語る。 エジプトを訪れたときのことだ。
——–
週末のある日、ふと思いついて、カイロ郊外にある「死人の町」に足を運んだ。邸宅を模す大理石造りの霊廟がずらりと並ぶイスラムの墓地に、行きどころのない人々が住み着いた貧民街だった。
その町の路地で、ひとりの病む幼女に出会った。ナディアという名のその子を、看護に疲れ切った母親から抱きとったとたん、羽毛のような軽さにどきっとした。緊急手配をした医者は間に合わず、ナディアは、私に抱かれたまま、静かに息をひきとった。
ナディアの病気は、下痢からくる脱水症状だった。安全な飲み水の供給と衛生教育さえしっかりしていれば、防げる下痢・・・。糖分と塩分を溶かすだけの誰でも簡単に作れる飲料水で、応急手当ができる脱水症状・・・。
誰の神様でもいいから、ぶん殴りたかった。天を仰いで、まわりを見回した途端、ナディアを殺した化け物を見た。きらびやかな都会がそこにある。最先端をいく技術と、優秀な才能と、膨大な富が溢れる都会がある。でも私の腕には、命尽きたナディアが眠る。悪統治。民の苦しみなど気にもかけない為政者の仕業と、直感した。
脊髄に火がついたような気がした。
————–
この「脊髄に火が」つく経験を心の基礎に、南アジアの元首たちや草の根の人々との時に取っ組み合い、時に抱きしめ合う日々を、彼女は過ごす。ムシャラフ・パキスタン大統領、マンモハン・シン・インド首相、クマラトンガ・スリランカ大統領、ブータンのワンチュク雷龍王4世・・・。
私を含め多くの人は、途上国というと、劣悪な住環境や貧困、腐敗した政治などを思い浮かべるのではなかろうか。よってオバマ大統領には憧憬の念を持っても、途上国のリーダーたちから学ぼうとは、思いづらい。彼らから学ぶことは、ないだろう。なぜなら我々は彼らより前に進んでいる、と。
全くの大間違いである。学ぶことだらけだ、と彼女は「国をつくるという仕事」の中で語る。何を?リーダーシップだ。文字通り命を賭けたリーダー達の生き様から、われわれは信じがたいほど多くのことを学べる。当然のようで気づいていなかった事実に、私は頭を殴られた気分になった。
【あなたの中に、リーダーはいる】
さらに彼女は、リーダーシップは、途上国の大統領が持っているだけではない、ということを次作「あなたの中のリーダーへ」で語る。
官僚的に部署同士で予算を奪い合い、机上の空論の融資計画を立てる世銀職員を変えるため、彼女はVIP(貧村没入計画)という、住み込み体験を始めた。
しかし「二の足を踏むものはまだいいほうで、「貧村や貧民街の視察を頻繁にしているから必要ない」と辞退する者や「貧しい国で育ったから時間の無駄」と意見する者などが、続出した。皆の不安は、自分の体験で知っていた。が、心を鬼にして「嫌なら部下とは思わない!」嫌々ながらも、重い腰が動き始めた」のだ。
「一日二十四時間、働かなければ死神が勝つ極貧の毎日。精神的な安定や、夢、希望どころか、自分のための時間さえぜいたくな中、貧困解消を使命とする世銀職員は、罪悪感に打ちのめされた。村と家族が抱える問題を自分たちで解決しようと自主的に動く情熱が芽生えた。(中略)
職場に戻ったチーム精神は、同僚に飛び火した。類は友を呼び、伝染病のように広がっていった。
しばらくして次年度予算会議の時が来た。毎年醜い予算奪い合いに徹底する部長らが「まず貧民の視点から援助戦略の大局を見直そう」と提言し、部門を越えた会話が始まった。」
そう、「進んだ自分たちが、劣った彼らを援助する」という価値観が骨の髄まで染み込んだ世銀職員でも、貧民たちと起居を共にするという「体験」を経ることで、変革のリーダーシップを取れるようになっていったのだ。
何も大統領に、世銀総裁に、会社社長にならなくても、我々は、リーダーになれるのだ。
【すぐそこにいる、リーダー達】
そして西水氏は三作目の本書で語りかける。読み手の背中に手を置き、穏やかに。「動きなはれ!」と。
その方法は、彼女らしい。自らがその場に身を置き、そこで見たリーダーシップの具体例を一つずつ挙げるのだ。
「緑の真珠」気仙沼大島の「おばか隊」
避難所で冷静に整然と列をなす被災者たち
刺し子をつくる、大槌の女性たち
「俺は負げねぞ!」と気仙沼で養殖業を営む若者
自発的に救援物資の配送を始めたヤマト運輸の社員たち
集落丸ごとの宿「集落丸山」の男衆女衆
岐阜県馬瀬の地元リーダーたち
地域に住む普通の人たち。彼らが震災や過疎化の中、危機感を持ち、立ち上がり連帯し、新しい地域がつくられていく。政治家や行政が私たちを救ってくれるのではなく、私たちが私たちを救う。そういう営みが、そこかしこに実はあるんだぞ、気づけ、と彼女は語るのだ。
【小さな体験によって変わった私の人生】
個人的な話をしたい。私は熱を出した子どもを預かる「病児保育」や、保育園では預かれない医療的ケアのある子に「障害児保育」を提供するNPOを経営している。社員数は400人を超え、ニューズウィーク誌からは「世界を変える100人の社会起業家」に選ばれたりもしている。
そういうとリーダーシップの塊のように思われるが、自分がこうした社会事業に踏み出したきっかけは、ちっぽけなものだった。ベビーシッターをしていた母が、私に愚痴ったのだ。「お気に入りのお客さんの双子のママが、仕事を失った」と。理由は、「子どもの看病で会社を休んだから。」保育園は熱を出した子は預かれないので、看病で休んだ母親に会社が激怒し、事実上の解雇になった、と。
そんなバカな、と思った。子どもが熱を出すなんて当たり前だし、親が看病するのも当然。しかし、そんなことで職を失う人がいる。この21世紀に。世界第2位の経済大国で。馬鹿げている。
私にとっての、「脊髄に火がつく」経験だった。
そこから、大学卒業後にフリーターとなって、日本初の訪問型病児保育のNPOを立ち上げていったのだった。
熱を出した子どもの家に保育者を派遣し、保育者は病院にも連れて行き、保護者が帰るまで、安全に保育を行う。WEBシステムで24時間予約が可能で、ほぼ100%依頼には応える。こうした仕組みが、首都圏5000世帯以上の働く家庭を助けている。
その後、社員の一人が子どもを保育園に入れられなかったことから衝撃を受け、「おうち保育園」というこれまでなかった9人のミニ保育所をつくった。それが政府に採用され、小規模認可保育所という制度ができあがり、2016年現在、全国2600ヶ所に広がっている。
さらに、医療的ケアが必要な重い障害のある子どもたちが、ほとんど保育園から門前払いにされているという事実を知り、日本で初めて、医療的ケア児を長時間保育できる「障害児保育園ヘレン」を開園した。それは後に、障害者総合支援法の改正に繋がっていく。
どれも、ふとした「心に痛い」体験から、「脊髄に火がついた」ことによって、始まっていった。
【痛みは行動の糧に】
被災や近しい人の死。そうした大いなる悲劇だけが、我々を奮い立たせるのではない。ちょっとした痛み。心の棘のようなものが、一歩を踏み出すきっかけになることもある。
友人の曽山恵理子さんは、普通の働く母親だった。地元の友人たちが次々と「保育園に落ち」て、待機児童を抱える様を見て、これはおかしいと思った。心に棘を感じた。役所に文句を言ってやろう、と立ち上がった。ご自身のお子さんは待機児童ではなかったにもかかわらず。
そうして2013年、役所の前で仲間たちとベビーカーをひいてデモを行ったら、メディアが殺到。杉並区は批判を浴び、慌てて認可保育所の増園計画を打ち出したのだった。俗に言う、杉並区保育園一揆である。
身近な人が困っている。そうしたちょっとした心の痛み、棘が、我々の背を押し、あれよあれよと現実を変えていく力になることは、あるのだ。
痛みは我々の行動の糧にもなる。変革の起点にもなる。これは希望だ。我々が日々感じている、困った、かわいそうに、おかしいよ、なんとかしないと、こうした痛みは、ともすれば体験したくないし、できれば降りかかってほしくはない。
しかし、しかしだ。
こうした心の痛みが、普通の我々を立ち上がらせ、現実を変えることに「使える」のであれば。我々に降りかかるものへの見え方は、受け止め方は、全く変わるのではなかろうか。
【さいごに】
我が国は2050年には高齢者が人口の4割を占める超高齢社会を迎える。一方で彼らを支える労働人口は今の3分の2に激減する。持続可能かどうか、答えはない。
なぜなら、我々が人類で初めて、こうした超高齢社会を迎えるからだ。
昔であれば欧米に視察に行けば知り得た答え。しかし官僚も政治家も、どうすれば良いかの答えは持っていない。この社会に生きる、我々が答えを出すしかない。そう、あなたが、あなたの持ち場でリーダーとなって、1ミリでもこの国を良くさせなければならないのだ。
でなければ我々の愛しい子ども達に、私たちは謝らなければならなくなる。「なぜあの時、変えてくれなかったの」という問いに、沈黙で返すしかなくなる。少なくとも私は、私の子ども達に、自分はベストを尽くした、と言いたい。だから私の持ち場で、小さな全力を尽くそうと思う。
この本を読み終えた皆さんの心の中で、わずかでもリーダーシップの鼓動が響くことを願う。皆さんが日々感じる痛みを抱きしめ、そこから湧き出る感情を糧に、あなたなりの変革をあなたの半径5メートルで生み出してくれることを。
きっと西水氏も、そう願っているに違いない。
編集部より:この記事は、認定NPO法人フローレンス代表理事、駒崎弘樹氏のブログ 2016年11月21日の投稿を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は駒崎弘樹BLOGをご覧ください。













