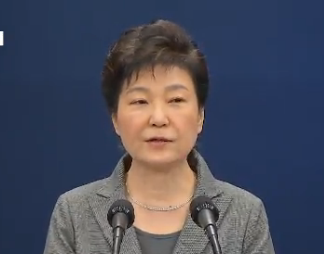「千秋楽は民を撫で。万歳楽には命を延ぶ。相生の松風。颯々の聲ぞ。楽しむ。颯々の聲ぞ。楽しむ」
謡の稽古を始めて2年。心を落ち着かせたい時は、『高砂』のきり(最後の部分)を口ずさむようになった。何しろ縁起が良い。
能に興味を持つようになったのは3年前。好きだった落語、演劇、オペラの延長線上で、妻と一度、能を観に行ってみようという話になった。番組は『翁』に続き『竹生島』。琵琶湖に浮かぶ島なので、滋賀県で育った私にとっては馴染みやすい演目かと思いきや、船(部隊に置かれた白い枠のみ)に乗って島に渡る漁師と女人が、数分間(私にはもっと長い時間に思われた)、体を前後に揺するだけで動かない。強烈な眠気に襲われた。周りを見ると、ある人は謡本を観ながら、ある人は明らかに眠気と必死で戦いながら能舞台を凝視している。能楽師と観客が織りなす異様な緊張感は何なのか。理解できなかっただけに、強い関心を抱くようになった。
縁というのは不思議なものだ。その数週間後、能楽師・森田流笛方の槻宅聡氏のお話を聞く機会があった。少数の勉強会だったので、能を観て感じたことを率直に質問することが出来た。
槻宅先生曰く、
「能楽が誕生して700年、ほとんど形を変えていない」
同じ伝統芸能の中でも、歌舞伎は時代に合わせて形をかえてきた。スーパー歌舞伎、コクーン歌舞伎などは誰でも取っ付きやすいのに対し、能は敷居が高い。
「能楽とは、人間に聞かせるものではなく、神に捧げるものである」
そう言えば、能楽師は最初も最後も観客に対して礼をしない。
「シテ方は一旦、能舞台に出れば一つの演目を何があってもやりきる責任がある。動けなくなった場合に備えて後見が控えている」
高齢の能楽師が能舞台に立つ姿には、強烈な気を感じる。舞台と観客の間の緊張感を媒介するのはそれだろう。
「まれに、シテに憑依することがある」
能面を被るとほとんど視界がない。あえて厳しい環境を課してシテ方は舞うのだ。何百年も使い続けられている能面を被ると、何かが乗り移る?もしかしたらあるかも知れない。
「ワキ方が、死んだシテ方を呼び出して弔うものがほとんど。夢と現を行き来するわけだから、眠くなるのは自然なこと。ただ、本当に寝てはいけない」
なるほど。眠気と戦いながら見るのが能の正しい見方だったのか。
話を聞いてまずます興味が湧いてきた。槻宅先生がクリスチャンであることにも興味をそそられ、弟子入りを考えたが、笛などやったことない自分が続けることができるか、自信がない。ふと頭に浮かんだのが妻のことだ。妻は、三島の夏祭りの山車で、しの笛を担当している。私よりは、素養も時間もありそうだ。帰宅して強く勧めると、妻は稽古に通うようになった。
不思議な縁が続いた。その数週間後、趣味にしている落語の会でワキ方宝生流の安田登氏とお会いした。近く、謡の素人稽古を始めて開くことにしたという。しかも、槻宅先生とは友人とのこと。私は、40歳になった直後に、安田先生の書いた『身体感覚で論語を考える』を読み、影響を受けていた。「不惑」とは「惑わない」ことではなく、「或に囚われない」(孔子の時代は、「心」という文字はなかったというのがその理由)という意味だというのだ。40歳にして、新しいことに挑戦してみという気持ちになったのは、その安田先生の本との出会いがあった。謡なら出来るかもしれない。そういえば、どこかで毎日演説をしている仕事柄、声は出る。その場で稽古に参加したいと申し出た。
謡を始めて2年。能には、古事記、平家物語、源氏物語、伊勢物語、そして数々の和歌など、日本文化が凝縮されている。わが国の文物を編集し、能に仕上げた観阿弥、世阿弥は天才だと思う。幕府の庇護がなくなった明治時代、日本文化が否定された戦後も守り抜いた先人たちの苦労は凄まじいものだっただろう。
謡を学ぶことは、庶民にとって教養だった。戦後も、魚屋には魚を買ってもらった時に客に謡い、大工さんは建前の時に謡う風習があったという。戦後も青年団を中心に謡は庶民の教養として継承されてきたが、青年団活動の衰退と共に廃れてきた。現代の日本文化の象徴であるカラオケの普及がとどめを刺したというのも皮肉な話だ。
室町、戦国、江戸時代と能が栄えた理由の一つは、武士が庇護したことにあった。謡をやってみると、その理由がよく分かる。シテ方、ワキ方、囃子方(笛、小鼓、大鼓)、そして地謡(謡の合唱)が登場する能には指揮者がいない。「申し合わせ」と称するリハーサルを一度やるだけで本番を迎える。あとは「呼吸」なのだ。武士にとって、味方同士が戦場で呼吸が合わなければ、即、死を意味したわけだから、能の稽古には真剣に取り組んだのだろう。政治家同士、官僚と政治家、そして国民と政治家の呼吸が合わなければ、政治も前に進まない。奥が深い。
能の主流はシテ方の観世流で、私が稽古しているワキ方宝生流はマイナーな存在だ。ちなみに、夏目漱石や石川啄木はワキ方宝生流を謡っていたので、かつては普及していたようだが、今は少数派になり、謡本も稽古もマニュアル化されていない。もしくは実際は逆に、マニュアル化されなかったから少数派になったのかも知れない。自ずと師匠の口伝を大切にすることになり、師匠と弟子の間に理屈を超えた強固な人間関係が形成される。
先日、安田登先生門下の「流れの会」、槻宅聡先生門下の東京乱声会などの合同発表会が開催され、師匠と稽古仲間の地謡をバックに『高砂』を謡うという無謀な挑戦をすることとなった。笛は妻が担当し、発表会のトリを務めた。政治家になって17年。大概のことではビビらなくなったが、能舞台に初めて立ち、経験したことがない緊張感を味わった。それぞれの分野で活躍している稽古仲間なのだが、みんな同じ気持ちだったようで、打ち上げは大いに盛り上がった。
結婚式で『高砂』を長老が謡っていたのは、いつごろまでだろうか。発表会の余勢をかって、先日、秘書の披露宴で謡おうかと考えたが、招待状に同封されてきた紙には「挨拶は3分以内でお願いします」とあり、自重することにした。考えてみると、私の下手な謡を聞いて、能などもうこりごりだと思われるのはまことにまずい。
幾多の危機を乗り越えて継承されてきた悠久の歴史を思うと、今を生きる我々が閉ざすわけにはいかないと思う。世界でも最も古い伝統芸能を継承するために、知り合いを能の鑑賞に誘うという、ほんの小さな貢献するのも悪くない。皆さんも是非。
編集部より:この記事は、衆議院議員の細野豪志氏(静岡5区、民進党)のオフィシャルブログ 2016年11月29日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は細野豪志オフィシャルブログをご覧ください。