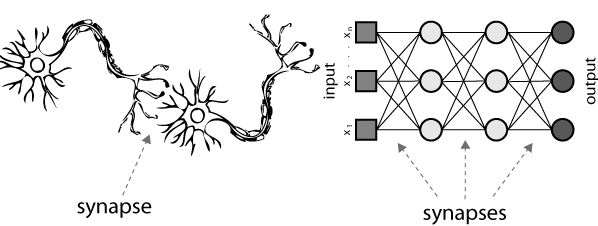先日、映画「海賊とよばれた男」をようやく観た。出光創業者・出光佐三氏をモデルにした国岡鐵造の一代記を百田尚樹氏が描いた原作は、刊行時に読んでいたので、「あの壮大なスケールの物語をどこまで映像化できるのか」と興味津々ではあったが、2時間余りの作品に詰め込んだ分、やや駆け足な描き方になったのは仕方なかったろうか。
とはいえ、「ALWAYS三丁目の夕日」でおなじみの山崎貴監督らが手がけたVFX技術に迫真性があり、なんといっても主演の岡田准一氏の熱演が見事だ。物語の山場が、主人公の壮年期とあって、実は原作を読んだ時には、渡辺謙氏が年齢的にも適役のように感じていたのだが、還暦を迎えた国岡役を、岡田氏は声色も含めて円熟味あふれる一代の起業家になりきり、オーラを存分に放っていた。
原作はベストセラーになったが、「士魂商才」に代表される彼のビジネス哲学、日章丸事件をハイライトとする冒険的な決断と行動力、石油メジャーや石統(石油統制配給)のような強大な相手に一歩も引かない強さ、あるいは原作者が百田尚樹氏ということもあって、愛国的な生き様が支持を得たわけだが、経営者としての凄みという視点で見ると、映画の前半で印象に残ったシーンがある。

門司での創業時(出光サイトより引用)
福岡・門司で創業した国岡商店(モデル・出光商会)は、日邦石油(同・のちの日本石油=現JXエネルギー)の特約店として石油の販売を開始する。出光の社史にもあるように、当初は炭坑や工場への機械油の売り込みに苦戦するも、対岸の下関の漁船への燃料油の売り込みを画策する。しかも、それまで割高だった灯油ではなく、安価な軽油への切り替えにより、漁師たちが喜ぶという顧客視点に基づく発想だった。
しかし、石油業界では草創期ながら早くも販売エリアのしきたりが業界の慣行として定着していたが、国岡はある奇策に打って出る。伝馬船を使って、漁船に横付けし、海上で直接販売する。たちまち漁師たちに国岡商店の評判を呼ぶことになるが、当然、下関の特約店は“荒らし”行為に激怒し、日邦石油の下関支店に国岡をなんとかするように抗議。国岡は下関支店の榎本支店長に呼び出されてしまう。
このときの国岡の言葉が「らしさ」を体現している。映画の台本が手元にないので、原作でその場面をベースにしたと思われるところを引用しよう(一部中略あり)。
下関の支店長は榎本誠だった。榎本は鐵造を呼んだ。
「君が下関の特約店の協定を破って商売をしてるという抗議が殺到しているんや」
「私は協定を破っていません」
「君は門司の特約店や。下関で商売したら協定破りやろ」
「私は下関で油は売っておりません。私が売ってるのは海の上です。船の上です。その油も門司から運んだものです。それに門司側の海で売っています。協定は破っておりません」
榎本は苦笑いした。国岡の言い分は強引すぎるものだった。(略)しかし榎本は黙認することにした。この気骨ある若い男の芽をこんなことで摘んではならない、と思ったからだ。

“海賊”の異名をとった出光佐三氏(出光サイトより引用)
映画では、岡田氏演じる国岡がロジカルに熱弁を奮っているので映画を未見の人は確認してもらいたい。原作にはないが、映画では、彼の去った直後、支店長に店員が「言っていることは間違っていない」という旨のことを述べて感心する。私もこの店員と同じことを思っていた。顧客ニーズを顧みない、官製、あるいは業界の自主規制は、いつの時代もある。そうした規制の矛盾に気づいたとしても、業界にはびこる日本的な空気を読んで、普通の経営者ならリスクをとらない。
しかし、国岡は、燃料費を抑えたいという漁師たちのニーズと、自社の業績向上を最優先に空気を読まずに海上販売を決行した。そして、それが国岡商店の転機となる。その後の満州進出につながる地固めとなったのは史実の出光が示す通りだ。その満州進出もそうだが、空気を呼んでいては“ゲームチェンジ”はできない。池田信夫が孫正義氏を引き合いにするように「空気を読まないことがイノベーション」の可能性を広げることを、この映画でも確認させられた。
さて、国岡商店のモデルになった出光石油といえば、昨今は昭和シェルとの経営統合を巡り、10年前の上場時に経営の一線からは退いたはずの創業者一族が反対してお家騒動になっている。拙著「蓮舫VS小池百合子、どうしてこんなに差がついた?」(ワニブックス)では政界での情報戦を取り上げたが、M&A関連のそれも熾烈だ。来年もビジネスメディアを巻き込んだ仕掛け合いが続くのだろう。
上場時までは、「定年無し、首切りなし、出勤簿無し、労働組合無し、給与公示がない、社員が残業手当を受け取らない、給与は労働の対価ではない」などの “出光の七不思議”が言われたが(近年は定年制導入など変化)、社風として根っこで息づく「出光佐三イズム」が、21世紀のグローバル経営の荒波にどう揉まれていくのか、“海賊の子孫”たちと現経営陣との攻防の行方と合わせ、今後も興味深く観察したい。






![海賊とよばれた男 単行本 上下セット [単行本] [Jan 01, 2012] 百田 尚樹 [単行本] [Jan 01, 2012] 百田 尚樹](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51lki85ll9L._SL160_.jpg)