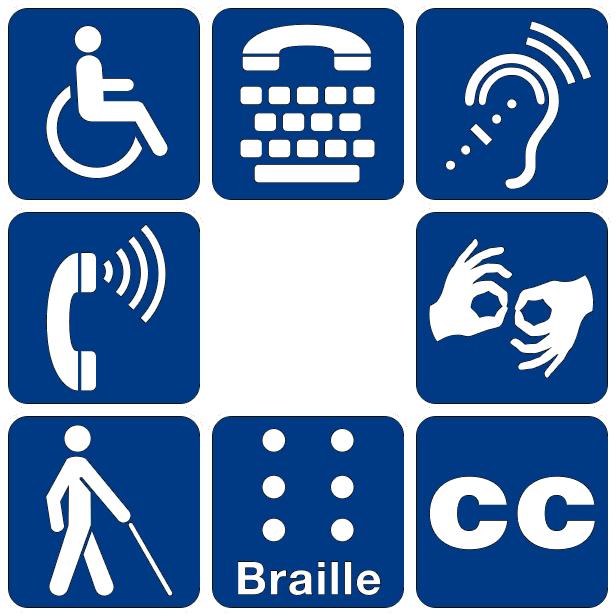旧ソ連のユーリイ・ガガーリン大佐は1961年、人類初の宇宙飛行士となったが、ボストーク1号から眺めた地球が「青かった」と述べたことが伝わると、われわれは感動を覚えた。同大佐は地球には国境のないことを確認した最初の人間でもあった。冷戦時代だった当時の世界の人々には計り知れないインパクトを与えた。

▲火星から見た地球と月の画像(NASA公式サイトから)
米航空宇宙局(NASA)が配信した火星から地球と月を撮影した映像はそれ以上のインパクトと神聖な感動を人類に与えるかもしれない。地球を2億キロメートル以上離れた火星から撮影した画像だからだ。
NASAは6日、火星を周回する無人探査機「マーズ・リコネサンス・オービター」から高解像度カメラで撮影した地球と月の画像を公開した。撮影は昨年11月20日で、火星と地球との距離は約2億キロ。赤茶色の大陸はオーストラリアだという。
当方の第一印象は、広大な暗闇の宇宙に浮かぶ地球、その地球周囲を公転する月が実際に存在している、という強烈な追認だ。地球上で生きていると、自分が宇宙の無数の惑星の一つ、地球で生きているという事実を忘れてしまう。地球は太陽系の惑星の一つとして、自転し、公転し、存在し続けている。これは天文学の初歩的知識だが、その事実を画像でみると圧倒されてしまうのだ。
地球上では今なお、多くの紛争が続いているが、それらは宇宙的視野から見たならばどのような意味があるのか、ウクライナからクリミア半島を奪ったとしてもどれほどの価値があるのか。シーア派とスンニ派のイスラム教内の宗派間闘争に意味があるのか。富を蓄えることが人生の目的となり得るか、等々の思いが湧き、心は苦しくなってくる。
ガガーリン大佐は人類初めて地球を地球の外から観察した。21世紀の私たちは直接ではないが、火星から地球と月の姿を観察できる時代的恩恵を享受している。
自分がどのように映っているかに関心が高いセルフィー(自分撮り)世代にとって、自分から2億キロ離れた火星から見た地球と月の画像に考えられないほどの新鮮さを覚えるのではないか。自分から1メートルも離れていないセルフィーでは笑顔も書割も画像調整が可能だが、2億キロ離れたところからの画像は、地球と月の明るさを同一程度に処理しているだけで、事実だけを映し出している。
地動説が出てきた時、天動説を信じてきた人々はその世界観、人生観に少なからずのインパクトを受けた。時代の経過と共に、自分たちが宇宙の無数ある惑星の一員に過ぎないことも学んでいった。そして2017年、火星から宇宙に浮かぶ地球を眺めている。
ところで、私たちが惑星の中でも小さな惑星・地球の住人に過ぎないことを甘受する時、人間の尊厳性はなくなるだろうか。なくならないとすれば、どこに人間の尊厳性、価値を探すべきだろうか。
ひょっとしたら、2億キロ先からの画像も無人探査機を利用しただけで、1メートル離れたところから撮影するセルフィーと同じではないか、という考えが出てきた。無人探査機はセルフィー用延長アームだ。
私たちは常に自分に拘り、自分は誰かを問い続けている。地球から2億キロ離れていても、最も関心があるのは自分であり、自分が住む地球の姿ではないか。火星探査も火星を知る目的以上に地球の生い立ちを知るうえで大きな意味があるといわれる。自己の存在、命を限りなく慈しむ。そこに人間の尊厳性が潜んでいるのではないか。釈迦の「天上天下唯我独尊」の世界を思い出す。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2017年1月11日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。