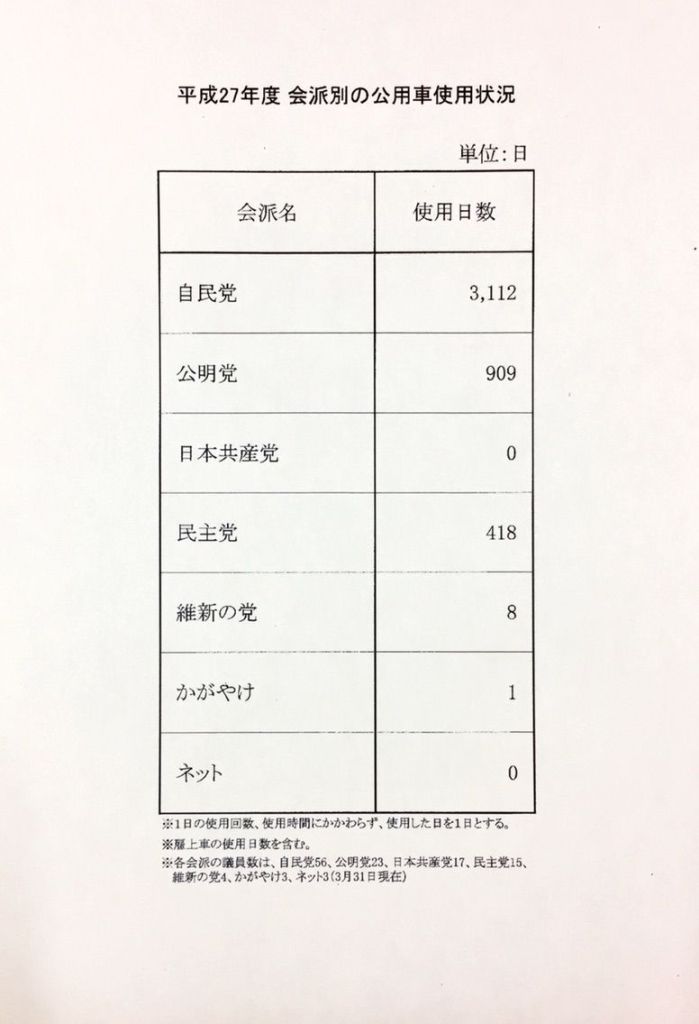前回のブログで山尾議員の改憲案について書いた際、「憲法裁判所」設置の改憲案は危険ではないか、と書いた。
英米法思想の強い影響を受けた日本国憲法体制で、アメリカ型の付随的違憲審査制をとっているのが、現在の日本の制度である。憲法裁判所制度は、ドイツやフランスを代表とするヨーロッパ大陸諸国で採用されているもので、判例法重視の英米法の伝統にはなじまない。拙著『集団的自衛権の思想史』や『ほんとうの憲法』で論じたが、本当の日本国憲法典はアメリカの影響が強いものだが、その解釈方法を独占的に論じてる日本の憲法学ではドイツ国法学的な伝統すら根強い。憲法典と憲法学の間のギャップは、憲法裁判所の導入によって、劇的なまでに白日の下にさらされることになるだろう。
独裁的な権限を持ちうる憲法裁判所の設置は、国政を混乱に陥れいれる危険性をはらむ。導入するのであれば、十分な議論と準備と管理が必要だ。たとえば裁判官の選定にあたっては、万が一にも、「憲法学者だから」、といったことを理由にした安直なやり方があってはならない。客観的な評価に耐えうる業績を持ち、人格的に高潔であることが条件になるのは当然だが、さらに、政治的偏向がない人物であることも、極めて重要な要件となる。
枝野氏と長谷部教授のダブスタ:枝野氏指導の憲法学者小嶋氏の補足
各裁判官推薦者の能力・人格・政治的偏向などを徹底的に審議検討し、議決を経て正式候補を認定する手続きを確保するべきだろう。国民審査をへるまでは裁判にあたってはいけない、などの規則を作っておくことも大切だ。
現在二つの憲法学会の長を同時に務める長谷部恭男教授は、次のように述べる。
「法律の現実を形作っているのは法律家共同体のコンセンサスです。国民一般が法律の解釈をするわけにはいかないでしょう。素っ気ない言い方になりますが、国民には、法律家共同体のコンセンサスを受け入れるか受け入れないか、二者択一してもらうしかないのです。」 (『朝日新聞』2015年11月27日)
憲法裁判所の場合、「法律家共同体」どころか、「憲法学者共同体」に、圧倒的な権限を与えられるかもしれない。現行憲法の三権を凌駕する超越的権限を持ちうるとすれば、現在の社会秩序を転覆させる革命的な独裁主義を内包した制度となる。設立されれば、多方面に甚大な影響を与えるだろう。
「安保法制を廃止せよ」、「アベ政治を許さない」、といった時局的かつ党派的な関心だけで、独裁制に道を開く制度を歓迎してよいのか、よく考えてみるべきだ。
私の見解を述べれば、どうしても必要でなければ、そのような危険な制度は、ないほうがいい。私は、山尾議員の改憲案に反対する。
*****
なお上記の点についてさらに強く思ったのは、前回のブログ掲載の後に届いたコメント群を見てである。
国際法と憲法の話をすると、必ず紋切り型のコメントが届く。何度も聞いたことがあるパターン化された紋切り型である。日本の法学教育では、よほど徹底して紋切り型コメントに関する教育がなされているらしい。それはあくまでも司法試験受験「法律家共同体」の中で徹底されているにすぎない紋切り型だろう。しかしその「共同体」に、独裁的な権限が与えられるとどうなるのか。憲法裁判所の行方も不安にならざるをえない。
何度も何度も個別に紋切り型コメントに対応するのは、率直に言って煩雑だ。以下にまとめて書いておき、今後はこのブログを参照するだけにしておきたい。
1.「憲法優位説が学会の通説だ」
こういう紋切り型コメントを発する人に、「国際法優位説など主張していない」と何度言っても、聞いてくれない。こちらが面倒になって話をやめるまで、「憲法優位説」という言葉を呪文のように唱え続ける。要するに「憲法学は天上天下唯我独尊」だ、という態度なのである。
「殺人罪なんていつでも無にできる」と、「憲法優位説」にもとづいて刑法学者にケンカを売る人いないだろう。ところが、ひとたび「国際法には自衛権の規範がある」、といった話をすると、すぐに怒った人が現れて「そんなことを言うのは国際法優位説だ、しかし学会通説は憲法学優位説だ、したがってお前は間違っている」、という反応になる。
日本国憲法98条2項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と定め、条約の遵守を求めている。憲法41条で「国権の最高機関」と定められている国会が審議して批准した条約で、「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない」(条約法条約27条)という規範も、日本は遵守している。
国内法体系と国際法体系を矛盾のないように「調和」させる努力をするのが、憲法典の要請である。すでに成立した規範体系は、そのような努力の結果だという前提をかけるのが、日本国憲法典が予定している秩序観である。
これは対立が生じたときにどちらが優位するか云々といった類の抽象的法理論の問題のことではない。憲法典が持っている国際協調主義の理念を否定するのは、端的に、反立憲主義的である。
2.「憲法学が正しい根拠は、憲法学の基本書だ」
憲法学の通説が偏向しているのではないか、という指摘をすると、すぐに怒った人が現れて、「お前は間違っている、なぜなら権威ある憲法学の教科書にこう書いてある、大学の憲法学の講義でこう聞いた・・・」という話が始まる。
「いや、私が言っているのは、まさにあなたが引用しているその基本書が偏向しているのではないか、ということなのですが・・・」と言っても、全く聞いてくれない。
「統治権」やら「国家の自然権的自己保存」やら、ドイツ観念論丸出しの議論は、私に言わせれば、実定法的根拠を欠いた単なる漫談である。ところが、そう言っている私に対して「何を言っているんだ、ホラこの教科書も統治権と書かれている、ホラこの教科書にも統治権と書かれている」などといったことを延々と羅列してくる方もいる。
戦後日本の立憲主義の理解への疑問:水島朝穂教授の私への攻撃を見て
「あのお・・・、貴方が引用されている無数の教科書類は全て、『実定法上の根拠がない話が憲法学の伝統になっている』、という私の指摘を補強するだけなのですが・・・」と私が言っても、全く聞いてくれない。
判例を引いてくるのは重要な法律論である。憲法学会の通説にも、それなりの意味はあるだろう。だがそのことと、「お前は間違っている、なぜなら憲法学の基本書の内容がお前の言っていることと違うからだ」、と主張し、異端者を排除する態度を徹底することとは、違う。「憲法学者の基本書は絶対無謬の聖書のようなものであり、何人も逆らうことが許されない」といった「二者択一」主義は、独裁主義を用意する危険な考え方だ。
3.「統治行為論だから最高裁は信用できない」
日本の裁判所は「統治行為論」を採用している、だから信用できない、という話が、驚くべきほどにまで流通している。憲法学から発しているものだ。しかしたとえば1959年砂川事件最高裁判決を、「統治行為論」だ、と断定し、「だからダメだ」と結論づけるのは、真面目な議論と言うよりも、政治的イデオロギーで偏向した議論だと言うべきだろう。
枝野代表の説明責任を果たしてほしい:砂川事件最高裁判決を読む
4.「戦前の復活だ」
日本には、半世紀以上にわたって「戦前の復活」の予言がなされ続けている。世の中のどんな事象を見ても「戦前の復活」につなげるのである。「戦前の復活」論は、いわば紋切り型思考のチャンピオンだと言ってよい(拙著『ほんとうの憲法』第3章参照)。
結論を「戦前の復活」と決めたうえで、そこに至る道筋だけを競い合うのは、いわば夏休みの宿題コンテストといった類のものだ。「僕は、緊急事態条項がナチス・ドイツの復活だ、という議論で戦前の復活を予言してみました」、「僕は、安保法制が徴兵制を必然的にする、という議論で、戦前の復活を予言してみました」、「僕は、特定秘密保護法案が『いつか来た道だ』、という議論で戦前の復活を予言してみました」、「僕は、篠田英朗が三流蓑田胸喜だ、と言うことで戦前の復活を予言してみました」・・・。
「コンテスト」は、仲間内で行うだけなら無害なのだが、具体的な他者を否定したいという政治的意図で開催されることも多いので、質が悪い。
しかも国際的には標準とされている話まで、日本では「戦前の復活」と言われることが多い。日本以外の国々では、「戦前」ばかりが流通しているようだ。戦後世界を生きているのは、世界最先端の憲法を持つ日本だけのようである。壮大な盲目的民族主義の物語だ。
5.「お前は従米義者だ」
こういった腑に落ちないやり取りが続いていってしまう社会構造の問題の核心にあるのは、日本人が持つアメリカへの屈折した思いだろう。
本来、戦前の復活だけを警戒するのであれば、満州事変などで悪用された個別的自衛権のほうを警戒しなければならない。集団的自衛権は、枢軸国を打ち破った連合国側のドクトリンだ。それがいつの間にか話がすりかわって、個別的自衛権=善、集団的自衛権=悪、になってしまうのは、1960年代末のベトナム反戦運動や学生運動の体験に過剰な思いれがあり、その思考枠組みにとらわれているからだ。したがって私は、集団的自衛権違憲論を、団塊の世代中心主義と呼んでいる。
以前のブログで「長谷部恭男教授の立憲主義は、集団的自衛権違憲論を説明しない」、と書いた。それでは何が集団的自衛権違憲論を証明するのか。反米主義である。

長谷部恭男・早大教授(日本記者クラブサイトより:編集部)
反米主義を感覚的に事前に共有している人々の間では、集団的自衛権違憲論は、論証抜きで広まる。そうでない人々の間では、広まらない。
もともとベトナム戦争に反対する運動が巻き起こっている中で沖縄返還の離れ業を達成した談合政治の時代の政治家たちが、「集団的自衛権は違憲なので、仮に国際法的には行使している状態があっても、憲法的にはやっていない」、という詭弁を作り出した。1960年代末以降の冷戦後期の思潮を反映した反米主義者と親米主義者の妥協の産物が、集団的自衛権は違憲だ、という物語であった(拙著『集団的自衛権の思想史』参照)。
今日でも長谷部教授の議論で、集団的自衛権を違憲論の基盤になっているのは、アメリカの戦争に巻き込まれたくない!、といった情緒的な話である。「自国の安全が脅かされているとさしたる根拠もないのに言い張る外国の後を犬のようについて行って、とんでもない事態に巻き込まれないように、あらかじめ集団的自衛権を憲法で否定しておくというのは、合理的自己拘束」(『憲法と平和を問い直す』162頁)だという。
それでは、日米安保条約の廃棄を求めるのだろうか。よくわからない。「憲法学に仕切らせろ」と登場してくる場面と、「ここは沈黙しておこう」の場面は、現在、完全に憲法学者の裁量に任されている。しかし憲法裁判所裁判官になったら、そのような態度は許されない。
憲法裁判所は、日米同盟違憲の宣言に踏み切って国制に大混乱をもたらすか、そうでなければ自己矛盾を抱えて崩壊する運命だろう。
アメリカの戦争に巻き込まれたくないなら、政策判断で、巻き込まれないようにすればよい。なぜそういう素直な話ができないのか。いちいち憲法を曲解して包括的な言い方で禁じてもらうような話ではない。
私はイラク戦争は国際法に反する行動だったと考えている。繰り返しこういった話は出てくるだろうと思い、2003年前後の著作で、はっきり文字にして、その見解を記録に残しておいてある(たとえば拙著『平和構築と法の支配』[2003年])。在外研究で米国滞在中の2002年には、反戦デモにも参加していた。だからこそあえて言う。イラク戦争は個別的な事例だ。アメリカは永久に邪悪な存在だと断定する根拠にはならない。「集団的自衛権は違憲だということにして、アメリカの戦争に巻き込まれないようにしよう」、という姑息なアイディアは、日本の将来の世代に不当な制約をかける無責任行為だ。
国際標準のやり方は、「国際法にしたがってアメリカの今回の行動は違法だと考える」といった議論を行うことだ。そのうえでイラクの戦後復興に協力しても、決しておかしくない。そういった議論や行動の積み重ねが、より良い国際秩序の形成への努力として評価される。
議論に参加する度胸を持たず、ただ、「国際法のことはわかりません、ただとにかくうちの国の憲法で禁じていることは、日本は何もできませんから、その点だけよろしく」、といったことだけ繰り返そうとするのは、あまりにも無責任である。
これから国際社会で活躍する甚大な可能性を持つ若者に、そういった無責任を強いるのは、罪深い。そのような姑息な反米主義を若い世代に強いるのは、日本という国を将来にわたってガラパゴス化させ、停滞させる行為でもあると思う。
編集部より:このブログは篠田英朗・東京外国語大学教授の公式ブログ『「平和構築」を専門にする国際政治学者』2017年12月1日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。