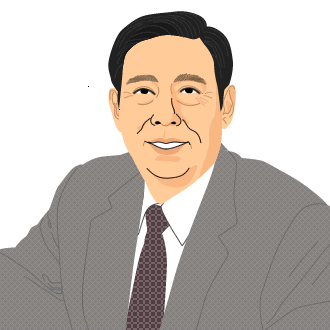英国のNHS(国民医療制度)公式サイトより:編集部
(英国の邦字紙「英国ニュースダイジェスト」の筆者コラム「英国メディアを読み解く」に補足しました。)
英国のNHS(National Health Service)こと「国民医療制度(国民保健サービス、と訳されることもあります)」が先月、創設から70周年を迎えました。税金で運営されているため、英国に住む人は基本的に無料で医療サービスを受けられます。
社会を構成するすべての人々に一律の医療サービスが無料で提供されるようになるまでには、どんな経緯があったのでしょう?
「National Health Service」という言葉を最初に使ったのは、英北西部リバプールのベンジャミン・ムーア医師だと言われています。1910年出版の著作の中で言及し、1912年には「国家医療サービス協会」を立ち上げました。
NHS発足前は、病気になったら自分で医療費を払うのが原則でした。貧困者が治療を受けるのは容易ではなく、いったん職を失えば、路頭に迷う可能性もありました。
1911年、転機が訪れます。自由党政権のデービッド・ロイド=ジョージ財務相の主導で、「国民保険法」が成立したのです。政府、雇用主、被雇用者が保険料を拠出することで、疾病時に医療費を負担し、失業時には給付金を支払えるようになりました。
当時は社会福祉というと「貧困者など一部の人に慈善で与えられるもの」「貧困度を測り、必要な人にだけ提供するべき」「国家予算を悪用されないようにしなければ」という意識が根強かったものの、第2次世界大戦(1939~45年)が勃発し国民総動員で戦う時代になると、「すべての人に与えられる一つの権利」として次第に認識されるようになりました。
戦時中、オックスフォード大学ユニバーシティ・カレッジの学長だった、経済学者のウィリアム・ベバリッジが、政府から社会保険制度の状況を検討するよう依頼されます。1942年に発表された「ベバリッジ報告書」は、すべての人の疾病を予防・治療する保険医療制度の設立を提唱していました。
1945年の総選挙で、この報告書の実現をマニフェストの一つに掲げて戦ったのが野党・労働党でした。第2次大戦で英国を勝利に導いた宰相、ウィンストン・チャーチルの率いる保守党を打ち破って政権に就いた労働党は、1946年に国民保健サービス法(National Health Service Act)を成立させます。その2年後、NHSと呼ばれる国民医療制度がいよいよ始まりました。
NHSは地域ごとに4つ(イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド)に分かれて運営されています。合法的に英国に滞在する外国人も加入できますが、2015年以降、欧州経済領域(EEA)以外の国籍を持つ移民の場合、査証取得・延長時にサービス利用料として年間150~200ポンドを支払うことが義務付けられました(永住権保持者は含まれません)。
最近は「常に危機状態」
ここ数年、NHSの財政難や人手不足、混雑した病院の内情を伝える報道をよく目にするようになりました。
NHSは今、膨れ上がる医療のニーズに病院側が対処しきれず、苦境に陥っているのです。
政府の公的サービスへの支出額の中で、NHSへの拠出は30%にも上りますが、支出が増えている大きな原因の一つは高齢化です。医療技術の進歩で、70年前と比べて平均寿命が13歳も伸びています。
65歳以上の人口比率が増加の一途をたどっており(2015年では約18%)、高齢になるほど長期的な疾病(糖尿病、心臓病、認知症など)の比率が高まっていきます。また、平均的な65歳のNHSでの医療ケアにかかる費用は30歳の2.5倍になるそうです(BBC ニュース、5月24日付)。
新薬の価格高騰、政府の緊縮財政でNHSへの予算の増加率が抑えられていることも運営を圧迫しています。緊縮財政策は、高齢者に対する自治体の生活支援サービスの削減にもつながりました。
NHSの恩恵を何年も受けてきた筆者は、「すべての人が無料で利用できる」という伝統をぜひ死守して欲しいと願っているのですが、担当の家庭医(GP)への予約が取りにくく、予約時にクリニックに行っても長い間待たされることが続くと、NHSも「そろそろ限界に来ているのかな」と思ったりします。
キーワード
Beveridge Report(ベバリッジ報告)
経済学者ウィリアム・ベバリッジが委員長となった「社会保険及び関連サービス各省連絡委員会」が、1942年に社会保障制度の拡充のために提出した報告書です。健康保険、失業保険、年金などを、すべての国民が対象となる統一制度として提唱しました。「ゆりかごから墓場まで」と言われる、第2次大戦後の社会保険制度の土台となりました。
編集部より;この記事は、在英ジャーナリスト小林恭子氏のブログ「英国メディア・ウオッチ」2018年8月8日の記事を転載しました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、「英国メディア・ウオッチ」をご覧ください。