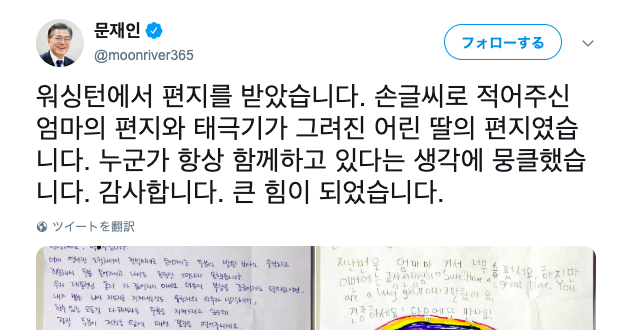平成から令和への代替わりの行事のクライマックスは、三種の神器の継承であるし、それをどのように行うかは政治問題にもなっている。その一方、三種の神器がどのようなものかとか、その歴史的な経緯については、あまり分かりやすい報道がされているとは思えない。そこで、外国人にも分かるような説明をしてみようと思う。

昭和天皇崩御直後、平成天皇即位前に行われた「剣璽等承継の儀」(1989年1月7日、官邸サイト)
私は皇室を日本の国の独立と統合に不可欠なものとして位置づけている。しかし、その権威を神話の中に求めてしまっては、国際的にも、宗教的なものも含めて多様な価値観を持つ人に対して説得力が無い。
もちろん、『日本国紀』のように、日本の建国史がよその国のように身も蓋もない歴史ではなく、神話のなかにだけ認めるからこそ貴重な存在なのだという意見もあろうが、私はそういう意見ではない(『「日本国紀」は世紀の名著かトンデモ本か』(ぱるす出版)。
そして、こんどの週末あたりから書店に出る『令和日本史記』(ワニブックス)では、皇室に最大限の敬意を払いつつ客観的に説得力の高い皇室の日本人の歴史を綴ったつもりだ。ここでは、そのなかで三種の神器に触れた部分をもとにして、書いている。

三種の神器の想像図(Wikipedia:編集部)
「八尺瓊勾玉」、伊勢神宮の「八咫鏡」、熱田神宮の「天叢雲剣」をもって三種の神器という。中世から皇位継承に不可欠なものとされ、源平の戦いや南北朝ではその争奪戦が繰り広げられたし、太平洋戦争では、伊勢神宮や熱田神宮がある伊勢湾にアメリカ軍が上陸する恐れが終戦の決断を後押しした。
しかし、不思議なことに古代史のなかでの位置づけは不明確なのである。『古事記』では天照大御神が天孫降臨の際に瓊瓊杵尊に「八尺の勾玉、鏡、草薙剣」を授けたとされているのだが、『日本書紀』では、「一書にいう」ということで「天照大神が天津彦彦火瓊瓊杵尊に、八尺瓊の曲玉及び八咫鏡・草薙剣、三種の宝物を賜わった」とあるから、編纂者としてはこれを公認しなかったということだ。
『日本書紀』では崇神天皇のときに、崇神天皇が天照大神の威光を恐れて天叢雲剣と八咫鏡を宮の外に出し、それが伊勢神宮に落ち着き、天叢雲剣はヤマトタケルに貸し与えられたのち、熱田神宮に落ち着いた。天皇の即位儀礼では、八尺瓊勾玉の本物と天叢雲剣と八咫鏡については、その代用として「形代」とが使われる。
いつ皇位継承にあって三種の神器が必要な道具として定着したかは不明である。持統天皇の即位のときに、中臣氏が寿詞を読み上げ、忌部氏が鏡と剣を奉ったとあるが、そこに勾玉はないが、平安時代の中ごろには皇位継承に不可欠なものとして意識されるようになったらしい。壇ノ浦で安徳天皇が入水するときに剣の形代は失われたが、八尺瓊勾玉は浮いているところを救われた。
見てはならないものとされているが、冷泉天皇が見ようとして止められたという話はあるがどうなのだろうか。草薙の剣は熱田神宮でこっそり見たという記録があり、銅剣のようだ。また、八尺瓊勾玉は壇ノ浦で拾った武士が開けたら複数個の玉があったという話もあり、昭和天皇の即位礼のときに手で持って運んだ人の証言によると子供の頭くらいの感触だったそうである。
八咫鏡は明治天皇の天覧に供したというが、中身まで見たのかは分からない。森有礼が見てヘブライ文字が書かれていたとかいう人もいるが怪しいものだ。ただ、伊勢神宮は火事に何度もあっており、もとの寸法とされていたのに比べて現在の容器が小さいので焼けたという人もいるし、形代は焼けたことがある可能性がより強い。
それでは、この三種の神器という考え方が、どこから来たのか。『日本書紀』には、「魏志倭人伝」でもおなじみの伊都国王のエピソードがある。仲哀天皇が来たので大きな賢木を根から引き抜き、船の舳先に立てた。その際、上枝には「八尺瓊」を、中枝には「白銅鏡」を、下枝には「十握剣」を、それぞれかけて下関海峡の彦島へ迎えた。そして、伊都国王は「私がこれらの物を奉りますのは、天皇が八尺瓊の勾っているように、お上手に天下を治めて頂きたいからです。また白銅鏡のように、よく山川や海原をご覧頂き、十握剣を引っさげて天下を平定して頂きたいからです」といった、とされている。
これなどをみると、「三種の神器」というものがまとまった形で王位継承の儀式に使われるというのは、筑紫地方に始まった風習が朝廷で採用されたのでないかという可能性も強そうだ。