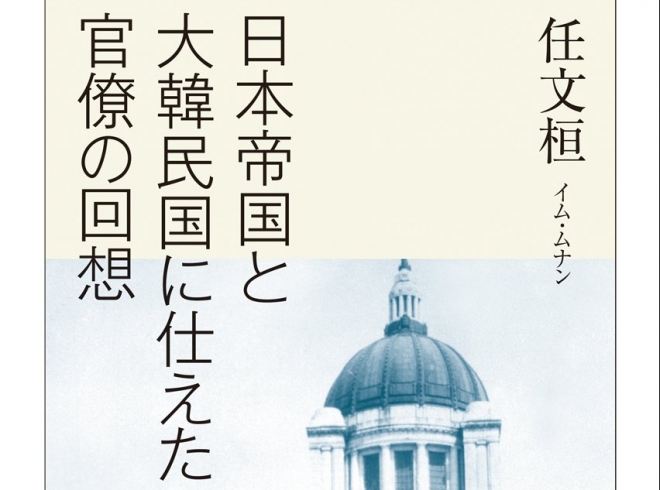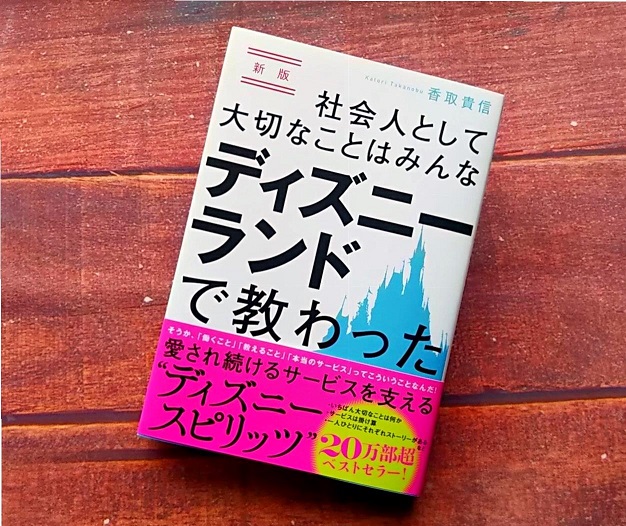『日本帝国と大韓民国に仕えた官僚の回想』(草思社。原著は1975年刊)を読んだ。首都大学東京の鄭大均教授の序文によれば、著者の任文恒(1907年-93年)は16歳で来日し、新聞配達、人力車夫、掃除夫などで生活と勉学の糧を得、また多くの日本人の善意にも支えられて東大法学部に進み、在学中の1934年に高文試験に合格した苦学の人だ。
拓務省から朝鮮総督府に出向して江原道鉱工部長で終戦を迎え、戦後は李承晩政権下で商工部次長や農林部長官を歴任した。が、任氏はその「職務を通して朝鮮人の利益拡大と人権向上に努めたものの、彼らからは支配者の走狗」と見做されたと述べる。同書は先の戦争前後の朝鮮半島で日本と韓国に仕えた官僚バウトクを主人公にしているが、紛れもない任氏の伝記だ。
任氏はバウトクが、北朝鮮人民軍が南を占領した1950年6月末から10月初めまでの3カ月間、人民軍とそのシンパに追われ、幾度も生命の危険に晒される状況を生々しく描くが、奇しくも6月30日の朝鮮日報に、69年前のその同じ3カ月間を回想したコラム2編、「人民軍統治下のソウル、地獄の3カ月」と「朝鮮戦争世代の回顧録に見る『声なき父親』たち」が掲載された。

破壊されたソウル市内(1950年11月米軍撮影、Wikipedia:編集部)
コラム2編は「地獄の3カ月」(以下、同様)が人民軍の非道さとその間の韓国人の心の移ろい、「声亡き父親たち」(以下、同様)が「お前はどっちの味方なのかと追及するのではなく」、「敵味方の二分法から脱し、今の我々のことを考えてみよう」ということがテーマで、実に考えさせられる内容だ。
今や米朝のトップが朝鮮半島の非核化問題を直接やり取りし、G20でも存在感のまるでない文大統領だが、本稿では、この時期に朝鮮日報が載せたこれらコラムの意義を、バウトクの回想も絡めて考えてみたい。
■
バウトクが人民軍に目を付けられたのは、彼が終戦で朝鮮総督府の職を失った後に住んでいた、米軍政府からの借家(日本人家屋)の70坪ほどの空き地で「ダリア栽培の他に200羽の鶏を飼っていた」ためだった。人民軍によって刑務所から解き放された、「近所に住んでいた共産主義者」がバウトクを捉まえて「人民裁判に掛けよう」としたのだ。
バウトクは6月28日に家族を連れて逃げ、10月4日に韓国軍がソウルに戻るまでの3カ月間、人民軍とその協力者らに追われることになる。人民軍は南を制圧して直ぐに首実検を行い一般市民に身分証明書を配った。バウトクのように身分証明書を持たない者は、頼った先々の密告に怯えながら逃げ続けるか、捕まって人民裁判に掛けられるかしかない。
「地獄の3カ月」は、ある人民裁判の様子が次のように描く。
機関短銃を背負った人民軍が青年数人を連れてきて、群衆に向かって反動分子かと尋ねた。皆が呆気にとられる中、1~2人が悪質な反動分子だと言うと、容赦なく銃殺した。
白色テロ時代の台湾もそうだが、知っていて通報しない者をも罪に問う密告社会が共産主義社会の特徴だ。共産ソ連に端を発し、毛沢東の中国も金日成の北朝鮮も、また若い時をソ連で人質同様に過ごし、帰国後の中国国民党や台湾で永らく特務を取り仕切った蒋経国もこれを活用した。
6月28日の様子を「地獄の3カ月」は「ソウルの通りでは赤旗を振り、万歳を叫ぶ人々が現れ、中には前日まで右派の大韓青年団の腕章を付けていた青年もいた」し、「学校に北朝鮮国旗がはためき、男女の学生らが人民共和国支持のデモを毎日のように行い」、「大韓民国の長官、学者がラジオに出演し、李承晩逆徒を非難した」と書く。
だが、人々は「時がたつにつれ、彼らのたちの悪さ、残忍さ、容赦なさ、虚偽宣伝、扇動にうんざりし」、「人民共和国を経験し、骨身にしみて大韓民国が懐かしい」と思うようになる。筆者は、台湾人が国民党軍を迎えた後に「犬が去って豚が来た」と嘆じた情景と余りに酷似しているので驚いた。
それにしても筆者が理解できないのは、韓国人が日本統治期でなく、まだ多くのソウル市民が残っているのにも関わらず漢江の橋を落として真っ先に南に逃げ、多くの市民を北の攻撃に晒して犠牲にした李承晩の大韓民国を懐かしんだことだ。
さて、そんな「声亡き父親」の一人に対して、「3カ月も我慢できずに敵に加担したというのか」と「国軍が失地を回復した後」で、父親の同僚が「附逆者(反逆加担者)」のレッテルを貼った。が、「附逆者の息子」は「3カ月になるか、3年になるかは誰にも分からないじゃないか。誰が望んで敵に加担するものか、と心の中で抗弁した」という話が出て来る。
別の「声亡き父親」は「絵画と書芸に才能があった」ので「人民軍に連行され、プラカードやらポスターやらを描いた」。が、「避難した人々が戻ってくると、父親は拘束され、厳しく責められ」たが「ポスターを描かせられた人のことも自分を拷問した人のことも恨んではいなかった」。娘は「人民軍の統治下では・・誰もが知らず知らずのうちに協力させられた。父はただ家族を養いたかっただけだった。左も右もない天国で安らかに暮らしてほしい」と書いた。
筆者は朝鮮日報のこれらのコラムを、文在寅の「積弊清算」や一連の反日政策と、廬武鉉の「親日反行為者財産国家帰属法」などに対する強烈なアンチテーゼとして読む。文と廬に糾弾される側も「誰が望んで敵に加担するものか」と言いたいに違いない。例えば、ドイツ占領下に暮らしたパリ市民にしても、他に取るべき途があったならそちらを選んでいただろう。
しかし、生きんがために信条を枉げて望まぬ途を選んだとして、それを70年、80年経っても非難し続ける政権は文政権を措いて他にない。まして日本に国際法上の非は今も昔もない。だからこそ「敵味方の二分法から脱し、今の我々のことを考えてみよう」とするこのコラムは貴重だ。鄭大均教授も次のように任氏の書を評している。
加害・被害者史観が、人間を弁別し、他者とされるものを理解しようとするよりは断罪しようとするものであるとしたら、ここに見られるのは、自己と他者の間の対話の態度であり、任文恒にそれが可能だったのは、おそらくは氏自身の中に、その両者が共存していたからであろう。
朝鮮日報に掲載された上記2編のコラムを読んで、筆者はその内容にほぼ賛同すると同時に、韓国人にも我々日本人と変わらないセンチメントを持つ者がいるんだなあ、と改めて考え直したのだが、バウトクと李承晩の次のやり取りも日本人であることを誇らしく思う一文だ。これを引いて稿を結ぶ。
李大統領:それで君は、今までどんな仕事をして来たのかね。
バウトク:日本時代には、学務、地方、郡守、産金、鉱山、予算、機械、物資配給、物価公定等の諸行政に携わり、今は鉱振会社の仕事をしております。
李大統領:時に君は、金にきれいな人だと言われているね。
バウトク:日本時代に役人をした人は、みな金にはきれいです。

高橋 克己 在野の近現代史研究家
メーカー在職中は海外展開やM&Aなどを担当。台湾勤務中に日本統治時代の遺骨を納めた慰霊塔や日本人学校の移転問題に関わったのを機にライフワークとして東アジア近現代史を研究している。