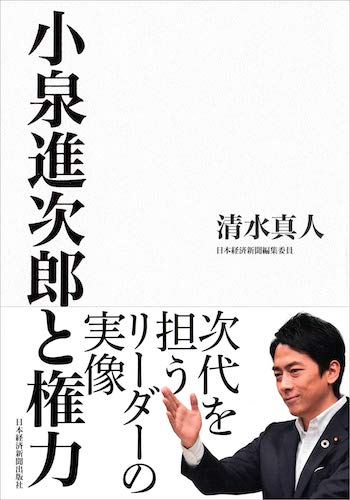テレビやネットにおける小泉進次郎氏の話題は、「のどぐろ」や「セクシー」をはじめとするポエム的な言動、あるいは元首相の父、著名キャスターの妻を絡めたヒューマンストーリーといった表層的なものにとどまりがちだ。
しかし、そこは前著『平成デモクラシー』で、統治システムという独自視点から平成の政治を振り返った著者だ。類稀なるリーダーシップを誇った小泉政権時代を知り尽くし、アカデミズム的な理論的考察と抜群の取材経験を元に、ありがちな「進次郎論」とは一線を画して政策視点をぶらさない。
たとえば、同じ長期政権でも、安倍政権と小泉政権では、「経済政策の司令塔」たる経済財政諮問会議の回し方が異なる。
「事前調整型」の安倍首相と「トップダウン型」の小泉首相。復興政務官として初めて行政府入りした青年議員の視点からリアルに描き出し、比較するところは、トップのリーダーシップ手法を分析する上で非常に興味深い。「権力のインフラ整備に強い意欲」(本書あとがき)が滲み出ていると指摘するところも、他で聞かない「進次郎像」だろう。
とはいえ、スマートな仕組み論の裏側は、ドロドロとした思惑や利権がうごめく百鬼夜行の世界だ。必然、本書はそこも漏らさない。
党の農林部会長として農協改革に取り組んだ終盤、「負けて勝つ」とほろ苦の心境を記者団に語ったのは周知の通りだが、族議員の重鎮への根回し、業界団体のキーマンとの厳しい交渉に苦悩するあたりは、成果の是非は別にして、進次郎氏が若くして“政治的技術”をそれなりに身につけてきたのは確かなようだ。
一方で、近年は政界遊泳術の巧みさが鼻につき始め、私が以前書いたように「化けの皮がはがれた」のではという進次郎評もかまびすしくなっている。「天才子役」と揶揄されてきた一因が、周囲の有能なブレーンが「演出家」として存在している側面が透けて見えるからなのは否定できまい。
だからこそ、本書を手に取った時、進次郎氏が政治家としてどのような国家、社会を思い描いているのか、誰かが振り付けたのでない「本音」、あるいは心底からにじみだす「政治観」に、著者がどこまでえぐり出せるのかもっとも興味を持っていた。

環境省公式YouTubeより:編集部
著者の筆致からは、将来の進次郎氏に父の時代の再現を期待しているからか、いささか“傅役(もりやく)”のようなやさしい眼差しを感じなくもないが、さしもの著者の取材にも、進次郎氏本人は簡単には隙を見せなかったようだ。
ただし、政治観の根底にある思いの手がかりになりそうなのは“小泉版・日本改造論”のエッセンスとも言えるこのセリフだ。
「個人主義は日本では否定的に受け止められがちだが、僕はすごく大切だと思う。日本の集団のまとまりの良さは大切にしたいが、強い個を創らなければ、強い集団も生まれない。人口が減っていくなか、自由闊達な議論や自己主張がなければ、イノベーションだって生まれない」(P218より)
「個」へのこだわりは、悪く言えば自己責任論、良くいえば新自由主義的な価値観だろうか。父の影響、米留学時代の異邦人としての孤独なども投影してのことなのかもしれないが、多様性や環境問題に親和性があるあたりは父ともやや異なるリベラルさも滲み出る。
いずれにせよ、宰相候補として特に重要な、憲法、外交、安全保障といったど真ん中のイシューに関する価値観はまだまだ解明の余地は大きいように見える。
その点、何人かの有識者が勧めるように進次郎氏自身こそ自らの手で政策本を出すべきだろう。安倍政権の終焉も近づき始めたなかで、2020年代の早いうちに決起する気があるのならばなおさらだ。
もちろん、30代のうちに350ページもの“政策本”を日経のベテラン記者に書いてもらうだけでも、突出した存在感であることには間違いないが、戦後政治史を振り返れば、田中角栄は『日本列島改造論』(1973年)、小沢一郎は『日本改造計画』(1993年)というベストセラーをそれぞれ出している。
後者は、小泉政権の頭脳だった竹中平蔵氏らも執筆に参加していたが、進次郎氏も自著を出すとなれば、政策テクニカルの部分は、竹中氏らの“傅役”の手を多少は借りることになろう。
ただし、当然のことながら、そこでも“傅役”の筋書きに沿ったセリフを述べているだけでは天才子役から脱皮したとはいえない。根源のところ、己の政治哲学、国家観をさらけだして国民に問えるかどうかだ。
果たして進次郎氏が決起する頃、著者が初入閣以後のストーリーを描くとすれば、本書の続編はどんな展開になるのだろうか。いや、描くに値する宰相候補になっているのだろうか。