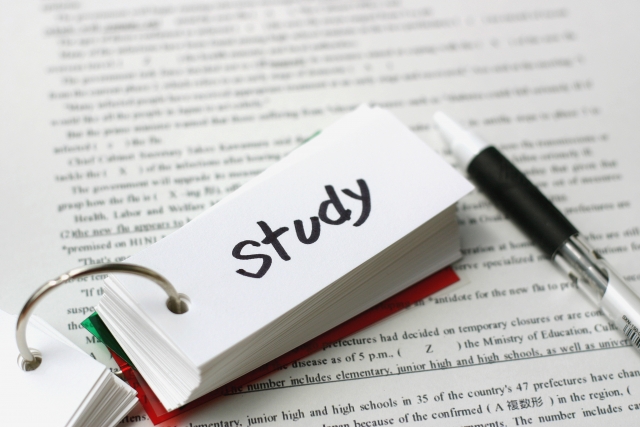最近二つの教育に関する気になる報道に接しました。一つはOECDが2018年度に実施した国際学習到達度調査で日本の読解力が世界15位と落ち込んでいること、もう一つは大学入試改革の目玉の一つだった国語と数学の記述式問題導入の延期の可能性であります。後者については近日中に文科大臣が何らかの発表をすると思いますが、どうも外堀から埋められた感が強く、萩生田光一文科大臣の歯切れもかなり悪い状態であります。

(写真AC:編集部)
まず国際学習到達度調査での日本の読む力の落ち込みについて考えてみます。日経には「調査結果からは表現力・記述力の不足という従来の課題に加え、デジタル時代に必須の『情報を評価する力』などが不十分な実態が浮かぶ。学校現場では、こうした力の育成が新たな課題になりそうだ」とあります。
私見ですが、溢れる情報量に対して子供たちがそれを精読しなくなり、結論だけを求めるようになったことに原点があると考えています。そしてそれは子供の世代に始まったわけではなく、その親の世代がそういう子供を育てたと考えています。この調査は15歳の子どもが対象。つまり、18年調査時点で2003年生まれの子ということになります。
日本で携帯メールが始まったのが99年。01年に3Gサービスが始まるなどIT化が芽生え始めた時期であります。08年にはツィッターが日本上陸し、親たちは本格的に始まったテキストメールやSNS時代を享受したのです。それに対して私はずいぶん前から警告してきたことがあります。ショートメッセージは人間を退化させると。テキストのやり取りは脳の奥底まで思考回路を廻す必要がなく、本能的(あるいは動物的)なやり取りが主体となるため、物事を深く考える必要がなくなってしまうのです。
前回のアメリカの大統領選挙でフェイスブックなどを利用した選挙工作の疑惑であるとか、IT先進国を自負する韓国でろうそく集会が年中行われるのは思想の深堀がなく、表面的なお誘い文句に「いいね」を押してしまう短絡的行動が生み出した悲劇であると考えています。
日本も当然ながらその問題にぶち当たっています。例えばネットニュースの記事量が一時期、異様に圧縮されていました。つまり読みたいというニュースをクリックしてもほんの数百字の記事の前書き部分ぐらいの分量しかなかったのです。理由は「そんなに長い記事は誰も読まない」であります。(最近は少し変わってきたと思いますが、逆に終わりまできちんと読む人がどこまでいるのか興味あるところです。)本当は「読まない」のではなく「読めない」であり、そんな「活字離れした日本人」が育てた子供たちの試験結果が今回のものだったと考えています。
次に大学入試改革の行き詰まりです。ポイントはどこにあるのか、朝日新聞の社説には「一番の心配は、受験生の自己採点と実際の採点とが大きくずれることだ。昨年の2度目の試行調査でも『不一致率』が3割に達した」とあります。つまり記述式回答の場合、50万人の受験者に対して1万人の採点者(塾の講師などのアルバイトが大挙動員されます)の採点基準のばらつきという中学生でもわかる初歩的問題がクリアできていないのであります。
記述式には記述技術と記述内容による採点者の感情が組み合わさることにより不一致が生じるのだろうと思います。更に受験者の自意識(パーフェクトだったとかよくかけた、という自信など)の問題もあります。どっちもどっちなのでしょう。これを改善するには申し訳ないですが、AI化するしかないと思います。50万人の平等な採点に人間が1万人で対応する現状において朝日の言う公平性なんて逆立ちしてもできるものではありません。ならば回答はすべてパソコン入力させることが前提になります。
そういえば上述のOECDの調査もパソコン試験だったことが日本の受験生に不慣れであったとも報じられています。このあたりの投資はもう少し進めるべきでしょう。
最後に日本の試験制度について答えを一つに絞らせる理由は採点者への負担減が私の幼少期の頃から言われていた話です。そのために四択も当たり前のように取り入れられてきました。ではなぜ四択なのか、六択ではダメなのか、という発想は誰もしていません。(八択だと受験生が時間内に試験が終わらないという問題が出そうなので私はせめて六択はアリではないか、と考えています。)
教育界は日教組効果もあり教育への姿勢が硬直化してしまっています。本来であれば教育者を再教育することが一番重要なのかもしれません。
では今日はこのぐらいで。
編集部より:この記事は岡本裕明氏のブログ「外から見る日本、見られる日本人」2019年12月15日の記事より転載させていただきました。