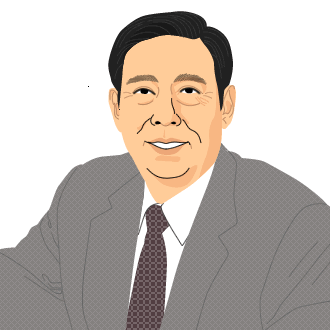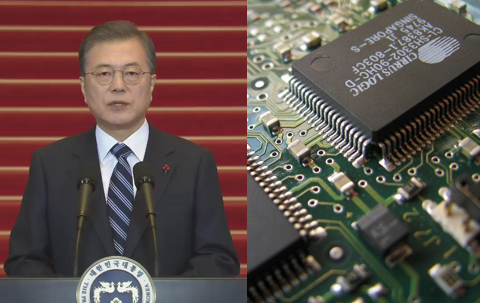どんなときに病院に行くべきか。何か不快な症状があるとしたら、その症状をやわらげるべきか。もっと詳しい検査を受けた方がいいのか。医療には、こうした細かく、しかし重要な「選択」が数え切れないほどあります。
もちろん、医療における「選択」の多くは、患者さん側に全面的にはゆだねられてはいません。検査が必要かどうか、検査結果を踏まえてどんな治療が最適なのか。その判断には、高度に訓練された専門家の知識が必要になります。
専門家からの説明を聞いた上で、提示された選択肢の中から、患者さんがある検査や治療を理解し、同意することになります。これを、専門的な言葉では「インフォームドコンセント」と呼びます。

photoB/写真AC(編集部)
多くの選択肢から、治療をしないという選択を含めて、何を選び取るべきか。医療が専門化し、高度化した社会では、ひとつひとつの意思決定は個人のリテラシーにより、快適なものにもなれば、困難なものにもなります。
適切な選択をするためにはどうすればいいのか。ひとつは、知識を増やすことであるのは言うまでもないでしょう。しかし、知識だけを増やしても、「健康のために○○しなければならない」「あと○キロ痩せなければならない」ということばかりが目標になってしまい、これでは、幸福に生きるための手段である「健康」が目的のようになってしまいます。土台のないところに知識だけを増やしていっても、数値に振り回されるだけです。
また、健康不安をあおるテレビなどに際限なく影響されてしまうこともあるでしょう。必要なのは、「自分はどういう人間で、どう生きたいのか、何をすると幸せなのか」という「価値観」を自分で形作ることだと思います。普段から、「どう生きて、どういう形で死を迎えたいか」ということを考える習慣をつけたり、周囲の人と話し合うこともいいでしょう(厚生労働省も、人生の最終段階のケアを家族や医療者と話し合う「人生会議」を推奨しています。ポスターの炎上は記憶に新しいのではないでしょうか)。
しかし、筆者が個人的に困難を覚えるのは、これから、「マクロな自分の価値観」を信じられる時代がどれだけ続くのか、ということです。これまでは、死や病気を、哲学的な事柄として扱う面もありました。最近では、遺伝子や化学物質のことが徐々に明らかになってきて、乱暴な言い方ではありますが、人間の「思考」も、脳内伝達物質の産物であると考えられるようになってきています。
これまで、医学ではないと考えられていた分野が医学として捉え直され、「診断」や「治療」といった医学の文脈で考えられるようになってきました。こういった事態は「医療化」と呼ばれ、1976年に、ウイーン生まれの思想家イヴァン・イリッチは「脱病院化社会」で、医療が人間社会の多くの事象を決定するようになり、人間は主体性を奪われ、統計学的に管理される対象と考えられるようになったことを批判的に考察しています。今から考えると、随分荒い批評にも見えますが、過剰診療の出現や製薬産業の隆盛も予見している興味深い著作です。
わたしは、「医療の発展により、人が主体性を奪われる」とは考えていません。健康になることは、より主体的に生きることを可能にするといえるでしょう。しかし、高度化した医療が生活のあらゆる側面に、とくに意思決定に関わってくるということは、それだけ選択が難しくなるということでもあります。
いまや、子どもを産むか産まないかということも、医療による決定がかかわってくることもありますし、今日何を食べるか、何歩歩くかということも「医療」と無関係ではありません。「医療」が深く浸透し、切り離すことが不可能になったわれわれの生活だからこそ、もう一度「マクロな価値観」を見直してみるべきかもしれません。

松村 むつみ
放射線科医・医療ジャーナリスト
プロフィール