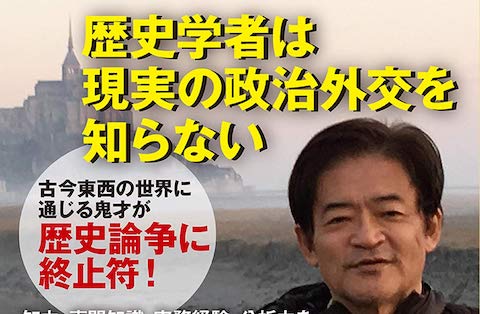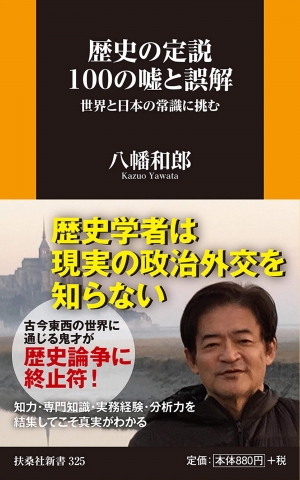本屋で歴史についての本を探すと、いわゆる歴史学者(文献や考古学の専門家)だけでなく、作家、政治家や官僚、ビジネスマン、アマチュア歴史愛好家、さらには、医学とか理系の人々など実に多くの分野の人が書いた本が並んでいる。
私も150冊ほど単行本を出しているが、半分以上が歴史に関するものである。そこで、これまで、唱えてきたことを、ある意味で集大成するつもりで、「歴史の定説100の嘘と誤解 世界と日本の常識に挑む」 (扶桑社新書)という本を出した。
ただし、2ページ見開きで一話が完結しているので、定説への批判と私の考え方を示すだけになっているのは、やむを得ないこととお詫びするしかない。そのかわり、要点はゴシックにしたりしたので、これまで常識だと思っていたことへの問題提起としては分かりやすい本としては評価していただいているようだ。
少し面白いと思った書評がアマゾンに寄せられていて、「『(こう考えた方が)辻褄が合う』というレベルで押し切る論法」とされていた人がいたのだが、これは私も考えさせられた。なぜなら、このように考えるのがいちばん辻褄があるというのは、実務の世界では王道だと思うからだ。
そんなことも踏まえながら、 これを機会に、わたしがなぜ政治・外交・経済の実務家として、歴史を語りたいのかということを少し書いておきたいと思う。
政治外交の現場での分析技術
歴史といってもその関心領域は広いが、主たるものは、政治外交史である。ところが、そういう方面で実際に仕事をした経験からすれば、「定説」にはリアリティがないものが多い。

交渉の裏舞台の写真が話題になった2018年のG7サミット(首相官邸Facebook)
そのように感じたきっかけは、そういう方面で実際に仕事をしていて、歴史学者の「定説」とか世間の歴史ファンの常識には、リアリティがないものが多かったからだ。
そして、現実の政治や外交の現場で、見通しを立てたり、事実関係が分からないときに、どのようにして、推理を行い、対策を講じていくにあたっていくかという手法を歴史についても応用すればいいではないかというのが、私の基本ポジションである。
そのときに、普通は100%確かな情報だけでなく、噂まで含めて情報を幅広く集め、知力・経験・分析結果、そして職業的な勘まで総動員していくつもの可能性を想定し、最適な政策ミックスを複合的に講じるものだ。
現実の外交の世界で、プーチンが何を考えているか、確実な文書や正式の表明がされた場合以外は参考にしないとかいったら、どうなるだろうか。まっとうな外交はできるはずないのは当然だ。
だから、ある噂を耳にしたら、あるいは、たまたま非公表の数字を手に入れたら、何人にも当たって裏を取ったり、どのくらいの可能性で本当なのか意見を聞いたりしたり、その確率を分析評価し、その確率に相応の扱いで対策を取るのである。
そのときに、通説とか定説などない。多くの可能性があるわけである。それでは、そのうち、最有力の可能性に賭けるのかと言えば、そんなことはない。あらゆる可能性に、その重要性に応じた、手を打つのである。
外務省も確実な情報にこだわりすぎで失敗
確実な情報の値打ちについては、実務家の間でも考え方は様々だ。たとえば、日本の外務省は、歴史学者とちょっと似ていて、確実性の高い情報を非常に大事にするし、もっとも大きな可能性に過度に重きを置いた対応をする傾向がある。
公電といったシステムでは、外交官が誰に会ってこういう風に聞いてきたとか、信頼できる主要紙の記事にこのように書いていたとかいうことしか載らないことが多く、噂話など本省に報告されないことが多い。さらに、外務省本省でも、「もしかして」という可能性は排除しがちだ。

kawa*******mu/写真AC
古くは駐スウェーデン大使館からのソ連参戦の可能性についての公電があったのにスルーしたことがある。2016年の米大統領選挙ではトランプの勝利の可能性を低く見過ぎた(駐米大使館はわりにしっかり対策を講じていたと評価されているが)。
あるいは、私が関与していた件では、通商交渉についてのある会議で、私はまとまらないと言い続けたが、外務省も通商産業省もまとまるという予測に応じた対処をしたが、結局、私が予想したような展開になってまとまらなかった。
たとえば、フランスで「反日」の評価がついていたクレソンという女性政治家が首相に就任するという噂を私はパリから東京に報告して対策を取るように進言していたが、外務省はしていなかったこともあった。
私は誰か関係者から聞いた話とか、コンフィデンシャル情報を集めた情報誌とかで集めた情報を、いろんな方面の専門家や政官界の関係者にぶつけて信頼性を計るのが好きだったから、予想外の展開には強かった。
天安門事件のときは、天安門広場そのものでは死者はゼロかほとんどいなかったというのは、ほぼ常識化している。当時も細かく情報を集めたらすぐにそうだと分かったが、大虐殺というイメージに世界中の外交官も引っ張られていた。
今回の新型コロナでもそうだが、大事件は、だいたい、確たる確実な情報もないまま予想外に突然に起きるのである。しかも、途中で何があったかなど謎のままで終わることも多い。
逆に、こういうことだったらしいと、後講釈で政治家が行っているという証言とか、マスコミの分析に載っていたとしてもそれが正しいなどと言う保証はない。
いま本能寺の変が起きても真実は分からない
たとえば、いま、本能寺の変のようなクーデターがどこかの国で起きたとして、その本当の動機は明らかになるのだろうか。いろんな関係者が発言するだろうが、本当かどうかなんて分からない。

『真書太閤記 本能寺焼討之図』(渡辺延一作:Wikipediaより)
そして、私はこう思うとか、誰それがこういってたとかいう日記だとか手紙が100年後に発見されたら、それは動かぬ証拠になるわけでもあるまい。しかし、私の書いたアゴラの記事だけが発見されたら、それが唯一の同時代人の証言とし定説になるのかもしれない。
それよりは、さまざまな周辺状況を集めて、さまざまな可能性を評価し、そして、多角的な検証を得た、いちばん辻褄が合うような推測というものこそ、実務の世界で行われている解析にちかいのでないかと思うのである。
作家はどうだとか、学者はどうかとか、また怒られそうで、あまりいいたくないが、一般にある世界の方の考えることは、それぞれにその職業の世界での評価基準がなにかで決まると思う。
作家の場合は、売れるかどうかだ。一般に奇抜で面白い説や、特定層の読者が喜ぶとかいうのが好都合だ。美女が真犯人だったり、南京事件はなかったとかいうと売れる。
学者はどうかといえば、学会で業績として認められるかどうかだ。たとえ、妥当であっても、『日本書紀』に書いてあることはやっぱり正しそうだなどといっても評価されない。新しい文書や遺物を「発見」したのでなければ、学者の仕事にならないし、学会主流派のお気に召さないとダメだ。そして、新しい発見をしてマスコミが囃し立ててくれると大発見になって、定説とまでは言わなくても有力説くらいには扱われたりする。
もちろん、実務家は、自分の仕事上のポジションが有利になるような解釈をしがちだ。実務家だから、偏らない普遍的な見方ができるということではありえない。
ただ、これだけは言える。歴史に限らず、真実を探求するためには、さまざまな分野の専門家が、それぞれの知恵を持ち寄って、切磋琢磨するべきものではないか。あらゆる物事がそうであるように、そこには「最終審判者や最終法廷などない」ということであり、さまざまな人が上から目線になることなく謙虚に議論することだと思う。