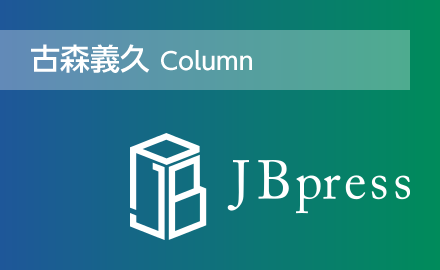今回のコラムにべートーヴェン(1770~1827年)とモーツァルト(1756~91年)に登場をお願いした。ここでは前者がボン出身のドイツ人であり、後者はザルツブルク出身のオーストリア人といった彼らの出自を確認するつもりはない。音楽の世界に大きな足跡を残した2人の天才作曲家がいなかったならば、音楽の世界はどれだけ寂しいものとなっていただろうか。彼らのいないクラシックの世界は考えられないだろう。しかし、その2人の作曲家を音楽の歴史から追放すべきだと主張する人が出てきたのだ。

ザルツブルクのモーツァルトの生家(moomusician/iStock)
そのような暴言を吐くのが音楽の世界に疎い素人ならばその無知を笑って聞き流しておけばいいが、英国の名門オックスフォード大学の音楽教授陣の中から、そのような主張が聞かれるのだ。彼らによると、両作曲家とその音楽は奴隷制度時代の世界から生まれたもので、だから大学のカリキュラムを変えるべきだと主張している。英語でいえば、decolonise the Syllabus(授業計画の非植民地主義化)だ。
ベートーヴェンとモーツァルトの音楽を今更説明する必要はないだろう。問題は、両作曲家とその音楽のどこが“植民地主義的”かについて、当方は説明できない。彼らが生きていた時代、欧州の列強はアフリカ大陸やアジアに進出し、地下資源など富を奪うだけではなく、現地人を奴隷として酷使してきた植民地時代に突入することは事実だ。
オックスフォード大学音楽部教授の中には「ベートーヴェンもモーツァルトの音楽も白人支配の植民地時代(White hegemony)から生まれてきた音楽だ。その音名・階名表記や楽譜は植民地主義的だ。その音楽を教える教師たちは学生たちに白人支配の植民地主義的、人種差別的世界を教えることになる」と考え、その変更を提案する学者がいる。
次の点は少々、理解に苦しむ。「ベートーヴェンとモーツァルトの白人音楽を聞けば,、有色系学生は過去の辛い時代を思い出して苦しくなる」というのだ。ベートーヴェンとモーツァルトの音楽を聴いて、心理的、精神的ストレスを感じて苦しんだ、という黒人音楽学生の証を聞いたことはない。植民地時代の祖先の痛み、苦悩が心的外傷後ストレス障害(PTSD)となってその有色系音楽学生を苦しめてきた、という話も聞かない。
音楽学の学者たちがいうように、黒人音楽学生が植民地時代を思い出してモーツァルトの音楽を聴きながら怒りが湧いてきたという証言を聞いたことがあるだろうか。ベートーヴェンもモーツァルトも少々奇人であり、隣人との付き合いはうまくなく、常に引っ越しを繰返してきたが、彼らの音楽を聴いて精神的に苦しんだ隣人がいたとは聞いたことがない。
音楽教授の主張を報じた英紙デイリー・テレグラフ(3月27日付)によると、「ベートーヴェンとモーツァルトの音楽に代わってポップミュージックを教えるべきだ」と提案しているという。もちろん、このような主張を展開する教授陣は一部かもしれないが、その考えは滑稽さを超えて、少々パラノイアだ。
音楽の効用は誰も否定できない。その音楽が素晴らしければ、それを聴く人にいい影響を与える。妊婦はモーツァルトの音楽を聴けば胎児教育にいいといわれてきた。南米出身のローマ教皇フランシスコは心が沈む時、バッハの音楽を聴けば癒されるという話をこのコラム欄でも紹介した。ベートーヴェンの交響曲第9番の「歓喜の歌」を聞いて涙を流す人をみたことがある。一方、名門大学の音楽学の教授らはそうではなく、「暗い植民地時代を思い出し、苦しくなる」というのだ。人にはそれぞれ独自の感受性があるから、それらを尊重しなければならないが、そのような受け取り方は通常の理解を超えている。
米ミネソタ州のミネアポリス近郊で昨年5月25日、警察官に窒息死させられたアフリカ系米人、ジョージ・フロイドさん(46)の事件に誘発され、米国各地で人種差別抗議デモが行われたが、それを契機として、米国の建国史の見直し論争が出てきた。米国の歴史は「清教徒の約束の地への建国」から始まったのではなく、その150年前、アフリカから連れてきた奴隷が米国に到着した時、1619年から幕開けする」と主張するメディアや学者が出てきたことはこのコラム欄でも紹介した(「米国の『不名誉な歴史の見直し』論争」2020年6月24日参考)」。
米国の影響を受けて、欧州でも過去の歴史の見直しを叫ぶ声が出てきた。具体的には「植民地占領時代」の見直しだ。特に、フランス、英国、ベルギーなど植民地大国だった国では、過去の植民地時代の見直しを叫ぶ歴史学者、メディアが出てきた。
イギリス西部の湾岸都市ブリストルでは奴隷取引業者、エドワード・コルストン(1636~1721年)の像が倒され、ベルギーのアントウェルペンではベルギーの国王、レオポルト2世(1835~1909年)の静止画が剥がされた。同国王はアフリカのコンゴでの植民地政策が糾弾された。植民地化時代では後進国だったドイツでも「鉄血宰相」いう異名を誇ったオットー・フォン・ビスマスク(1815~1898年)の植民地政策の再考が求められ、ビスマルク像を倒すべきかで議論が出てきている有様だ(独週刊誌シュピーゲル2020年6月20日号)。
「歴史の見直し」と言えば、響はいいが、実際は過去の歴史を全て否定することになる。21世紀の立場から過去の歴史を見れば、いろいろな問題点は浮かび上がることは当然だろう。しかし、当時の歴史が21世紀の世界観、歴史観に一致しないからといって否定すれば、歴史の多くの事例はその検閲に耐えられないだろう。
どの民族の歴史にも栄華の時と共に多くの負の遺産があるものだ。それらの長い歴史を経て21世紀の現在が生まれてきたわけだ。過去の負の遺産が気に食わないとして消却すれば、歴史書はきっと薄っぺらい本になってしまうだろう。歴史の年代を暗記しなければならない受験生にとっては助かるかもしれないが、薄くなった歴史はもはや歴史ではなくなってしまう。
ベートーヴェン、モーツアルトの音楽を音楽史から追放すれば、それだけ音楽の文化遺産は乏しくなる。同じように、一時代の歴史観でもって歴史の事例を削除すれば、人類歴史の全容を掌握するチャンスを失うことにもなる。大切な点は、「歴史を審判する」ことより「歴史を直視する」ことではないだろうか。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2021年3月31日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。